
2025/2/26
成長と共に増えていく子どもの教育費を、修学支援制度と私的保障を活用して準備する方法
人生の三大資金の一つである教育費は、成長と共に費用がかさみ、特に受験や進学時にはまとまった支出が見込まれます。教育費にはどのようなものがあるのかを把握し、修学支援制度や私的保障を活用した費用の準備方法について考えていきましょう。
保障に関する疑問や不安を
少しでも解消できるよう、
項目ごとに具体的なヒントを紹介します。
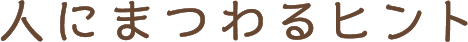
けがや病気のときの治療費はどれくらい?
ライフステージごとの備えは?
人にまつわる保障の疑問にお答えします。

2025/2/26
人生の三大資金の一つである教育費は、成長と共に費用がかさみ、特に受験や進学時にはまとまった支出が見込まれます。教育費にはどのようなものがあるのかを把握し、修学支援制度や私的保障を活用した費用の準備方法について考えていきましょう。

2023/2/14
更新⽇︓2023/07/10( 最新情報に基づき記事の内容を一部更新しました)人生にはさまざまなリスクがあります。死亡や重い障がい、介護が必要になるなどで働けなくなるような大きなリスク以外にも、病気やけがによる入院のリスクなどは、いつ自分におきるか予想がつきません。こちらの記事では、保険・共済は本当に不要なのか、若いうちに保障に加入しておくことのメリットやムダなく選ぶ方法とそのポイントをお伝えします。

2022/7/27
更新⽇︓2023/07/10( 最新情報に基づき記事の内容を一部更新しました) 気象庁の発表によると、昨年は6 月下旬から7 月上旬の高温が特徴的で、まだ十分に暑さへの備えができていない状態で、本格的な夏がやってきました。また、昨年に引き続き今年の夏も首都圏エリアでは電力不足が懸念されており、熱中症への早めの対策が呼びかけられています。今回は熱中症の対策と、リスクをカバーする保障についてお伝えします。
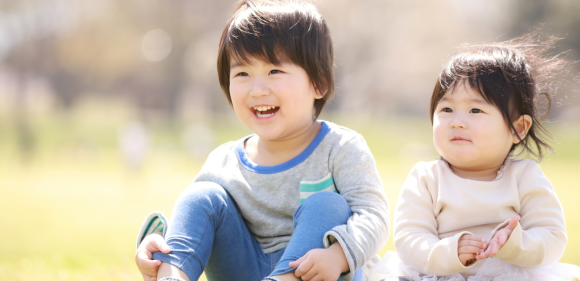
2022/3/8
更新⽇︓2023/10/4( 最新情報に基づき記事の内容を一部更新しました)子育てをしていると、日常の些細なことから漠然とした将来のことなど、多くの悩みや不安がありますよね。それら悩みや不安のすべてに対し、構えることや備えることは非常に難しいですが、もしかしたら保険や共済に加入することで解決できることがあるかもしれません。今回は子どもの心配事や不安を解消するために保障でできることについて紹介します。

2021/11/18
更新⽇︓2023/10/20( 最新情報に基づき記事の内容を一部更新しました)毎年11月から12月頃になると、働く方々の手元に年末調整の案内が届くようになります。 年末調整というと、提出書面がわかりにくく、記入方法も1年に1回の作業なので忘れてしまう、保険会社からのハガキ(保険料控除証明書)が一度に送られてくるので保管や提出漏れがないようにするのが面倒などの理由から、つい手続きを後回しにしたくなってしまいます。 では、なぜ年末調整をする必要があるのでしょうか?年末調整の手続きを正しく行うと、私たちが1年間で払いすぎた所得税を還付してもらえるなど、お財布にも優しい効果があるのです。今回は、年末調整の目的から得られるメリット、特に保障に加入している際に受けられる所得控除について、お話しいたします。

2021/11/9
掲載日:2021/11/09 更新日:2023/01/27長く続くコロナ禍で、学校をはじめ、習い事や塾など、子どもたちの教育環境も大きく変化してきました。ワクチン接種が進み、行動制限が解除された今、少しずつコロナ前の日常が戻りつつありますが、依然として学校の授業体制や行事、また習い事など、子どもの教育環境には一定の制限があるかと思います。今、そして今後の教育環境の変化も見据えて、これから先の子どもの教育費に対する準備のポイントをお伝えします。

2021/6/30
更新⽇︓2025/3/27( 最新情報に基づき記事の内容を一部更新しました)学校を卒業し、社会に出て自分で働いて収入を得るようになり、「そろそろ保険や共済に入っておいた方がいいのかな」と初めて保障について考えている人も多いのではないでしょうか。今までは親に守ってもらえていたけれど、これからは、もしものときに備えておくことも大事になってきますね。ここでは若いうちだからこそ知っておきたい医療保障の必要性についてお伝えします。

2020/12/21
更新⽇︓2024/10/09( 最新情報に基づき記事の内容を一部更新しました)新型コロナウイルス感染症の流行により、私たちの日常生活や働き方、経済活動に至るまで大きな影響を受けました。こうしたウィズコロナ社会における変化の中で、万一の病気やけがに備えるための医療保障について考えてみませんか?

2020/6/1
更新⽇︓2024/8/13( 最新情報に基づき記事の内容を一部更新しました)病歴や持病がある方の中には、保険や共済に加入できるのか心配に思っている方も少なくないのではないでしょうか?最近では、引受基準緩和型といった病歴や持病があっても加入できる保険や共済が増えてきています。今回は、引受基準緩和型の保険・共済(以降「保障」とします。)のポイントと、注意点をお伝えします。

2020/5/1
更新⽇︓2024/08/02(最新情報に基づき記事の内容を一部更新しました)「がんは治る時代」と言われますが、働き盛りの世代ががんになった場合、どのような負担があるのでしょうか。働きながら治療を続けることはできるのでしょうか。治療費など、どのようなお金がかかるのかを知り、がんへの備えについて考えてみましょう。

2020/3/2
元気に生まれてきてくれた赤ちゃんでも、大人と比べると体の機能は未発達で、免疫力も低く病気にもかかりやすいです。病気しがちな乳幼児期に、医療費の負担をサポートしてくれる公的制度や保障があるのはご存じですか?赤ちゃんが生まれたらすぐに備えておけるよう、妊娠中から知っておきたい情報をお伝えします。

2020/3/2
妊娠中に夫婦二人で考えておきたいことの一つが、家計の見直しです。赤ちゃんが生まれると、育児にかかるお金や教育資金、他にもマイホームを考えたりなど、家計のやりくりが変わるだけでなく未来のお金をどう準備するかということも気になってきます。今回は、家族が増えたらどんなお金が必要になるのか、なにを準備したらいいのか、ポイントをお伝えしていきます。

2019/12/16
更新⽇︓2024/01/31( 最新情報に基づき記事の内容を一部更新しました)子どもがすくすくと元気に育つことは、お父さん、お母さんの願いです。だからこそ、子育て中で特に心配なのが、子どもの病気やけが。いつ病気になるかはわかりませんし、予期せぬけがをしてしまうこともあります。療養中は、支える親にとって肉体的、精神的、経済的にも不安ですよね。子どもが入院をすると、家事と仕事と看護に伴う付き添いなどで、家族の負担は大きくなります。毎日の生活の中で起こりうる子どもの病気やけがに慌てず対応できるよう、子どものもしもに備えるポイントを確認しておきましょう。

2017/9/29
更新⽇︓2023/11/6( 最新情報に基づき記事の内容を一部更新しました)医療保障はどうやって選んだらいい?と思われている方に、3つのポイントをご紹介していきます。短期入院は手持ちのお金でまかなうのが基本です。医療保障は、長患いのときこそ威力を発揮するものを選択するのが賢明です。

2017/5/31
更新⽇:2025/8/18( 最新情報に基づき記事の内容を一部更新しました)けがや病気で治療が必要になったとき、「治るのだろうか?」「仕事は大丈夫だろうか?」「家族に負担をかけるのではないか?」など、たくさんの不安に押しつぶされそうになろうかと思います。その中でも、「治療費はいくらかかるのだろうか?」というお金に関する不安も大きいのではないでしょうか。例えば急性心筋梗塞の窓口支払い額の目安は、3割負担の場合約51万円(出典:公益社団法人全日本病院協会「医療費」重症度別2022年)。治療費の高さに驚く方もいらっしゃると思いますが、あらかじめ日本の公的保障を理解し、備えておくことで、お金の心配が少しは解消できるかもしれません。

2017/5/31
更新⽇︓2023/12/28( 最新情報に基づき記事の内容を一部更新しました)もし、あなたが病気になったとき、どこまでの治療を望みますか?「先進医療」を受けることにより病が改善する可能性があるとしたら、あなたは先進医療を希望しますか?昨今では一般的になってきた先進医療。「重粒子線治療」や「陽子線治療」など、メディアでも取り上げられることが増えてきたため、ご存じの方も多いのではないでしょうか。病気になったとき「できる限りの治療を受けたい」と考え先進医療を選択する人も多く、先進医療にかかる患者数、医療費ともに年々増加してきています。

2017/5/31
あなたは今、どのような生活をしていますか?そして、10年後や20年後はどのような生活を送っているでしょうか。「結婚」「子どもの誕生」「住宅の購入」「両親の介護」など、生活環境は変化していることでしょう。その変化に応じてあなたに求められる「お金」や必要となる「保障」は変わっていきます。
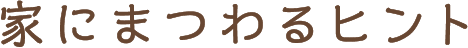
火災、増加する自然災害・・・。
大切な住まいへの備えはどうすれば?
家にまつわる保障の疑問にお答えします。

2024/11/6
更新⽇︓2025/2/27( 最新情報に基づき記事の内容を一部更新しました)2024年1月1日16時10分、石川県能登地方を震源とする最大震度7の大きな地震がありました。新年早々に発生したことへの驚きと、大きな災害が「いつ起きてもおかしくない」ことを思い知らされました。能登半島地震から間もなく1年が経過する今、改めて、被害状況から必要な地震への備えを考えてみましょう。

2023/6/30
更新⽇:2025/6/26( 最新情報に基づき記事の内容を一部更新しました)不安定な天気が多いこの時期は、大雨の被害とともに、落雷の被害も多い傾向にあることはご存知でしょうか?今回は落雷被害の例とその保障、また家庭でできる対策についてご紹介します。

2022/11/18
更新⽇︓2025/3/17( 最新情報に基づき記事の内容を一部更新しました)保険料控除とは、対象となる契約の掛金(保険料)を支払った場合に、所得税と住民税の負担が軽減される制度のことです。保険料控除制度には地震保険料控除制度と生命保険料控除制度の2種類があります。今回は、地震保険料控除制度の仕組みや、控除額の計算方法などを説明します。

2022/11/9
近年、台風や降雪などによるさまざまな自然災害が発生しています。これらの自然災害によって物が倒れて建物に被害が出たり、窓ガラスが割れて雨風が吹き込んだことで家財に被害が出ることもあります。そんなとき、賃貸住宅であれば誰がその修繕費用を負担するのでしょうか?この記事では、賃貸住宅で必要な保障と、どんなケースで保障されるのかについて解説します。

2022/6/29
更新⽇︓2024/05/9( 最新情報に基づき記事の内容を一部更新しました)近年、局地的豪雨(ゲリラ豪雨)や集中豪雨による土砂災害が多く発生しています。今回は、これからの台風シーズンに備えて、自然災害の危険性と、住まいの保障の重要性についてお伝えします。

2022/6/29
更新⽇︓2022/9/22( 最新情報に基づき記事の内容を一部更新しました)近年、6月にも関わらず沖縄地方に台風が接近したり、梅雨前線が停滞し新幹線の一部区間が運休になるなど、すでに大雨による影響がでています。

2021/12/23
コロナ禍の影響で、私たちの生活スタイルは大きく変化しました。中でも、在宅の機会が増えたことで、現在のお住まいの環境を変えようとする方が増えたのか、住宅購入や住まいの保障の見直しが注目されています。そこで今回は、当記事を監修いただいている「FPユニオンLabo」のファイナンシャルプランナーさんに、「住宅購入時の個別相談でよく聞かれる火災保障に関する疑問」を厳選いただきました。その疑問に答えつつ、こくみん共済 coop の住まいの保障である「住まいる共済」について紹介します。

2021/8/16
環境意識の高まりや光熱費の負担軽減などから、さまざまな工夫した暮らしを実践している方や省エネルギータイプの住宅やエコ設備を検討する方・選ぶ方は多いのではないでしょうか。総務省統計局によると、東日本大震災以降、省エネルギー設備等に対する注目の高まりや技術の発展、補助金制度の整備によって、特に太陽光を利用した発電機器を設置している住宅が増加したといわれています。

2021/3/26
更新⽇︓2025/6/26( 最新情報に基づき記事の内容を一部更新しました)大きな災害が起きたとき、国や自治体からの保障はどのくらいかご存知ですか?防災グッズは日頃から備えていても、住まいを守る保障についてはよく確認していないという方も多いのではないでしょうか?近年の地震、自然災害を取り巻く状況をふまえながら、自分が住んでいる家を守る住まいの保障について考えてみましょう。

2020/2/3
更新⽇︓2024/04/02( 最新情報に基づき記事の内容を一部更新しました)春は、卒業や入学など節目の季節であると同時に、引越しシーズンでもあります。引越しに伴っていろいろな手続きをすることになりますが、火災保障の手続きもその一つです。今回は、賃貸に引越す方が、火災保障について知っておきたいポイントを紹介します。

2017/12/26
火災保障は自宅が損害にあった場合に備えて加入するのが一般的ですが、自宅の火災が原因で近隣に損害を与えた場合の賠償責任について考慮されていないことも多いため、是非確認しておきましょう。

2017/5/31
更新⽇:2024/11/18( 最新情報に基づき記事の内容を一部更新しました)35,222件。これは令和3年1月~12月の総出火件数です(※出典:総務省消防庁 令和3年(1月~12月)における火災の状況)。おおよそ1日あたり96件、15分ごとに1件の火災が発生したことになります。火事の恐いところは、自分は気を付けていても放火やもらい火などで被害を受ける可能性があることです。特に日本は家屋が密集している場所が多いため、火事が起きると隣近所まで被害が及ぶことも少なくありません。
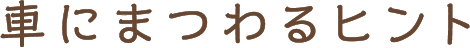
自動車はもちろん自転車も!
運転する人はおさえておきたい情報。
車にまつわる保障の疑問にお答えします。

2022/9/1
更新⽇︓2025/2/28( 最新情報に基づき記事の内容を一部更新しました)子どもが運転免許を取得して、自家用車(親の所有する車)を運転する場合には、自動車保険・共済の補償内容を変更しないと、万一の事故時にきちんと補償を受けられない可能性があるのをご存知でしょうか?今回は、子どもが運転免許を取得した際の車の補償について、確認すべきポイントや、こくみん共済 coop の「マイカー共済」の「子供特約」について、ある家族を例に紹介します。

2022/8/19
更新⽇︓2023/09/26( 最新情報に基づき記事の内容を一部更新しました)コロナ禍で、密を避けながら移動できる手段として「二輪車」需要が高まっているのをご存知でしょうか。通勤手段を公共交通機関からバイクに変えたいという人や、ツーリングなど屋外でレジャーを楽しみたいという人が増えています。しかし、一方で、任意保障への加入率は低いようです。バイクに乗り始めたけど任意保障の内容はよくわからない、入った方がいいの?と疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。今回は任意保障の必要性と、もしもに備えるこくみん共済 coop のバイク・原付の保障をご紹介します。

2022/6/17
更新⽇︓2025/3/27( 最新情報に基づき記事の内容を一部更新しました)2022年6月に関東地方で深刻な被害をもたらしたひょう被害。当会にも6月7日時点で3000件を超える被災連絡をいただいております。 今回は、お申し出の多い被害の内容を紹介しつつ、そのようなひょう被害への補償内容や、対策をご紹介します。

2022/3/31
後方や左右から車間距離を極端に詰めたり、幅寄せをしたり、前方を走っている車が急ブレーキをかけるなどといった「あおり運転」。こうした危険な運転は大きな社会的問題として認知されてきています。今回は、「あおり運転」に備える補償についてお伝えいたします。

2021/11/19
更新日:2025/9/11( 最新情報に基づき記事の内容を一部更新しました)自動車事故が起こると、当事者は、どちらの交通違反なのか、また不注意の責任はどちらにどの程度あるのかが、争点となります。この責任の割合のことを、「過失割合」といいます。今回は、自分に過失のない、つまり、過失割合が100:0である「もらい事故」の注意点と備えについてご紹介します。

2021/9/21
更新⽇︓2023/12/28( 最新情報に基づき記事の内容を一部更新しました)自動車を持っているみなさん、自動車運転の事故にしっかりと備えていますか?事故を起こさないために安全運転を心がけるのはもちろんですが、対人・対物補償以外に自分自身や搭乗者のための補償にも気を配りたいものです。ところで、「人身傷害補償」と「搭乗者傷害特約」との違いはご存じでしょうか?

2020/11/30
更新⽇︓2024/9/18( 最新情報に基づき記事の内容を一部更新しました)近年増加傾向にある自転車事故。ニュースなどで耳にする機会が増えた方も多いのではないでしょうか。今回は、自転車事故に対する備えという視点から、保障を選ぶ際のポイントやメリットをお伝えします。

2020/4/1
更新⽇︓2025/2/28( 最新情報に基づき記事の内容を一部更新しました)契約者の事故の有無に応じて、掛金(保険料)を割り引いたり、割り増したりするのが自動車保険(共済)(以下、自動車補償とします)の等級制度です。今回は、マイカー共済を例にしながら、等級制度を説明します。

2019/11/1
自動車の補償には、必ず加入しなければいけない「自賠責保険・共済」と、任意で加入する「自動車保険・共済」があります。この2つにはどのような違いがあるのでしょうか?

2017/5/31
更新⽇︓2023/10/4( 最新情報に基づき記事の内容を一部更新しました)「あっ!車にキズが…!いつの間に…!?」「停めていた車がない…」もし愛車がいたずらや盗難に遭ってしまったら悲しい思いはもちろんのこと、日常生活に支障をきたしたり、ローンの支払いだけが残ってしまったりといったことが考えられます。被害に遭いやすいのは、自宅の駐車場だけではありません。契約駐車場やコインパーキング、不特定多数が出入りするショッピングモールといった、所有者が誰か分かりにくい場所が狙われやすいといわれています。一財産である車を傷つけられたり、盗まれたりして、悲しい想いをしないように、しっかり対策をしておきたいですね。

2017/5/31
家族構成によっては複数台の車を所有している家庭も珍しくありません。2台目以降の車の補償の契約について「車を購入するときに勧められるまま加入した」という人も多いようですが、別々に契約することにより基本の補償内容や特約などが重複してしまっていて、必要のない補償にまで掛金を支払っているケースがあります。その掛金、もしかしたら「もったいない」かもしれません。
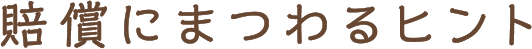
盲点になりがちな加害者になるリスク、
どんな「まさか」に備えるべき?
賠償にまつわる保障の疑問にお答えします。

2017/5/31
2024/07/23(記事内の表記を一部更新いたしました。)他人にけがをさせたり、他人の物を壊してしまったときには、法律上の損害賠償責任が生じる場合があります。例えば、スマホを見ながら歩いていたところ、前を歩いていた人とぶつかり、相手が転んでけがをしてしまった場合などです。歩きスマホによって人とぶつかってしまうことは、身近に起こりそうなことですよね。法律上の損害賠償責任が生じるリスクは、意外と身の回りに多く存在しています。損害賠償責任を負ったときに、頼りになるのが「賠償責任保障」ですが、じつは、「賠償責任保障」は、すでに家族の誰かが契約していれば、「ひとつの契約で家族全員を保障」できる場合がありますので、保障範囲をしっかり確認しておくと安心です。

2017/5/17
2023/10/24(記事内の表記を一部更新いたしました。)例えば、友人や知り合いの家に遊びに行ったとき、我が子がはしゃいでいるのを見て「何かトラブルを起こさないだろうか……」とドキドキした経験はありませんか?他人の物を壊したり、けがをさせたりすると、損害賠償請求が発生する可能性があります。実際に弁償(損害賠償)しなくてはならない状況になったとき、高額な賠償であった場合、どのように対処したらよいのでしょうか。通常、子どもが起こしてしまった事故は親の責任となり、親に損害賠償請求されます。子どもがいらっしゃる方は自分の家族のためにも、そして相手のためにも、個人賠償保障を用意しておくと安心です。