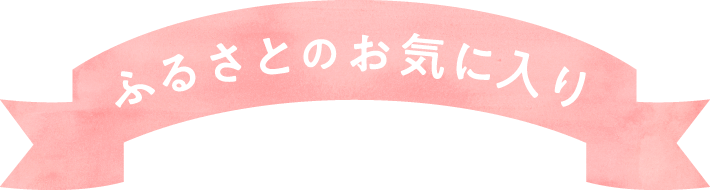- こくみん共済 coop の公式ホームページ
- あんしんのタネ
誰しも生まれた地、育った地があります。ずっとその地で過ごす人、進学や就職を機に離れる人、転々とする人。
縁ある土地とのつき合い方は人それぞれです。「第二のふるさと」「心のふるさと」という言葉があるように、「ふるさと」は、生まれ育った地とも限らず、もしかすると、物理的な土地とすら結びつかない、その人にとって大切ななにかがある場所とも定義できるかもしれません。
あなたにとって「ふるさと」は、どんなものでしょう。
第15回長南光さん
山形県鶴岡市生まれ、鶴岡市育ち、鶴岡市在住

長南光(ちょうなん・みつ)
知憩軒 女将
1949年山形県鶴岡市生まれ。農家の末っ子として鶴岡で育つ。1998年に、自宅敷地内の元堆肥舎に手を入れ、二組のみ宿泊可能な農家民宿「知憩軒(ちけいけん)」を開業。知憩軒の名は「軒下で憩い、知識を得合う場所」という思いが込められており、田舎の食と暮らしを伝えている。その後レストランとしても営業を開始。古民家で供される、地元の食材で丁寧に手作りされる料理と、あたたかな人柄に惹かれ、国内のみならず海外からも訪れる人が絶えない。
末っ子にして、農家の後継に

農家の3人きょうだいの末っ子で、上に兄と姉がいました。私のころは、長男長女以外は口減らしで家を出るのが普通でしたから、私も中学を出たら叔父を頼って東京に行って、働くつもりでした。同級生のうち、進学する人、働く人は半々くらいでしたね。集団就職の時代です。家を継ぐはずだった兄が、継がないで家を出ると言い出したもので大騒動でした。姉は18歳でお嫁に行ってしまってたから、私が継ぐことになりました。兄にはやりたいことがあったんですね。あの時代ですから、そんなことは許されませんでした。厳しい両親でしたし、もう、勘当ですよ。この家には帰って来れなくなりました。
私は、20歳前くらいに小田原の紡績工場に出稼ぎに行った以外、地元を出ることもなく、兼業農家として働きました。21歳でお婿さんに来てもらい、息子と娘が生まれます。23歳のときに母が病気になり介護が始まって、そのあと父も倒れて。畑のほかに別の仕事を持ちながらの介護でしたから、息子は小学校3、4年のときから夕食当番でした。息子としても、自分でつくらないと食べられませんでしたからね。母親の私がそんなふうだったので、うちの子はふたりとも、家のことを早くからできるようになりました。娘も隣の酒田市で、レストランを営んでいるんですよ。
ふるさとを思う側ではなく、守る側

小規模農家、いわゆる小作農家で貧しかったんですよ。病院代も払わないとならないし、家で介護しながらできる仕事をと、なんでもしました。地元の印刷屋さんの請け負いを6年ほどした後、縁あって始めた織物の仕事はもう30年になります。農家の人を中心に地元の女性を集めて、京都の西陣織で知られる、つづれ織りの帯を織りました。高い技術を必要とする絹の織物です。みんなで一生懸命覚えて。私もずいぶん、人に教えました。それぞれが一人前の織り子になっていったんですよ。しばらくして民宿やレストランをやるようになったのも、ここでできることを考えてのことです。私みたいに頭のよくないのには、思いつける仕事がそれくらいだったから(笑)。
ふるさとって、「遠きにありて思ふ」ものでしょ。生まれ育ったのとは別のどこかに行って初めて意識するものじゃないかと思うんです。私はずっとここだから、ふるさとって感じはしないです。私には、ふるさとはないのかなって。だけどたまたま民宿やってたら、ここを「ふるさとみたい」と思ってくれる人が出てきたんですよね。そう言って、何度も来てくれる人もいます。だから、守らないとって、思うようになりました。私は、ふるさとを思う側じゃなくて守る側なんでしょうね。私自身、古いものが好きなんです。新しい技術はよくわかりません。新しいものに囲まれて生活している人にとっては、それがほっとするみたいですよ。
地方ならではの、最高に豊かな暮らしを

ここが、昔の日本を感じられる場所として、心のふるさとみたいになっていければいいなぁって、いまは思ってます。そのためにもね、お金がないからこそ知恵を出しながら、お金持ちにはできない生き方をしたいんです。なれるなら、お金持ちではなく、人から大事にされる人。豊かな食事、豊かな文化で、また来たい空間をつくって待ってたいです。
ふるさとが、生まれたところでなくたっていいじゃないですか。自分の中にあればいい。東北は、日本人のふるさとにふさわしいと思うんですよね。私たちにとっての豊かなふるさとを守ることが、都会の人が深呼吸できるふるさとをつくることにもなるのかなと。誰かがしないといけないことなら、いつまでできるかわからないけど、頑張ろうと思います。楽しくないと人が寄ってこないでしょ。だから、地方ならではの、最高に豊かな暮らしを私もしつつ、ここでしあわせに人生を送る人を増やしたいですね。
私はどんなものもできるだけこの地域から買います。大きなスーパーよりいくらか高くても、日用品は地域の商店から、電化製品は地域の電器屋さんから。電器屋さんって技術屋さんですよね。買った家電になにかあったら飛んできて直してくれる。買うときに1万円高かったとしても、だからここで買うんです。人に頼って、お互い様で生きてるのだから、1万円より、その店の人の笑顔のほうを大事にしないと。
「命の裏側」を大事にしないといけない

うちは全部、家庭料理を出してます。ずっと自分も食べてきた味です。このあたりは、おかあさんの味じゃなくておばあちゃんの味なんですね。働き盛りのお母さんは、忙しくて子どもの世話ができなくて、年とって働けなくなったおばあちゃんが子どもに食べさせるから。私のも、おばあちゃんから受け継いだ味です。教わったことはないけど、舌で覚えた味。生まれたばかりの赤ちゃんが、教わらずしておっぱい探すの見ればわかるように、食べることは生きることですよね。
東京って、申し訳ないんですけど、私にはもう、日本じゃない気がします。おえらい先生たちは、自分たちが日本をつくってるつもりでいるけど、地方がつくってるんです。地方は本当は、東京がなくたって生きていけるんですよ。いざとなったとき生き延びられるのは百姓ですからね。東京は地方がなくなったら生きていけませんよね。一次産業がない。食べるものがないもの。お金は食べられないでしょ。誰かが汗かいて支えてる、「命の裏側」を大事にしないといけないって、いつも言ってます。みんなの命を支える人が一番貧しくて、8時間労働では食べていけない。私も貧しかったから、困った人の気持ちがわかりますしね、ふるさとを守る、命を守る人たちの、暮らしが豊かになるように頑張りたいです。えらい人をあてにしないで、楽しく生きていけるように。
鶴岡市編
by長南光さん


-
不便
庄内(地方)には新幹線がないの。置き去りだという人もいるけれど、それがいいところだと思います。便が悪くて日帰りできないから滞在するでしょ。そうやって、滞在しないと見えないものを見て帰ってもらうんです。なにかというと、人情みたいなものですよね。そういうものが、いまの人には必要なんだと思うんです。
編集後記
とにかくお料理がおいしい。本当においしいのです。地域の在来種の野菜でこしらえられたおかずとか、郷土の保存食であるとか、長南さんは「家庭料理」とおっしゃいますが、私たちの知るそれより、はるかに完成されたなにか、という印象です。それでいて、いわゆるお店の味とも異なります。喜んでいるのは味覚だけではない感じでもあります。沁みるように、おいしかったです。食事をいただく空間も、器も、長南さんご自身の佇まいも、言葉もすべて、そんなお料理になるべくしてなった理由を見るかのように、美しくつながっていました。
(取材・文:小林奈穂子)
お問い合わせ[お客様サービスセンター]


- ※電話番号のお掛け間違いにご注意ください。
- ※自動音声でご案内後、担当者におつなぎします。
- ※休み明けは電話が混み合うことがございます。ご迷惑をおかけしますが、ご了承ください。