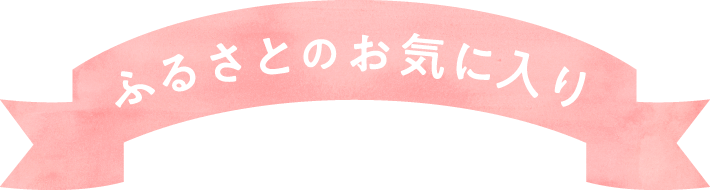- こくみん共済 coop の公式ホームページ
- あんしんのタネ
誰しも生まれた地、育った地があります。ずっとその地で過ごす人、進学や就職を機に離れる人、転々とする人。
縁ある土地とのつき合い方は人それぞれです。「第二のふるさと」「心のふるさと」という言葉があるように、「ふるさと」は、生まれ育った地とも限らず、もしかすると、物理的な土地とすら結びつかない、その人にとって大切ななにかがある場所とも定義できるかもしれません。
あなたにとって「ふるさと」は、どんなものでしょう。
第14回和田富士子さん
東京都品川区生まれ、品川区育ち→
アメリカ・ニューヨーク州など→品川区→
神奈川県横須賀市、鎌倉市→ハワイ→
神奈川県藤沢市→品川区在住
東京都品川区生まれ、品川区育ち→アメリカ・ニューヨーク州など→品川区→神奈川県横須賀市、鎌倉市→ハワイ→神奈川県藤沢市→品川区在住

和田富士子(わだ・ふじこ)
地元びいき 代表
1969年東京都生まれ。品川区の、人づきあいがしっかり残る地域で生まれ育ち、外の世界を見てみたいと海外を目指した時期を経て、地元に戻る。都会と地方をつなぐことをしたいという思いから、2013年、地元に根ざしたひと・活動・産業の発掘ポータルサイト『地元びいき』を立ち上げる。旧東海道品川宿周辺まちづくり協議会で地域活動の広報を担当するかたわら、品川区認定農家を目指して屋上の緑化、野菜の栽培を行っている。趣味は波乗り。
地元びいき地元の人づき合いの濃さから、離れたかった若き日

東京で生まれ育ったゆえでしょうかね、持ってる“ふるさと”という感覚は、もともと薄いほうだと思います。“ふるさと”って言葉もいまひとつピンとこないし、なんなのか、いまもよくわかりかねる感じ。ずっと、地方出身のみんなには帰るところがあるのに、自分にはないような気はしてました。
母は東京の人です。疎開で秋田に行って、戦後、焼け跡の東京に戻って来たんですね。そこで職を求めて上京してきた父と知り合った。父は徳島の田舎の次男坊です。私は遅くにできたひとりっ子で、大事に籠の中で育てられたようなところがありました。海外志向が強くなったのは、その反動かもしれません。
品川のこのあたりは地元意識が強いんですよ。東京人というより品川人というか、品川宿※の人間という気持ちがしっかりある。人づき合いもしっかりある。私も中学生くらいまではそれで楽しかったのですが、高校生にもなると、通学路で必ず誰かに声をかけられるようなことが嫌で、寄りつかなくなりました。いまはよくぞ残ってくれたと思うこの地域のコミュニティが、若き日の私には気づまりだったんですね。
※江戸時代に整備された五街道のひとつ、東海道五十七次(「東海道五十三次」が広く知られているが、実際には五十七次であったと考えられており、品川宿ではそちらを採用している)の代表的な宿場として栄えた。海と山の景色を背景に、江戸の玄関口として、ひと、もの、情報が行き交う賑わいのある宿場町を形成。多くの歴史上の人物が足跡を残している。
海外志向が強く、アメリカを目指した

恥ずかしながら(笑)、若いころの夢は国際弁護士でした。人種問題に興味を持って。大学は法学部の新聞学科に進みました。世の中の不平等を表に出したいとの思いで、弁護士やジャーナリストをイメージしたんですね。もっとも、まだ子どもでしたから、当時の知識ではそれくらいしか思い浮かばなかったというのが実際のところです。高校卒業後はアメリカに語学留学しました。ほぼ三ヶ月単位で、なんとなく海沿いの町を転々としました。1年くらいでバイトで貯めたお金が尽きて帰国します。当時は特に、自由の象徴というアメリカ像に憧れたんでしょうね、なんとかアメリカで働けないかと思ってました。
帰国後、残業、徹夜当たり前、という東京の会社で何年か働いて、スイッチの切り替えが欲しくなりました。職場も住まいも都会だと気分的にも疲れちゃうので、通勤圏で探した神奈川県の三浦海岸に暮らし始めました。品川と行ったり来たりの、いまでいう二拠点居住。サーフィンも始めて、そんな生活を5〜6年してました。三浦海岸に着いて電車のドアが開いたら空気が違うんですよ。あの感じ、好きでしたね。アメリカにはその間も、仕事でお世話になった知人を頼って、ニューヨークに何度か通ってました。アメリカで仕事をする希望は持ち続けてましたから。その後、縁あってハワイに2年弱滞在しました。趣味がサーフィンということもあって、ハワイはいまも大好きです。あのままいられるなら、そうしたかったかな。
品川宿のアイデンティティ

日本では、ジャーナリズムから転じた流れで、一貫して編集系の仕事をしていました。雑誌のときもありましたし、ハワイから帰って来たころはネットが一気に普及してきていたので、大手IT系企業でサイトの編集関連を。その経験を活かして、都会と地方をつなぐなにかになりたいと、『地元びいき』というサイトを立ち上げました。年を重ねるうちに、徐々に、ローカルとか、自分の足元にも目がいくようになっていたんですね。そうこうするうち、いまもお世話になっている、「旧東海道品川宿周辺まちづくり協議会」を人づてに知り、お手伝いするようになりました。住民としてはブランクがあった私ですが、ここで生まれ育ったのだからと、みなさんがすぐに受け入れてくれたんです。
よく「三代続くと“江戸っ子”」という言い方がされますよね。品川宿には、四代、五代の人たちがいますが、自分を江戸っ子だとは思っていないんですよ。宿場だから江戸じゃなく、江戸の外なんだと。江戸時代、江戸から数えて一つ目のこの宿場町には、近すぎて泊まる人はほとんどいなかったそうです。だから、泊まるより遊ぶところというのでしょうか、歓楽街として栄えて、芸事、食に長けた人が多かったらしいです。江戸から来た人はここで禊(みそぎ)を落として外に行く、江戸に入る人は、下駄の鼻緒をすげ替えるとか、ここで身を整えて行った。そんな中継地点だったんですね。代々地元に暮らす人には、宿場の人間だという気持ちに加えて、宿場の中でもほかと違うというアイデンティティが染みついていると思います。
地元で踏ん張る“土”の人がいてくれたから

外からの人が行き交うまちだったからこその気風は、いまとなっては私の性に合ってたみたいです。それでいて、地元の人たち同士の結びつきは、いまもしっかりしてるんですよ。上の世代の人たちを見ていると、お祭りのときにはなんというか、血汐らしきものを感じますよね(笑)。地域のつながりの中心に神社仏閣があった時代、そこに根ざしたお祭りだったわけで、そのせいか、お祭りへの向き合い方が違います。そんな姿に触れると、自分なんかここでは、埃だか塵くらいだなって感じますよ。通り過ぎる“風”ではないけど、このまちをつくる“土”でもない。その中間くらいなのかなって。四代、五代と地元を守ってきた人たちが、ここの“土”なんですよね。土の人たちが踏ん張ってくれたから、今日や明日にはできないまちの個性がある。地元のために汗をかいてきた人のおかげなんです。
品川に限らず、「ここだから汗をかける」「地元のためだから」と思える、土の人のいる、全国の“地元”を応援したいですよね。私自身、いつでも自分の地元を出ていける思いはいまもありつつ、こうしてフワフワしていられるのも、帰るところがあるからだと、いまはわかっていますから。
品川宿編
by和田富士子さん


-
おせっかい
これがないとなにも始まらない(笑)。人のつながりもまちづくりも、おせっかいから始まってます。おせっかいなんてなくなったと言われる世の中で、ここには売るほどあります。私も昔はこれが嫌いだったはずなのに、いつの間にか自分がやってる(笑)。やっぱりDNAなのでしょうかね。いまでは、おせっかいおばさんになるのが夢です。
編集後記
意外とお聞きする機会の少ない、東京ローカルのお話。品川をそんなふうな目で見たことも和田さんにお会いするまでなかったので、江戸時代の様子を思い浮かべながら、新鮮な気持ちで聞き入りました。新幹線が停まり(ただし品川駅が所在するのは品川区ではなく港区!)、高層ビルやホテルが立ち並び、湾岸にタワーマンションを有する品川の、別の豊かさを知って感心。ちなみにそれらは、品川宿の人にとっての品川にあらず、だそうです(笑)。和田さんのお話を聞く限り、地域の結びつきの強さは、ひょっとすると地方の小さなまち以上ですね。
(取材・文:小林奈穂子)
お問い合わせ[お客様サービスセンター]


- ※電話番号のお掛け間違いにご注意ください。
- ※自動音声でご案内後、担当者におつなぎします。
- ※休み明けは電話が混み合うことがございます。ご迷惑をおかけしますが、ご了承ください。