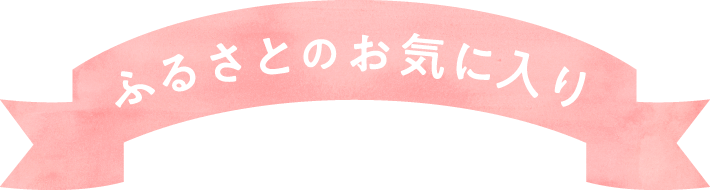- こくみん共済 coop の公式ホームページ
- あんしんのタネ
誰しも生まれた地、育った地があります。ずっとその地で過ごす人、進学や就職を機に離れる人、転々とする人。
縁ある土地とのつき合い方は人それぞれです。「第二のふるさと」「心のふるさと」という言葉があるように、「ふるさと」は、生まれ育った地とも限らず、もしかすると、物理的な土地とすら結びつかない、その人にとって大切ななにかがある場所とも定義できるかもしれません。
あなたにとって「ふるさと」は、どんなものでしょう。
第3回市来広一郎さん
静岡県熱海市生まれ熱海市育ち→神奈川県横浜市→
熱海市在住
静岡県熱海市生まれ熱海市育ち→神奈川県横浜市→熱海市在住

市来広一郎(いちき・こういちろう)
株式会社machimori、NPO法人atamista 代表
1979年静岡県生まれ。大学のとき、生まれ育った熱海市を離れ家族で横浜に。東京都立大学大学院理学研究科(物理学)修了後、海外を旅したのち、ビジネスコンサルティング会社に勤務。2007年に熱海にUターンし、地域づくりに取り組み始める。地元自治体と連携しながら、遊休農地の再生や、地域資源を活用した体験交流ツアー、空き店舗の再活用などを手がけ、奇跡とも言われる熱海再生の立役者として注目されるように。地域づくり関連の複数の社団法人の理事も務める。
趣味は喫茶店で過ごすこと。著書に「熱海の奇跡〜いかにして活気を取り戻したのか〜」(東洋経済新報社)
いつも近くにあった熱海は、「ふるさと」という実感がない

生まれ育った熱海にUターンして10年以上経ちました。ここがふるさとであることは間違いないのでしょうけれど、自分の感覚ではどうもピンとこないですね(笑)。新幹線で40分、東京に近いじゃないですか。実際、高校生くらいから、東京まで気軽に買い物しに出かけてたので、東京に対する憧れもありませんでした。ふるさとって、遠く離れた都会に出て、しみじみ思いを馳せるようなイメージがありませんか?僕は熱海のあとに住んだのも、そう離れていない横浜だし、都会で働いている間もたびたび熱海に来てたし、そんな感慨もなくって。
両親は住み込みで銀行の保養所の管理人をしてました。僕は、保養所を実家として育ったんです。20歳のとき、熱海にあったその保養所がなくなって、一家で横浜に越すことになりました。途中、東京の八王子でした1年間のひとり暮らしと、仕事で平日は福岡のホテル住まいだった二拠点生活の9ヶ月間を除くと、それから10年近く、横浜の住宅街に住んでました。横浜では、商店街に行きつけの飲み屋をつくって通ってました。週末にはライブがあって、プロ志望の若いミュージシャンたちが集うんです。その感じが好きだったんですよね。僕が、家でも会社でもない、いまよく言われるようになった第3の居場所、“サード・プレイス”を初めて持ったのがあのころです。この経験は、その後、いまに続くまで影響していると思います。
閉鎖的な部分は昔から嫌いで、壊したかった

熱海の思い出は、やっぱり多いですよ。町に海があるって大きいですね。ぼーっと見ているだけでも一日過ごせますから。あと、実家。実家が保養所だなんて人はなかなかいないでしょう。当然、敷地も部屋も広いわけで、同級生には完全に金持ちだと思われてました(笑)。敷地内のちょっとした林みたいなところで鬼ごっこしたり、襖で仕切られた10畳ぐらいある部屋をふたつつなげて広間をつくり、そこでレゴで遊んだり。団体のお客さんの宴会に混じって遊んでもらうことも、麻雀を教わることもありました。そして、これは保養所じゃなくても熱海では当たり前ですが、お風呂はもちろん温泉です。むしろそういうものだと思ってました。どれもこれも贅沢ですよね。
でも、だから熱海が大好きだったかというと、そんなこともないんです。やっぱり狭いんで、たまたま女の子と一緒に下校すると、家に着いたらもう「あんたあの子とつき合ってるの?」とか言われるんですよ(笑)。いつも見られてるし、すぐにうわさされる。それだけでなく、地域のコミュニティの、独特の閉鎖性は息苦しくて大嫌いでした。だから、ここに、自分が担い手の立場で戻って来たとき、地域の、物心共に閉鎖的な部分は壊したかった。カフェとかコワーキングスペース※とか、まずはハードから、オープンに、オープンにとつくるようにしました。移住者が多く集まっても、もともと地元の人と外から来た人とが分断してしまうのは、どこの町にも見られることなんです。とにかくそうしたくなくて、自由に、自然に、行き来が生まれる場所をつくりたかったんです。
※ 主にIT系で起業した人やフリーランスが、ひとつのオフィススペースを複数人で共有しながら仕事をする場合の、そのスペース。2010年以降都市部を中心に増えた。一般に、管理・運営する企業などに使用料を支払い利用する。
寂れてゆく町。でも、「可能性、あるじゃないかと」

熱海にUターンしたのは、高校生くらいから寂れてゆく姿を見てきて、なんとかしたいという気持ちが募りに募ったからです。2005年くらいからでしょうか、ここには住まない人が所有するリゾートマンションが立ち並ぶようになり、同時に旅館が次々と廃業して、すごく複雑な気持ちになりました。大人になって東京や海外を見るうちに、熱海の良さにあらためて気づいたというのもあります。
印象に残ってお手本にしているのはクロアチアの世界遺産の街、ドブロブニクでしょうか。景色のきれいなリゾートなんですけれど、人の暮らしもあるんです。干した洗濯物も、サッカーをしている子どもたちも絵になって、地元の人は楽しそうで、こんなところに住めたらいいなと感じました。僕はヨーロッパの旧市街や、日本だと尾道のような、暮らしと共に脈々と続いてきた街が好きなんです。でもふと振り返ると、熱海もそうなんですよ。観光地であり、暮らしの場であり。昭和のままの喫茶店や飲み屋さんが何軒も残ってる。可能性、あるじゃないかと。
Uターンしてみると、自分と同じ、いまの30〜40代を中心として、この町が廃墟になる危機感の中で後を継いだ人たちが多かった。数字で見ると、熱海は2011年がどん底状態。危機感に比例して連体感も強かったので、まとまるときは早かったです。みんな「なんとかしないと」と、僕が目指した、ラフでフラットな都市型の関係性を持ったコミュニティの構想に真剣に耳を傾けてくれて、賛同してくれる人も多かった。ありがたかったです。「自分たちのまちづくり」への意識を共有し、協力し合うことができたんです。
熱海で得られている充足感を、広げてゆきたい

まだまだ課題も多いですよ。経営者として、スタッフにも、もっと経済的な余裕をつくりたいし、あと10年余りは、若い人たちに継いでもらえる地盤づくりのために走りたい。ただ、自分自身のことを言えば、すごく満たされてるんです。家族がいて、こころ許せる仲間がいて、コミュニティがあって。与えられたものではなく、自分たちでつくってきたと思える誇りや充足感がある。意味のある仕事をしながら、顔の見える売り買いで多くを成り立たせることもでき始めている。この町には自然も残ってるし、好きな喫茶店やバーもあるので、たまに日常から離れられる条件もそろってます。ほとんど理想的なんです。今後は、ほかの町とつながって、熱海に来てもらえる人を増やしながら、いま自分が感じているような充足感をほかの町にも広げてゆけたらと思っています。
そのうちほかにも拠点を持つかもしれません。いつか…と思う場所のひとつは、市来家のルーツがある鹿児島。市来という地名もあるし、市来さんもいっぱいいるんですよ。20歳くらいのときに思い立って訪ねたことがあります。小学生のころ、『まんがはじめて物語』という、歴史上の出来事の起源を教えてくれる子ども向けのテレビ番組に、なんと父方の祖先が登場しました。市来四郎という、日本で初めて写真を撮ったと言われている人です。撮影したのは、名君で知られる薩摩藩の島津斉彬!親戚に尋ねたらうちの祖先で間違いないそうで、びっくりしました。そんなこともあり鹿児島には思い入れがあります。僕にとってはむしろこっちのほうがふるさとっぽいかな。それでも本拠地は、この先もずっと熱海だろうと思いますね。ここは気をゆるめられる場所です。仕事で考え事をしていても、ふと見ると海があって、山もあって。海から日が昇ってくるのを見ると、「いい朝だなぁ」って、なにがあっても思えるんです。
熱海編
by市来広一郎さん


-
海
眺めていると、「熱海にいるな」と感じます。海からの日の出を初めて見たのは大学生くらいのころでした。そのあと、月が昇るのも見ました。どちらも感動しました。熱海の海はほかの海とは違う気がするんです。でも、なにが違うんだろ。
-
コンパクトな規模感
花火大会のフィナーレ、ナイアガラ花火のときには、街がキラキラ光るんです。それが大好きで、花火でなく街を見てます。見渡せる感じのコンパクトさが落ち着きます。歩いていると、知り合いにも会うけど、知り合いばかりではない。それがちょうどいいです。
編集後記
「与えられたものではなく、自分たちでつくってきたと思える誇りや充足感」。これはうらやましくもあり、身につまされもします。市来さんたちがつくっているのは、現在熱海に暮らす人、これから暮らす人にとっての、未来の「ふるさと」でもあるのでしょうね。さて、その市来さん、“熱海再生の立役者”との評判からは、前に前に出て行く人物像が想像されなくもないですが、「みんなが楽しそうにしているのを端っこから見てるのが好き」なのだそうです。何気に口にされたその言葉に、お人柄が表れているように感じました。
(取材・文:小林奈穂子)
お問い合わせ[お客様サービスセンター]


- ※電話番号のお掛け間違いにご注意ください。
- ※自動音声でご案内後、担当者におつなぎします。
- ※休み明けは電話が混み合うことがございます。ご迷惑をおかけしますが、ご了承ください。