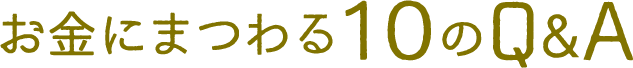- こくみん共済 coop の公式ホームページ
- あんしんのタネ
今月の「生きるヒント」
その人の価値観をはかるモノサシにされることも多い“お金”。人生に、深くかかわりがある割に、真正面から語られることが少ないのも“お金”です。
誰かのお金観の背景にある経験やエピソードは、いつか自分のそれと重なるかもしれないし、現在の向き合い方を考え直すきっかけになるかもしれません。専門家による経済の話でなく、人それぞれの、お金にまつわるストーリーをお届けします。
第
11
回
やりくりが得意だから、先の心配はしすぎない やりくりが得意だから、
先の心配はしすぎない

星野 友里さん
ほしの・ゆり
株式会社ミシマ社 編集者
1982年東京生まれ。大学卒業後、証券会社に就職。投資商品の管理・開発に関わった後、経営管理部門に異動。2010年に、東京自由が丘の古民家に本社を置く、小さな総合出版社・ミシマ社に転職。営業事務担当を経て、現在は主に編集を担当。最近担当した作品は、『等身の棋士』(北野新太著)、『似合わない服』(山口ミルコ著)、『おなみだぽいぽい』(後藤美月著)など。
都内にひとり暮らし。趣味は旅行で、昨年はフィンランドに。目下行ってみたいのはキューバ。
お金に関する原体験は、幼稚園のお買い物ごっこで

幼稚園のころ、園のお祭りのようなものがあって、お買い物ごっこ的イベントが催されました。おもちゃのお金と引き換えに、子どもの好きなコチャコチャした“商品”を自由に買えるのですが、選べなくて、ふわ〜っと舞い上がってしまった私は、結局どれも買いそびれてしまいました。ちゃんと使い切ったみんなと違い、手の中に残ったのは(おもちゃの)お金だけ。ところが、余っていた商品の中から、偶然、買おうかと最後まで迷っていた、キラキラしたスーパーボールをもらうことができたんです。「お金って、使わないと意味がなくなるんだ」「でも(お金を使わなくても)ラッキーで欲しいものが手に入ることもあるんだ」と、二つのことを同時に学んだ、思い返せばそれが私のお金にまつわる原体験です。お金というのは儚くて、お金だけが力を持っているわけではないと。もちろん当時は、きちんと具体的に解釈できるはずもありませんけれど、そのような感覚は残り続けた気がします。
三つ子の魂百までなのか、幼稚園のときからずっと、あまり熱くなにかを欲するようなこともなく、ここまできました。壮大な夢を見るタイプではありません。大きな家に住むことより、小さな家の中で家具の配置を工夫したり、たくさんでなくても好きなものに囲まれたりして、いかに心地よく暮らすかのほうに興味があります。食い詰めるような経験はないので、苦労を知らない証拠なのかもしれません。他人と比べることもせず、その点では、どちらかというとぼんやりとでもやれてこれたように思います。
適性が活きると思い証券会社に勤めるも・・・

大学卒業後は証券会社に就職しました。もともとやりくりが得意で、学生時代、親が老後のことを心配しているのを見て、代わりにいろいろ調べたり、計算したりしてあげたことがあったくらいです。自分でもお金を扱うのが嫌いではないと自覚していたことから、オンライン主体でおもしろそうだと感じた証券ベンチャーを就職先に選びました。ところが入社後、投資ツールの開発に携わったり、システムの人とやりとりする仕事を2年半やってみてわかったのは、同じお金を扱う仕事でも、私が得意だと感じていた、“やりくり”のようなものとそれらの仕事は、種類が違うということでした。私が面白さを感じるのは、手元で目に見えるお金を活かすことだったのです。お金を増やすあれこれには、どうしてもあまり興味を持てませんでした。
会社側も、そんな私の適性を見極めたのか、売り上げと予算の管理をする部署に異動になりました。証券会社でのトータル5年間のうち後半の2年半は、元来向いていた仕事をさせてもらったことになります。ただ、そのような管理の仕事は業種を問わず必要とされるはずで、せっかくなら、金融商品よりも興味が持てる商品を扱う会社でやりたいなと思うようになったとき、出会ったのがいまの会社です。経理を含む営業事務の募集があったので応募しました。本が好きだったんです。
10年後は、そのときの自分に託す

転職して収入は減りました。一般に給与水準が高い金融業界に対し、ミシマ社は小さな出版社ですから。だけど気になりませんでしたね。心配してくれる人もいましたが、自分で経営するとかフリーになるならいざ知らず、定収入があるという安心感は引き続き得られるわけで、それさえあれば、額はさほど重要ではありませんでした。やりくり好きとしては、限られた中でなんとかすることへの不安は少ないのです。実際に、要所要所、自分なりに思い切って使えるくらいの余裕はつくれてます。
最初のほうでも触れましたが、博打を打つようなタイプではないのが大きいですね。将来のことはわかりません。10年前、いまの自分はまったく想像できていませんでした。これからもそうだと思うんです。でも、そのときの自分がなんとかするだろうと託せばいい。10年後の自分がやりくりするだろうから、その自分に「よろしく」と任せて、あとは、細かく切り詰めるでなく、お金のだいたいの出入りと、どこを抑えるべきかだけ把握しておけば、それほど不安にはなりません。転職してから発覚した病気で、手術を受けたこともあるのですが、幸いにも思ったほどには持ち出しもなく、逆に、ある程度は社会的なシステムがケアしてくれるとわかりました。ですからいまのところ、将来に備えるということに、そこまでの重きは置いていませんね。
仕事においては、お金との向き合い方が違う

仕事においてのお金の向き合い方は、個人的なそれとは少し違います。10人ほどのミシマ社で、私も古株になってきました。営業事務で入社はしましたが、いまは編集者としての仕事がほとんどです。売り上げに対する責任は、若いころよりずっと感じるようになりました。会社に利益をもたらさなくてはならないし、著者さんの労力もわかっているし、そこのお金は、個人としてのお金よりもしっかり自覚的に、シビアに見なくてはならないという思いが増してきました。
一方、私たちの仕事は、「売らなきゃ売らなきゃ」では、やっぱりダメなのです。本当にいいと思うものがまずあって、それをよりたくさんの人に届けられるのが一番。その結果、会社が次にもっといい本をつくることができるのが理想です。稼ぐことが人間のパワーになることは間違いないですが、優先すべきを見失わずにいるためにも、お金だけを見て、何パーセント成長、などというのは違うと思っています。ミシマ社自体が、額面とは別の価値観を持つ会社で良かったです。為替や日経平均を気にする必要のない世界を、少なくとも私は居心地がよいと感じています。前職のような世界を否定はしませんけれど、私の場合は、自分の目に見えて、自分の手の届く範囲の中でやってゆくのが好きです。関わりたい世界の違いかな。
いまの仕事では、果たさなくてはならない責任のプレッシャー込みで、楽しみたいと思えます。著者さんとの打ち合わせの時間などは本当に楽しくて、お金を払ってでもその場にいたいと感じるときすらあります。そんな私がこんなことを言うと、恵まれているから言えると思う人もいるでしょうけれど、学生さんなんかと話しているとときどき、つらいことをしてお金をもらうというのが仕事の概念として初期設定になっているように感じることがあります。その、「お金と引き換えにしている」という考えには、素朴に異を唱えたいです。


-
- Q1.
- お金のことには詳しいほうだ。
-
- Q2.
- 「趣味は貯金」に共感する。
-
- Q3.
- 「趣味は投資」に共感する。
-
- Q4.
- 先のことはわからないからこそ「使う」。
-
- Q5.
- どんぶり勘定の人よりお金に細かい人のほうが信用できる。
-
- Q6.
- 100万円と10億円、もらえるなら10億円。
-
- Q7.
- お金の稼ぎ方と使い方、こだわるなら稼ぎ方。
-
- Q8.
- 「金は天下の回りもの」に賛同する。
-
- Q9.
- アリとキリギリスならアリタイプ。
-
- Q10.
- お金にまつわる経験から得た教訓や信条をお聞かせください。
ニュートラルな存在のはずのお金は、そこから引き出されてくる人間の感情やエネルギーの良し悪しに左右されますよね。仕事や健康など、いろんな不安要素がお金の不安に変換されてしまうこともあると思うんです。お金のせいにして、お金さえあれば解決できると考えてしまう。お金の果たす役割は確かにありますが、お金を介さなくても回ることもあります。お金の占めるウエイトを抑えて、人間関係などを動かして回したほうがうまくゆくケースは多いと思います。どんどん成長するわけではない時代を安らかに生きるためには、順番としてお金を先に持ってこないほうがいいのではないでしょうか。
編集後記
本文では触れていませんが、星野さんは、お金がモノとして好きなのだそうです。紙幣もコインも、モノとして魅力があると。ご自身が分析するに、同じ材質、形のものがきれいに揃う様(さま)に感じるものがあるのではないかということで、かつてのテレフォンカードも好きだったし、本も、どうやらその延長線上ではないかとおっしゃる。お金のお話をしてきて、その視点を持ったのは初めてでしたが、言われてみればなんとなくわかる気がしてきます。慣れきったものをそのように見るやわらかな感性、素敵です。
お問い合わせ[お客様サービスセンター]


- ※電話番号のお掛け間違いにご注意ください。
- ※自動音声でご案内後、担当者におつなぎします。
- ※休み明けは電話が混み合うことがございます。ご迷惑をおかけしますが、ご了承ください。