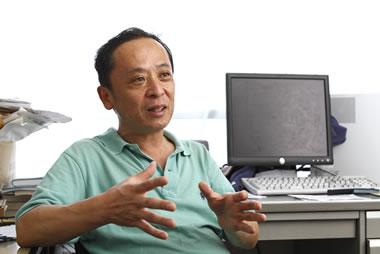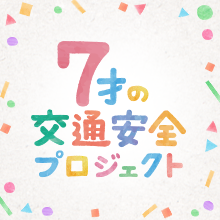- こくみん共済 coop の公式ホームページ
- あんしんのタネ

-
家族と食卓を囲みながら、ゆったりとした時間を過ごし地域のことにも思いをはせるーー。そんな、あたりまえの「豊かな暮らし」を求める人が増えています。「食の安全」「地産地消」「スローフード」などのキーワードがしばしばメディアを賑わすのも、そうした表れの1つ。このシリーズでは、「食」と「暮らし」を巡って議論されている、古くて新しい豊かさと幸福、持続可能なライフスタイルとは何か、を探っていきます。
第5回目は、ジャーナリストで出版社「コモンズ」代表の大江正章さんに「食」を通じたまちおこし・地域おこしの可能性についてうかがいました。
昔からあった「地産地消」や「旬産旬消」の考え方
大江さんはこれまで編集者・ジャーナリストとして長く有機農業を取材し、食や農を通じた地域活性化のあり方を追求して来られました。そのきっかけはなんだったのでしょうか?
![]() 1980年に大学を卒業し、ある出版社に就職しました。そこで、たまたま新しい農業に関する本を編集することになったのです。
1980年に大学を卒業し、ある出版社に就職しました。そこで、たまたま新しい農業に関する本を編集することになったのです。
当時、元・東京大学の先生たちを中心にある研究会が発足していまして、わたしが担当したのは、その研究会が作る本のお手伝いでした。入社してすぐの一年生がなぜ、そんな本の担当を命じられたのか。じつは、その経緯というのが少しおもしろい。というのも、研究会に集まっていた先生方が「これからの時代を担うのは第一次産業だ、なかでも有機農業が大事だ」という主張を展開しておられたんです。それを聞いて、その出版社の社長が驚いてしまいまして。時はバブル経済の少し前ですから、有機農業という言葉自体、まだ一般的ではありませんでしたし、「何それ? 勇気出してやる農業のこと?」なんて本気で聞かれるくらいでした。ですから、社長は当然のごとく「そんな本は売れるわけがない」と考え、新人のわたしに担当のお鉢が回ってきた、という訳です。
研究会に出席し、先生方の話を聞いているうちに、有機農業というのはわたしたち自身の食生活や健康を守るばかりか、環境や文明にとってもとても大切なものであることがわかりました。当時はわたし自身、漠然と「こんな経済成長一本槍の生活は長く続かないだろう」と感じていましたし、その頃は公害問題もまだ深刻だったし、また、環境問題の大切さが叫ばれ始めた時期でもありました。若かったわたしは、「この有機農業という考え方はおそらく社会のあり方を根本から変えていく手段になるだろう」と確信し、それに対する関心をどんどん深めていったわけです。
今シリーズのテーマ「人に優しい食のススメ スローフードという生き方」を聞いた時、率直にどう感じられましたか?
![]() 時代は変わったな、と。けれど、考えようによっては昔からある「あたりまえの価値観」に戻っただけ、とも言えます。
時代は変わったな、と。けれど、考えようによっては昔からある「あたりまえの価値観」に戻っただけ、とも言えます。
日本には昔から「身土不二(しんどふじ)」や「四里四方に病なし」という言葉がありました。身土不二とは、身体の健康と土とは切っても切り離せないという教えであり、四里四方に病なしは身近で採れたものを食べていれば病気になりにくい、という考え方を表します。今で言う、「地産地消」や「旬産旬消」という概念に近い考え方です。
こうした価値観が大きく崩れ始めたのは、1960年代の高度経済成長期以降のことです。1964年、東京オリンピックの開催を目指し、東京と地方を結ぶ新幹線や高速道路網などが次々と整備され始めると、それに伴って食の広域流通もスタートし、各地に巨大なスーパーマーケットが建つようにもなりました。同時に、道路や地下鉄工事のために地方から東京へ出稼ぎに出て行く人も多くなり、1970年代前半になると、たとえ農家の長男であっても家業を継がないケースが目立ってきます。その大きな理由のひとつは、農業だけではなかなか食べていけない時代になったからでした。
スーパーマーケットで売られている卵の価格を思い浮かべて下さい。今だとおそらく、10個128円くらいではないか、と思います、じつはこの価格、30年以上、ほとんど変化していません。お米に関して言うと、1980年前後、生産者の手取りは60キロあたり16,000円から17,000円もありました。ところが、現在は同じ60キロあたりでおよそ11,000円。つまり、経済成長過程でほかの物価はどんどん上がっても、農産物の価格だけは据え置きか、下がり続けてきたわけです。
そうした状況に伴い、人々の価値観も変化していきました。農林水産業は遅れた産業であるという意識が強まると、昔からあった「百姓」や「職人」といった言葉には少なからぬ侮蔑の意味が込められるようにもなっていきます。そうしたなか、若者の農業離れが起こっていくのも当然のことだったと思います。
年間8,000人以上のペースで増える農業への参入者
日本では今、その有機農業に興味を持つ若者たちが増えています。おそらく、2000年ぐらいから本格化した動きだと思いますが、大江さんはそれについてどのような社会的変化があった、とお考えですか?
![]() いくつかの要因が挙げられると思います。ひとつのきっかけは1992年、ブラジルのリオ・デ・ジャネイロで「環境と開発に関する国際連合会議」が開かれたことでした。これ以降、環境問題に関心を持つ若い人たちがぐっと増え、その延長線上で農業や食の安全・安心にも強い関心が向くようになってきたと思います。
いくつかの要因が挙げられると思います。ひとつのきっかけは1992年、ブラジルのリオ・デ・ジャネイロで「環境と開発に関する国際連合会議」が開かれたことでした。これ以降、環境問題に関心を持つ若い人たちがぐっと増え、その延長線上で農業や食の安全・安心にも強い関心が向くようになってきたと思います。
アレルギー・アトピー患者の激増も、こうした動きに拍車をかけました。ご存じのように、日本では現在、赤ちゃんの3人に1人はなんらかのアレルギー症状を持って生まれてきています。ですから、農薬や化学肥料、添加物を使わない、より自然な食べ物を求めるニーズが高くなるのも、当然だと思います。
三つめにはもちろん、バブルがはじけて仕事がなくなり、人々を惹きつけていた都会の魅力のひとつが消えてしまった、という要素もあるでしょう。結果として、都会暮らしに疲れた若者たちが地方へとIターン・Uターンしていった。
それから、4番目に重要だと思うのは、社会全体の価値観の変化です。生まれた時から不景気を生きている今の20代、30代にしてみれば、親世代を見ていてもちっとも幸せそうだとは感じられません。企業社会にからめとられた人生はつまらない、自分はもっと違う生き方がしたい、と考えるようになった若者たちが増えた結果、それまでの人口移動とは正反対である「都会から地方へ」という人の流れが生まれてきたように思います。
現在、新規就農者というのはどれくらい、増えているのでしょうか?
![]() 国が初めて非農家出身の新規就農者の統計を出したのは1985年ですが、当時、その数というのは年間66人しかいませんでした。それが2000年代半ばぐらいからは一貫して2000人前後で推移しています。その多くは有機農業をめざしているといえるでしょう。それ以外にも、農業法人に就職する非農家出身者は年間約6,000人から8,000人はいます。ですから両者を合わせると、毎年8,000人から1万人が新たに農業に参入していることになります。
国が初めて非農家出身の新規就農者の統計を出したのは1985年ですが、当時、その数というのは年間66人しかいませんでした。それが2000年代半ばぐらいからは一貫して2000人前後で推移しています。その多くは有機農業をめざしているといえるでしょう。それ以外にも、農業法人に就職する非農家出身者は年間約6,000人から8,000人はいます。ですから両者を合わせると、毎年8,000人から1万人が新たに農業に参入していることになります。
こうした動きには、2006年12月に有機農業推進基本法が制定されたことも影響しているでしょう。この法律によって、それまで「異端」とみなされていた有機農業や環境保全型農業がきちんと定義づけられ、社会に認知されるきっかけにもなりましたから、新規参入しやすくなったことは確かです。
複雑な「有機農産物」の定義
一方で、農産物全体における有機農産物の流通量というのは
まだまだ少ないという話も聞きます。
![]() たしかに、あまり多いとは言えない現状です。ただし、そこには「有機農産物とは何を指すか」という難しい問題が絡んできますので、いちがいには言えません。
たしかに、あまり多いとは言えない現状です。ただし、そこには「有機農産物とは何を指すか」という難しい問題が絡んできますので、いちがいには言えません。
先ほどの基本法制定に先立ち、国は1999年にJAS法を改正して有機農産物の第三者機関による認証制度を導入しました。仮に、その認証を受けた農産物だけを「有機農産物」と定義すれば、その割合は全体のたった0.18%しかありません。
ところが、スーパーなどの市場に出荷するのではなく、食べる人と顔の見える関係のなかで農産物をやりとりするだけならば認証を受ける必要はないため、農家のなかには面倒な手続きを嫌がって認証を受けたがらない人もたくさんいます。ですから、実際に生産されている有機農産物がはたしてどれくらいあるか、という厳密な統計はないに等しいのです。
私自身はおそらく農産物全体の1.5%くらいは有機で生産されているのではないか、と推測しています。また、これも非常にややこしいのですが、国は慣行農業と比べて農薬や化学肥料を半分以上削減して生産したものを「特別栽培農産物」と定義して、表示を認めています。それを含めると、おそらく全体の農産物の15%程度まで上がるでしょう。
農業に関しては、その担い手の高齢化も心配されています。
![]() 現在、農業の担い手は全体のおよそ60%を65歳以上が占めています。じつは、昨今非常に人気が高い直売所でやりとりされる農産物も、その多くは農薬や化学肥料を使っていません。これらは市場出荷されないため統計ではなかなか捕捉されませんが、作っているのはほとんど高齢者です。
現在、農業の担い手は全体のおよそ60%を65歳以上が占めています。じつは、昨今非常に人気が高い直売所でやりとりされる農産物も、その多くは農薬や化学肥料を使っていません。これらは市場出荷されないため統計ではなかなか捕捉されませんが、作っているのはほとんど高齢者です。
高齢化はたしかに不安要素ではありますが、個人的には、それは必ずしも悪いことばかりではない、と考えています。第一に、高齢化は日本社会全体の問題であり、農業だけの問題ではありません。だとすれば、高齢者が活き活きと元気に、生き甲斐を持って働ける職業のひとつとして農業を考えればいい。そうすれば、農業はこれからの未来を先取りする生き方のひとつにもなるはずです。
新規参入してくる若者にとっても、自分のおじいちゃん・おばあちゃん世代に農業や昔ながらの暮らし方を教わるのは悪くありません。じつは、漬物や味噌作りなどの伝統食に関しても、そのノウハウを持っているのは現在の70歳以上です。今の60代はちょうど近代農業を始めた世代ですから、20代、30代の若者たちとは価値観が微妙に合いません。70代以上の高齢者にしてみれば、息子・娘世代には振り向いてもらえなかった梅干しの作り方や味噌の作り方を孫世代にあたる若者たちが「すごい、すごい」と聞きにきてくれる。それは、とても嬉しいことだと思います。
「農」から「地場産業」へと広がる活性化の動き
日本各地では今、「食」を活かしたまちおこし・地域おこしが盛んです。
大江さんが今、特に注目されている地域はありますか?
![]() 埼玉県の小川町というところです。池袋から東上線で70分ぐらいのところにある、人口3万4,000人の小さな町です。農村地帯ではありますが、地場産業は和紙と建具であり、今も造り酒屋が三軒残るような商業の町です。かつては甲府と秩父を結ぶ秩父往還道の要所でもありまして、埼玉県内すべての市町村のなかで商業売上が5番目を誇ったこともあるそうです。
埼玉県の小川町というところです。池袋から東上線で70分ぐらいのところにある、人口3万4,000人の小さな町です。農村地帯ではありますが、地場産業は和紙と建具であり、今も造り酒屋が三軒残るような商業の町です。かつては甲府と秩父を結ぶ秩父往還道の要所でもありまして、埼玉県内すべての市町村のなかで商業売上が5番目を誇ったこともあるそうです。
ところが、その後、御多分に漏れず地場産業が衰退してしまい、町はすっかり元気をなくしていました。じつは、その町を活性化させたのが、「有機農業」であり「食」でした。
その中心人物となったのは地元で農業を営む金子義登さんという方で、彼は1970年に農業者大学校を卒業して有機農業を始めました。しばらくは試行錯誤が続きますが、1980年代半ばにはすでに農薬も化学肥料も使わないで慣行農業とほぼ遜色のない農作物を作り、それを会員の消費者に販売することで十分な収入も得るようになります。
そこで、彼は次に有機農業と地場産業とのつながりを作ろうと考えます。ちょうど、地元の造り酒屋さんにも「地元の無農薬の米でお酒を造りたい」という意向がありました。こうして、その造り酒屋では、酒米の一部を金子さんとその仲間が作る無農薬のお米に切りかえました。そして、88年からその米を使った「おがわの自然酒」という純米酒を売り始めると、これが徐々にヒット商品になったのです。
酒造りがうまく行くと、地元の製麺所からも声がかかり、無農薬うどんを作り始めます。それもうまくいくと、今度は隣町にあるお豆腐屋さんにも声をかけ、大豆を提供し、無農薬の豆腐が販売されました。
それまで、そのお豆腐屋さんはスーパーに叩かれながら海外産の大豆で安い豆腐を作っていました。しかし、無農薬の、しかも地元でとれた大豆に切りかえてから、スーパーに卸さなくても十分に商売が成り立つようになりました。どういうことかと言えば、その豆腐のおいしさと原料の安全性が高く評価されて、消費者のほうから直接、お豆腐屋さんに買いに来る。そうこうしているうちに、最初は今のご主人とそのお父さんの二人だけでやっていた店が、とうとう従業員35人の会社になった。
今では、週末ともなればそのお豆腐屋さんには一日平均して700人から800人のお客さんが詰めかけ、その平均購買単価は1,400円から1,500円にも上っています。どうしてこのようなことが可能になったのかと言えば、それはもっぱらまっとうな原料を使っておいしいものを作る。ただそれだけを徹底したからでした。
小川町では非常にいい循環が広がっているような気がしますが、そのようなまちおこしを進めていく上で必要な条件というのはありますか?
![]() まちおこしには一般に「よそもの、若者、ばかもの」が必要だと言われますが、じつはこれに加えて、この3者を結ぶコーディネート役の存在が非常に重要だ、と感じています。そういう人がいることで、よそもの、若者、ばかものが思いきり力を発揮できるようになるからです。
まちおこしには一般に「よそもの、若者、ばかもの」が必要だと言われますが、じつはこれに加えて、この3者を結ぶコーディネート役の存在が非常に重要だ、と感じています。そういう人がいることで、よそもの、若者、ばかものが思いきり力を発揮できるようになるからです。
全国各地には今、「農商工連携コーディネーター」と呼ばれる人たちが活躍しはじめており、小川町の場合もそうしたコーディネーターの尽力があって、現在のようないいつながりができた。たとえば、商店街の肉屋さんがコロッケに地元のじゃがいもを使いたいと思って農協に相談に行ったところ、量が少ないから対応できないと、けんもほろろに断られた。その後、地元のお総菜屋さんと金子さんの集落の農家を結んだのは、有機農業とまちおこしの重要性について十分に勉強していたコーディネーターの女性でした。
小川町では今、彼女の努力で地元の有機食材も使った日替わりシェフのレストランが誕生したり、先ほどの造り酒屋から出た酒粕を使った特産品を作ろう、という動きも出てきたりしています。そうした形でしっかりした関係性を積み上げ、新たな特産物を生み出していけば、人は必ず外からやってきます。これからはモノが広域流通するのではなく、そこにしかないモノを求めて人間の方が動いていく。その方がずっと健全な食の流通のあり方だ、とわたしは思っています。
東日本の復興には真の「強い農業」が鍵を握る
3月11日の東日本大震災では、農業や漁業を生業として営んでいる人たちが多く住む地域が被害を受けました。こうした地域が復興していくためには、何が一番大切だ、と思いますか?
![]() 「東京のため」という考え方を一切捨てることです。まずは地元。いいものを作って、地元で消費していく、あるいは加工していく。残ったら、それを都会に出す。そういう基本的な発想の転換が必要だと思います。
「東京のため」という考え方を一切捨てることです。まずは地元。いいものを作って、地元で消費していく、あるいは加工していく。残ったら、それを都会に出す。そういう基本的な発想の転換が必要だと思います。
国は最近、「強い農業」という言葉を使いますが、そのイメージするところの中心は大規模農業です。わたしは、農業の大規模化には反対です。なぜなら、農業の大規模化が失敗したことはすでに歴史が証明しているからです。
1961年に農業基本法を制定してからというもの、国はずっと農業の大規模化を言い続けてきたわけですが、その結果、日本の食糧自給率は1960年の79%から直近の39%まで下がり続けています。大規模化は日本の農業の生産性や競争力を高めるどころか、それを細らせる方向にしか働いてこなかった、と思います。
わたしが考える「強い農業」とは何かと言えば、地産地消に支えられた農業です。しかも、それはなるべく農薬や化学肥料を使わない、有機農業であるべきだと思っています。
1960年代以前の日本の農業は「有畜複合農業」と言いまして、どの農家にも1頭、2頭の牛か豚がいて、数十羽の鶏が飼われていました。そして、人々はその家畜の糞と雑木林の落ち葉、野菜屑で堆肥を作り、それを土に返すことで恵みを得てきました。経済成長期、日本人はそうした農業を徹底的に「遅れた農業である」として排除しようとしてきたわけですが、今、世界中の人々が求めているのはまさに、そうした農業なわけです。
有機で作れば手間はかかりますし、一般のものや海外産のものに比べれば価格が多少は高くならざるを得ないでしょう。しかし、食の安全や安心を求めるならば、農家が再生産できる価格を適正価格として受け入れることもある程度は必要になってきます。加えて、今ある食の広域流通のあり方も根本的に見直して行かなくてはなりません。じつは、そうした「食」にまつわるもろもろの実情を子どもたちに伝え、考えさせていくのが、本来あるべき「食育」の姿だとも思っています。
むろん、有機で作られた農産物がどんなにいいとわかっていても、高すぎれば人は買えません。しかし、地産地消を徹底させ、中間のマージンを少なくしていけば、その価格はふつうの農産物の2~3割高ぐらいに抑えられるはず。それくらいの価格であれば、買おうという人は決して少なくないはずです。
おいしくて安全・安心できるものには人はお金を払うもの。それを信じ、それを理解してくれる人に向けて食べ物を作り、売っていくのが「強い農業」を作る基本であり、本来の意味での「復興」だ、とわたしは思います。
バックナンバー
過去に掲載されたバックナンバーをご覧いただけます。
お問い合わせ[お客様サービスセンター]
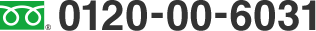

- ※電話番号のお掛け間違いにご注意ください。
- ※自動音声でご案内後、担当者におつなぎします。
- ※休み明けは電話が混み合うことがございます。ご迷惑をおかけしますが、ご了承ください。