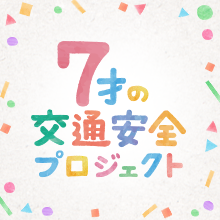- こくみん共済 coop の公式ホームページ
- あんしんのタネ
※東日本大震災を受けて「今月のおすすめ」4月号は休載します。
また、次月以降の掲載内容や更新時期は未定となっております。予めご了承ください。

現代の社会を、より良くそして健やかに生き抜いていくために、私たちは、人間の持つさまざまな「力」を体得し高めていく必要があります。「生きる意味を見つけること」「コミュニティーの一員として自分に何ができるかを考えること」「現実をクールに分析・理解すること」「自分に尊厳を持つこと」等々──。そうした一つひとつの「人間力」こそが、私たちの人生を豊かで実りの多いものに導いてくれるはずです。
最終回のテーマは、「対話力」。
相手を知るためだけではなく、自分を知るためにも必要な対話力とは何かについて、政治学研究者で東京大学名誉教授の石田雄さんにうかがいました。
対話に必要なのは他者感覚である
シリーズの最後を締めくくるにあたり、私たちは「対話力」というテーマを選びました。その理由は、職業や立場、あるいは置かれた環境の違う人たちの間で必要なコミュニケーションが成立しなくなり、意識の共有がますます難しくなってきている、という認識があるからです。石田先生は、この点に関してどのような印象をお持ちでしょうか?
![]() 社会のいたるところで、会話はあっても対話は成立しない。これはたしかに、おっしゃる通りだと思います。では、単なる会話と対話は何が違うのか。まずは、この点を明確にすることから話を進めたいと思います。
社会のいたるところで、会話はあっても対話は成立しない。これはたしかに、おっしゃる通りだと思います。では、単なる会話と対話は何が違うのか。まずは、この点を明確にすることから話を進めたいと思います。
たとえば、会社の食堂、あるいはエレベーターの中で社長と社員がばったり会ったとします。そこで、社長が社員に向かって「どうだ、元気か?」と問い、社員が「元気です」と答える。あるいは、「ところで、今月の売上はどうだ?」「おかげさまで順調です」などの会話を交わしたとしても、果たしてそれは対話と呼べるのか、という問題です。
社員にしてみれば、社長に睨まれてクビになっては困るでしょうし、評定が悪くなって賃金が上がらないのも困るでしょう。そうすると、自分の思っていることを正直に話せる訳がない。もしも、社長がそのことを十分に認識した上で会話をしていなかったとしたら、そこには対話は成立していません。
もうひとつ、別の例を挙げましょう。体調を壊した患者が病院に行ったとします。このところの病院のサービスはかなり良くなり、患者のことを「患者さま」と呼んだりしています。しかし、肝心の診察時間は相変わらず短く、医者は患者を診ずにパソコンに表示された数値やレントゲン映像ばかりを見ていることがある。こういう場合もやはり、対話が成立しているとは言い難いでしょう。
単なる会話と対話の違いは何かと言えば、私はそこに「他者感覚」があるかないか、だと思っています。それは単なるテクニックの問題ではなく、姿勢の問題です。そして、この他者感覚を持って相手に接するという姿勢が失われつつあることが、先ほどおっしゃられた対話が成立しないという問題に大きく絡んでくる重要なポイントだと思っています。
「他者感覚を持つ」ことは「相手に同情する」こととは違うのでしょうか?
![]() 相手がかわいそうだから相手の身になって考えましょうというのは単なる道徳的な態度であり、私の考える他者感覚を持つ意味とは違います。その本来の目的はむしろ、相手からの本質的な問いかけを引き出すことによって、社会における自らの位置を正確に掴むことの方にあるからです。
相手がかわいそうだから相手の身になって考えましょうというのは単なる道徳的な態度であり、私の考える他者感覚を持つ意味とは違います。その本来の目的はむしろ、相手からの本質的な問いかけを引き出すことによって、社会における自らの位置を正確に掴むことの方にあるからです。
マックス・ウェーバーは「あらゆる合理的文化の中心地点では新しい考え方が生まれにくい」と指摘しました。それはなぜかというと、「毎日電車で通学することに慣れっこになっている子供が、いったいどうして電車が走りはじめることができるのか、を問うことはほとんどないからだ」と。これと同じで、同質の集団とばかり接していると、本質的なことは何も見えなくなっていきます。本質への問いかけは、周辺にあって、異なった文化と接触をした場合にのみ起こる。その時に必要になってくるのが、この他者感覚なのです。
私が特に重要視したいのは、自分より弱い者に対する他者感覚です。人はたいてい被害には敏感ですが、加害については鈍感です。だとすれば、気づいている被害者の方からなるべく多く「あなた、私の足を踏んでいますよ」と言ってもらう必要があります。
足を踏んでいることに気づかない人は、相手から指摘されてようやく「ああそうか」と気づき、これまで思いもよらなかった社会の構造に目がいくようにもなります。ひょっとして、自分の頭の上にも何かしら重いものがのっかっているのかも知れない、と感じ、上への問いかけをしてみようかという気にもなる。
ですから対話というのは、本来は他人のためではなく、自分自身をよく知るためにこそ必要なものだというのが、私の考えです。
強くなる縦割り社会と二重構造の終焉
自分を知るためにこそ対話は必要だというご指摘は、とても新鮮です。その一方で、現実には対話どころか会話そのものが難しいという状況も広がっています。たとえば、同じ会社の中にいても、話し合う時間がとれない、あるいは、ほんの少し部署が違うだけで言葉が通じない。こうした問題は、どう考えれば良いのでしょうか?
![]() それは、いわゆる縦割り社会で起きる問題だと思います。縦割り社会の中では、言葉は常に上から下へと伝わる。それを繰り返していくと、それぞれの社会だけで通じるジャーゴン(専門語)がたくさんできてしまって、外の社会との対話が成立しにくくもなっていきます。じつは、こうした縦割りの現象が世界規模で起こっているのが、今のグローバル化だと思います。
それは、いわゆる縦割り社会で起きる問題だと思います。縦割り社会の中では、言葉は常に上から下へと伝わる。それを繰り返していくと、それぞれの社会だけで通じるジャーゴン(専門語)がたくさんできてしまって、外の社会との対話が成立しにくくもなっていきます。じつは、こうした縦割りの現象が世界規模で起こっているのが、今のグローバル化だと思います。
少し歴史的な経緯をご説明しますと、日本の近代化というのはそもそも、もともとある伝統的な連帯の上に西欧から取り入れた目的合理主義的な組織のあり方をのせる、というやり方で進んできました。つまり、日本はこの二重構造をうまく利用することによって、戦前は富国強兵、戦後は経済至上主義へと突き進んでいった訳です。ところが、現在ではその二重構造が底辺から崩れてしまい、機能しなくなってきている。その結果、今度はあらゆる組織で、どうすれば対話が生まれるのかという問題に真剣に取り組まなければならなくなってきたというのが、今日起きている現象だと思います。
たとえば、日本企業にはかつてQCサークルという職場の連帯を基本とする組織がありました。この組織は、一方では企業の生産性を高めることに使用され、もう一方では組合活動にも使われていた。これを情報の流れという観点で眺めると、ひとつのパイプが、ある時は上から下への意思伝達に、またある時は別の下からの不満を吸い上げる機能を担っていた訳です。
ところが、上からの合理化要求があまりに強くなると、このパイプの流れが次第に一方通行になり、下からの不満が上がらなくなる。自分が経営者である間に株価を上げなければ経営者自身もクビになってしまうということになれば、人件費をなるべく減らして、QCサークルなんていうややこしいことはしない方がいい、ということにもなってきます。その結果何が起こったかと言えば、組織全体に血が通わなくなり、非常に不健全な状態にもなってしまいました。
先ほどの二重構造で言いますと、合理的な組織それ自体が肥大化し、自己目的化してしまい、それを支えていたはずの伝統的な連帯を破壊し始めた。派遣社員の問題などグローバル化に伴って噴出している様々な問題の根っこには、じつはこうした二重構造の終焉という問題が隠れていると思うのです。
そうした状況のなかで、寸断された人々が出会う場も
少なくなっているように思います。
![]() かつては、家庭の中にあれば多世帯で世代を超えた対話が生じ、地域の中にあれば若衆宿のような風習があり、否が応でも顔をつきあわせなければならない場面が多くありました。むろん、そうした伝統的な連帯にも、同調性を強く求めるあまり、個性を殺してしまうような負の側面がなかった訳ではありません。しかし、それでもともかく、対話が成立する場だけはいくつもあった。しかし、今はその場をどう作っていったらいいかでみなが悩まなくてはならない時代になってきた、ということだと思います。
かつては、家庭の中にあれば多世帯で世代を超えた対話が生じ、地域の中にあれば若衆宿のような風習があり、否が応でも顔をつきあわせなければならない場面が多くありました。むろん、そうした伝統的な連帯にも、同調性を強く求めるあまり、個性を殺してしまうような負の側面がなかった訳ではありません。しかし、それでもともかく、対話が成立する場だけはいくつもあった。しかし、今はその場をどう作っていったらいいかでみなが悩まなくてはならない時代になってきた、ということだと思います。
人々を寸断する要素としてもうひとつ指摘しておかなければならないのは「競争」です。先ほどもお話したように、日本の近代社会は同調と競争の結びつきによって成立してきました。ところが、この競争にもじつは二種類ある。ひとつは、自分たちの間で知識を積み上げていって高みに達しようという、積み上げ式の競争。もうひとつは、他者を蹴落としてでも上へ行こうとする排他的競争です。現在問題になっているのは、おもに後者の方の競争だと思います。
この一番極端な例が、明治のはじめの頃に採用された、紡績工場における競争賃金です。この賃金制度では、Aという女工さんの生産量が昨日より多くても、それだけで賃金は上がりません。その日の相対的な順位で賃金が決まっていく仕組みですから、絶えず他人より上回る結果を出さなければならないというプレッシャーがかかる。
こういう排他的競争の原理がつよくはたらく組織では、どうしても横の連携は薄れます。しかも、現代はその排他的競争が世界規模で拡大していますから、どこまで競争しても先が見えない。結果、個人がどんなに頑張っても報われない社会ができあがってしまった。
この悪循環を断ち切るためには、どのような考え方が必要になるのでしょうか。
![]() ドイツの社会学者であるユルゲン・ハーバマスはこのような仕組みを、「システムが生活世界を植民地化した」という言葉で表現しました。その構図を簡単に説明すると、最初にまず「これだけの利潤をあげよう」という目的が上の方で設定される。すると、そのためにはどういう仕組みが最も効率的で効果的かという観点で、その目的追求のためのシステムが組まれる。そして、結果的にはそのシステムそのものによって生活世界全体が破壊されてしまう。これが今、世界規模で起きていることの本質です。
ドイツの社会学者であるユルゲン・ハーバマスはこのような仕組みを、「システムが生活世界を植民地化した」という言葉で表現しました。その構図を簡単に説明すると、最初にまず「これだけの利潤をあげよう」という目的が上の方で設定される。すると、そのためにはどういう仕組みが最も効率的で効果的かという観点で、その目的追求のためのシステムが組まれる。そして、結果的にはそのシステムそのものによって生活世界全体が破壊されてしまう。これが今、世界規模で起きていることの本質です。
ならば、この植民地状態をどうやって抜け出したらよいか、というご質問ですが、じつは非常に簡単で、発想を逆転させればいいのだと思います。すなわち、利潤をあげる目的を追求することによって人々の暮らしを豊かにしようとするのではなく、豊かな暮らしを実現するにはどのようなシステムが最適かという観点から、システムそのものを組み直していく。これが今、世界的に求められていることでもあると思います。
ここで言う豊かさとは、物質的な豊かさばかりではなく、精神的な豊かさ、より人間らしい生活をするための豊かさを含みます。そして、それを構築していくために欠かせないのが、言葉です。
問題は、その言葉そのものが失われた状態にあるにもかかわらず、多くの人がそれを認識できていないことにある。じつはこの失われた言葉を取り戻す重要な手段が、対話なのです。
放っておくと、人は言葉に使われる
「言葉を失った状態」とはどういう状態を指すのでしょうか?
![]() 簡単に言うと、言葉を使うのではなく、言葉に使われている状態です。その最もわかりやすい例として、戦時中の体験を挙げて申し上げます。
簡単に言うと、言葉を使うのではなく、言葉に使われている状態です。その最もわかりやすい例として、戦時中の体験を挙げて申し上げます。
戦時中の軍隊には軍隊内務令という決まりがありました。そこには命令は絶対であり、どのような内容であれ、その当不当を論じ、あるいは理由を問うてはならない、と書かれていました。逆らえば、陸軍刑法によって最高死刑が言い渡される。そういう緊迫した状況のなかで、私はある日、こんな体験をしたことがあります。
陸軍の中隊長だった私の元に、米軍の飛行機が墜落し、それに乗っていた米兵がパラシュートで避難したという連絡が入りました。現場に駆けつけると、その米兵が東京湾を泳いで岸に向かってくるというので、近隣の人々がみな竹槍を持って集まって来ていました。
戦時国際法では、捕虜は殺してならないことになっています。私は隊長ですから、現場で竹槍を止めることはできる。しかし、それを司令部に報告して「殺せ」という命令が下ったら、その命令には従わなければなりません。
「米兵が岸に着いたらどうしよう」と、私は焦りました。自分は人を殺したくない。けれど、命令が下れば、誰かに「殺せ」と命じることになる。それを拒否すれば、今度は自分が殺されるかも知れない。
結局、その時はたまたま通りかかった海軍がその米兵をボートに乗せて連れて行ってしまいましたから、私は決断を下さなくても良かった訳ですが、戦争が終わって戦犯裁判が開かれると、同じような状況で米兵を殺した日本兵が、BC級の戦犯で裁かれることもありました。
つまり、言葉を失うというのはどういうことか。私の経験から申し上げると、それは考える力を失うということに等しい。命令に対して絶対服従の状態が続くと、人は言葉を失うだけではなく、思考力を失う。私がそれを痛切に感じたのは、敗戦になって日本がポツダム宣言を受諾した時です。内容を読んでも、何が書いてあるのかまったく理解できない。上から言われたことをただやればいいという状況に慣れきってしまっていたがために、言葉を理解し、自分自身で考える能力を完全に失ってしまっていたのです。
現代社会において、それと似たような状況にあるのはどのような人たちでしょうか?
![]() 北イタリアに住むユダヤ人であったプリーモ・レヴィーは第二次世界大戦中、アウシュビッツに強制収容され、後にその体験を『溺れるものと救われるもの』(竹山博英訳、朝日新聞社)という本に書きました。その中で彼は、「灰色の領域」という言葉を使っています。その意味するところは、加害者と被害者の間の境界線というのはそう明確に引けるものではなく、大多数の人々は加害者であると同時に被害者でもある、ということです。現代社会もこれと同じように、多くの人は新自由主義的なグローバル化の被害者であると同時に加害者にもなっている。つまり、だれがどれほど言葉を失った状態にあるかという差は、言ってみれば程度問題だ、ということになります。
北イタリアに住むユダヤ人であったプリーモ・レヴィーは第二次世界大戦中、アウシュビッツに強制収容され、後にその体験を『溺れるものと救われるもの』(竹山博英訳、朝日新聞社)という本に書きました。その中で彼は、「灰色の領域」という言葉を使っています。その意味するところは、加害者と被害者の間の境界線というのはそう明確に引けるものではなく、大多数の人々は加害者であると同時に被害者でもある、ということです。現代社会もこれと同じように、多くの人は新自由主義的なグローバル化の被害者であると同時に加害者にもなっている。つまり、だれがどれほど言葉を失った状態にあるかという差は、言ってみれば程度問題だ、ということになります。
たとえば、いわゆる「派遣切り」の問題。その被害者を支援する「派遣村」の取り組みに対し、「税金の無駄遣いだ」という声が挙がる。そう言う人たちのよって立つ根拠は「自己責任論」ですが、彼らには、自分たちもじつは灰色の領域の一部である、という自覚がないのではないでしょうか。派遣村にたどりつくことさえできない人たちの中には、自殺か、路上死か、それとも食べ物を盗んで犯罪人になるか、という選択肢しかない人がいる。それを見て見ぬふりをするということは、自分自身もまた、誰かに足を踏まれているかも知れないという現実を、見て見ぬふりをしているということに等しい。
それは私の表現で言えば、言葉に使われているだけであって、言葉を使ってはいないことになります。
言葉に使われないために、自分の立ち位置を掴む
インターネットが普及した現代において、言葉はより手軽で身近なものにもなっています。ブログやソーシャルネットワークなどの手段を使って、誰でも手軽で簡単に言葉を発することができますし、場合によってはそれによって世界中とつながることもできます。しかし、そのことによってより不自由になったり、むしろ知性が失われたりするような現象も起きているように思います。進んでいく情報化社会に対して、個人はどのような意識をもってのぞむべきでしょうか?
![]() 道具を使う場合には、その道具の特徴というのを理解しておく必要があります。相対で人と接する場合、言葉を交わしながら相手の表情も見えるし、場合によっては、一言も言葉を発しなくても言いたいことが瞬時に伝わることもある。しかし、インターネットの場合は、言葉を発しなければ相手には存在していないも同然の環境になってしまいます。逆に言えば、インターネットという道具の使い方を間違えると、そこにいるはずの存在が見えなくなってしまう危険性があるということは、十分に認識しておく必要があると思います。
道具を使う場合には、その道具の特徴というのを理解しておく必要があります。相対で人と接する場合、言葉を交わしながら相手の表情も見えるし、場合によっては、一言も言葉を発しなくても言いたいことが瞬時に伝わることもある。しかし、インターネットの場合は、言葉を発しなければ相手には存在していないも同然の環境になってしまいます。逆に言えば、インターネットという道具の使い方を間違えると、そこにいるはずの存在が見えなくなってしまう危険性があるということは、十分に認識しておく必要があると思います。
同時に、インターネットで何かを発信する場合には、それが単なる感情の発露なのか、それとも自分の生み出した言葉、思想を伝えているのか、という点も考えなくてはならないだろうと思います。感情は表出することによって解消される場合もあれば、加速される場合もある。憎悪は特に、表出することによって非常に加速し、加速した憎悪が自分自身に跳ね返ってくるは恐さもあります。
それが最も顕著に表れた例は、アフガニスタンの戦争です。「恒久的自由のためのオペレーション」という言い方をされていたかと思いますが、本来、人間を解放するために作り出したはずの「自由」という言葉が、あの場合には人間を支配するための道具にも使われてしまった。あるいは、人を殺すための武器にさえなってしまった。つまり、言葉というのはこのように常に二面的な意味を持つものです。
このことを十分に認識せずに言葉を使うならば、それは言葉を操っているつもりでも、じつは言葉に操られているに過ぎないということになろうかと思います。
言葉に使われないために心がけておくべきことは、何でしょうか。
![]() 最初に指摘したことに戻りますが、やはり、他者感覚を忘れないということに尽きると思います。有史以来、人間は言葉を作り、それによって思想を形成し、豊かな社会を実現してきました。それはすなわち民主主義であり、自由であり、人権であり、ということだと思います。ところが、人間が作り出した言葉や思想というものは、時に人間を支配する道具にもなってしまう。私がこのことを繰り返し申し上げているのは、そういう支配の道具のために言葉を使うことに、二度と荷担したくないという強い思いがあるからです。
最初に指摘したことに戻りますが、やはり、他者感覚を忘れないということに尽きると思います。有史以来、人間は言葉を作り、それによって思想を形成し、豊かな社会を実現してきました。それはすなわち民主主義であり、自由であり、人権であり、ということだと思います。ところが、人間が作り出した言葉や思想というものは、時に人間を支配する道具にもなってしまう。私がこのことを繰り返し申し上げているのは、そういう支配の道具のために言葉を使うことに、二度と荷担したくないという強い思いがあるからです。
ならばその言葉を、本来の目的である人々の暮らしをより豊かにすることに使っていくためにはどうすればいいか。それは、現在使っている言葉の意味を問い直し、より豊かな思想を作り出していくことしかないでしょう。こう言うと、それは学者が考えることで、自分たちには関係のないことだと感じるかも知れません。しかし、私たちは誰しも言葉なくては生活できませんし、思想がなければ生きられません。言葉というものから逃れられない以上、それをどうしたらよりよく使っていけるかという問題は、じつは私たち全員にとって最も身近で切実なテーマである、とも言えます。
利潤追求のための合理的なシステムがグローバルに拡大してしまった現在、世界で起きている現実と自分の身の回りにある生活を結びつけて考えることが、非常に困難な時代にもなってきました。だからこそ、人間らしい暮らしを取り戻すための第一歩は、その膨大に広がる灰色の領域のなかで、果たして自分はどこに立っているのかを正確に把握することだと言えるでしょう。そのためには、自らや自らが属する組織に対する絶え間ない問い直しが必要であり、それを可能にするための他者との対話が必要になってきます。もっと言えば、自分より周辺にいる人たちに対する他者感覚が非常に強く求められている時代にもなっている。
健全な民主主義の社会、あるいは生きやすい社会というのは本来、そうした絶え間ない対話と問い直しを繰り返していくことでしか、作り得ないものだと思います。
-

-

-
1923年青森市生まれ。東京大学名誉教授。「学徒出陣」から復員後、丸山眞男ゼミに参加し、1949年東京大学法学部卒業。同学部助手を経て、1953年東京大学社会科学研究所助教授、1967年同教授。1984年定年退職後、千葉大学教授、八千代国際大学教授を歴任。その間、ハーバード大学、エル・コレヒオ・デ・メヒコ(メキシコ)、オックスフォード大学、アリゾナ大学、ダル・エス・サラーム大学(タンザニア)、ベルリン自由大学などで研究・教育にあたる。専門は、明治期以後の政治思想史および政治学。著書は『丸山眞男との対話』(みすず書房、2005年)、『一身にして二生、一人にして両身--ある政治研究者の戦前と戦後』(岩波書店、2006年)『誰もが人間らしく生きられる社会をめざして--組織と言葉を人間の手に取り戻そう』(唯学書房)など多数。
バックナンバー
過去に掲載されたバックナンバーをご覧いただけます。
お問い合わせ[お客様サービスセンター]
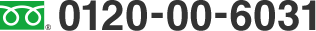

- ※電話番号のお掛け間違いにご注意ください。
- ※自動音声でご案内後、担当者におつなぎします。
- ※休み明けは電話が混み合うことがございます。ご迷惑をおかけしますが、ご了承ください。