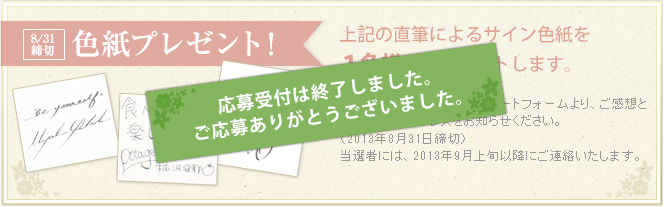-

- ふじさわ・くみ/1967年、大阪府生まれ。1989年、大阪市立大学卒業後、国内外の投資運用会社勤務を経て、96年、日本初の投資信託評価会社を起業。同社を世界的格付け会社スタンダード&プアーズ社に売却後、2000年ソフィアバンク設立に参画。現在、代表。1000社にのぼる企業経営者インタビューを続け、07年からは、世界経済フォーラムから「ヤング・グローバル・リーダー」に選出され、世界25カ国を訪問し、被災地や貧困地域の支援活動に参加。各種メディア・講演を通じて、経済や経営について提言を続け、全員参加型の社会づくりに取り組む。法政大学大学院客員教授の他、政府各省の審議委員等公職も多数兼務。代表的な著書に『子どもに聞かせる「お金」の話』『なぜ、御用聞きビジネスが伸びているのか』など。

私が就職活動をしていた頃は、女子が門前払いを食らうのが当たり前でした。企業に電話をかけるたびに冷たくあしらわれ、社会に出ても女性は活躍できないのではないかという思いが募るばかり。それなら性別関係なく、がんばった人が評価される会社を、自分たちでつくるしかない!同級生とそう話したのが、起業のきっかけです。
就職活動のときは、国際投信委託(現 国際投信投資顧問)に入社したいと強く思っていました。面接のとき、社長に「経済学部出身ではないですが、猛勉強して1年で追いつきますから、私を雇ってください」なんて啖呵をきるくらいに。もう、とにかく入りたかったんです。トイレに行きたいのと一緒です(笑)。どうしても行きたかったら、普段なら考えられないような行動をしてしまいますよね。
国際投信委託に入りたかったのは、アナリストになりたかったから。なぜアナリストかというと、未来を知りたかったんです。ちょっと変な動機だと思いますか?その大本は、子ども時代、ベートーベンの伝記を読んで、人間がいつか死ぬことを知り、自分もいつかは死ぬのだとショックを受けたことにあります。自分が死んだあと、それでも世界が続くなんてと、衝撃と失望と恐怖を感じました。だったら、できるだけ死んだ後の世の中がどうなっているか知りたいと思ったんです。だから、子どもの頃は占いを勉強してたんですよ。それが、就活のときに就職案内の冊子を読んでいたら、アナリストのページに「世界の未来を予測する」って書いてあった!もうこれしかないでしょう(笑)。だから、もともと投資や金融に興味があったわけじゃないんです。

国際投信委託に採用してもらい、さあアナリストになるぞと意気込んでいたら、配属されたのは投資信託を設計してプロモーションする部署でした。こんなことをやりたかったわけじゃないと3日で辞めたくなったのですが、とりあえず投資信託のことを勉強するため毎日仕事の予習復習をしていました。しかも、起業のために毎日800円しか使わないと決めてお金を貯める地味な日々。
ところがなかなか事業アイデアも浮かばないし、仕事も行き詰まってきた。そんなときに、ふと結婚して子どもができたら、この苦労から逃れられるかなと思ったんです。それと同時に、ああこうやって女の人は逃げ道が用意されてるんだな、とも思いました。本当に子どもがほしいならともかく、出産を逃げに使ってはいけない。そう考えて、もうちょっとがんばることにしたんです。
そうしているうちに提携してくれる会社が見つかり、29歳のときに起業しました。しかし、投資信託を評価するビジネスなのに、ベンチャー企業だからと大企業がデータを提供してくれない。データがないと評価はできません。まともな売上は半年くらいたちませんでした。年収は96万円にまで落ち、ドトールのコーヒーも高くて買えませんでした。
オフィスもなるべくお金をかけずにつくろうと思ったので、コピー機は知人から無料でいただいた中古品。ソート機能がなくて、出力した何十枚もの紙をみんなで順番に並べていました。北向きで寒いオフィスで、冬はコートに手袋でデータ入力をしていました。それでもすっごくおもしろかったんです。「この案件がうまくいったら、月1億の売上になるかも!」などと言いながら、一つでもアポイントが決まると夢が広がって、みんなで盛り上がっていました。
やりたいことのために努力するのは、辛くないんですよね。傍から見ると、貧しくてかわいそうに見えたかもしれないけれど、本当に楽しかったです。

『NHK教育テレビ ビジネス塾』
出演時(2004年)
そのうちに、投資信託の評価の分野に大手企業が参入してくるようになりました。私たちがやりたかったのは、業界内に隠されていた情報を世の中に行き渡らせることだったので、そうした目的を大手企業が果たすならそれでもよかった。会社は売却することにしました。
売却した翌年に、シンクタンク・ソフィアバンクを立ち上げます。NHKの番組でキャスターをやらせていただく機会にも恵まれました。そして、NHKのキャスターをやると、知名度が上がり、すごく世の中の評価が変わったんです。その環境に慣れてしまっていたんでしょうね、2005年に番組が終わったとき、どうしていいかわからなくなってしまいました。ネットには「藤沢久美はもう終わった」なんて書かれるし、仕事を断れば「偉そうだ」と言われる。評価されないことがおそろしくてたまらなくなりました。
悩んでいるうちに、体のいろいろなところが腫れ、蕁麻疹が出て、人前に出られないようになりました。検査をしても特に原因が見つからず、完全にストレスが発端だったのです。症状が深刻になりとても仕事ができる状態でなかったため、3ヶ月まるごと休むことにして、宗教書や哲学書などいろいろな本を読んで考えました。たどり着いた結論は、いろいろな人がいろいろなことを言うけれど、自分に責任をとれるのは自分しかいないということ。自分の心にもっと正直に生きていこうと思いました。そこからすうっと楽になり、体も回復していきました。
その2年前に父が亡くなったのですが、亡くなる1年前くらいに仕事のことで、すごくイライラしていました。様子を見ていて、父は病気になるんじゃないかと思ったんです。人は誰かを非難し続けたり、不本意に過ごしていると、体が壊れていく。そして最悪の場合、命を失うことがある。心が人の命を奪うんだ、ということを父が教えてくれたんじゃないかと思っています。

起業したときは、世の中のためになりたいという思いが強かったわけではなくて、ただ公平な組織をつくってそこで働きたいと思っただけでした。でも起業したらいろいろな人に助けてもらうことになり、その方々に恩返しをしたいと思うようになりました。また、若くて何の実力もない人間でも、動けば世の中が変わるということを実感したんです。それまでは、世の中は政治家や大企業の幹部など、巨大な権力を持った一部の人間が動かしていると思っていました。でも、誰でも行動を起こせば、少し世の中を変えることができるんです。世の中を動かせると、超楽しいんですよ(笑)。その感じをみんなに体験してほしいと思ってやっていることが、結果的に社会起業家の育成などにつながっています。
いま興味があるのが、養子縁組と障がい児教育です。私の友だちには40歳を過ぎてから不妊治療をしている人も多くいるのですが、すごくお金がかかるし、心と体の負担も大きい。その一方で、中絶数は年間20万件を超えます。このマッチングをうまくできないかと思うんです。また、日本では障がい者として生まれると、障がい者年金をもらい、一生障がい者としての人生を送る人が非常に多い。でも、海外では特別な才能を生かし、社会で活躍する機会が存分に与えられている障がい者の方がたくさんいます。そういった、能力を伸ばせる学校や社会システムをつくれないかと考えています。
死んだあとの世界まで見通したいといいながら、今やっていることの結果は、自分が生きている間に出なくてもいいと思っています。少しずつ世界が良くなっていくような土壌をつくり、種を蒔ければいいかなって。「私がやったところで何も変わらない」と無力感に襲われるときもありますが、今はITで人々がつながり、共感が広がりやすい時代です。何か行動を起こせば、きっとどこかで世界が動くと信じています。