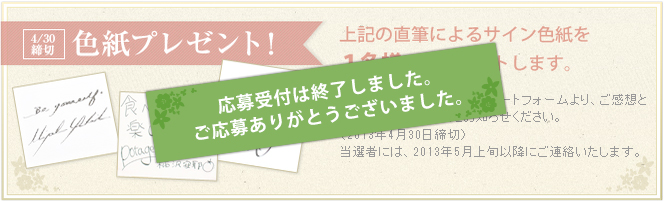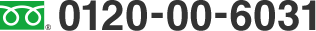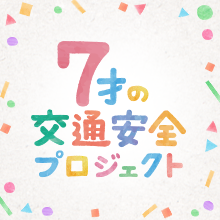-

- まきむら・さとる/1956年、東京都生まれ。73年、高校在学中に、少女漫画誌「別冊マーガレット」でデビュー。『愛のアランフェス』『ダンシング・ゼネレーション』などヒットをとばす。高校卒業後、メーカーに就職するものの、原稿料が給料を上回った時点で退職し専業作家に。自己のトラウマに向き合い、克服した経緯を綴った自伝的エッセイ『イマジンノート』は、多くの女性に支持された。また、その経験の後に生まれた、生きる自信にあふれた女性を主人公とする『おいしい関係』は、ドラマ化もされる大ヒットとなった。42歳で性人類学者のキム・ミョンガン氏と結婚。代表作に『イマジン』『BELIEVE』『Do Da Dancin'!』『Real Clothes』など。

私のターニングポイントは、35歳。これはもう、はっきりしています。父親から性的虐待を受けた過去に向き合い、受け入れたこと。自分を慈しむ自尊心を取り戻し、世界の捉え方が180度変わった。それが35歳のときでした。
それまでは、すごく生きづらかった。具体的に言うと、うまく人と付き合えないんです。自分の自意識がひりひりしていて、そのケアだけで手一杯。人を思いやる余裕がまったくありませんでした。そして、ぽっかりあいた大きな心の穴を埋める手段として、とにかくたくさん仕事をしていました。描いているのはすべて、自分のための漫画だったんです。でも、自分を肯定できてからは、読者のために描くようになりました。
トラウマをどうして乗り越えられたかは、いまだによくわかりません。こういうと身も蓋もないですが、もともともっていた生命力が強かったのでしょう。それは漫画家という職業を選んだことにも表れています。漫画家は腱鞘炎になったり、腰を悪くしたり、精神的なストレスに耐え切れなくなったりと、途中でリタイアする人が多いんです。でも、私は、体は小柄ですが、トラックのエンジンがついているというか(笑)、かなり乱暴な運転をしても大丈夫なんですよ。心の壁を乗り越えるのにも、やっぱりエネルギーが必要です。つらくて、やましくて、封じ込めていた事実に直面するエネルギー。それは生来もっていた、生きたいと望む力だったんだと思っています。

父親からの虐待があったのは、ちょうど思春期に入るくらいの頃。そんな影を背負って、人生について考えていたわけですから、当然クラスの子とは話が合いませんでした。円満な家庭で育っている子は「郷ひろみと野口五郎どっちがいい?」みたいな話題で盛り上がっているんですが、いやいや、と(笑)。まったくついていけなかったですね。でも、群れなくても平気でした。一匹狼だと、いじめにも巻き込まれないし、気が楽だったんです。
ただ、誰かに自分のことをわかってもらいたいという強烈な思いはありました。だからこそ、漫画にのめり込んだんだと思います。そして、高校1年で漫画家としてデビューしました。最初のうちはよかったのですが、デビューして4、5年経つと、だんだん行き詰まってくる。自分勝手に描いていた作品を、人に伝わる作品に変身させていく時期に入るからです。線をなめらかにするなど、技術的な力を積み上げて、乗り越えていかなければいけない。その時期は苦しかったですね。つらくて先が見えないあまり、「結婚するのかな、私」と思いました。結婚「したい」んじゃなくて、この状況から逃げるための次善の策で結婚「する」。まあ、そう都合良くはいきませんでしたね(笑)。その時は、仕事・漫画と、結婚・奥さんというものを、簡単に天秤にかけられるような気がしていたんです。でも、それらはぜんぜん質が違うから、比べるようなものじゃないんですよね。

月刊誌「Cocohana」(集英社)で
連載中の最新作『YES!』は、
仕事にプライベートに悩む
29歳の女性が主人公の
ストーリー
デビューしてから40年。ずっと漫画を描き続けています。想定読者は、変わりたいと思っている人。変わりたいと思っているなら、10代だろうと60代だろうと、年齢は関係ありません。でも、誰かに庇護されて安穏と暮らしたいと思っている人は、私のお客さんではないですね。変わりたいと思って、本を手に取る人がいる限り、私は描き続けると思います。
漫画を描くのは大変です。物理的な手間もすごくかかるし、思ってもいないことを描いてしまうと、その先が続けられなくなる。体力的にも、精神的にも、常に追われています。でも、何年かに1回、「ああ、この子すごく好きだなあ」という女の子のキャラクターを生み出せることがある。そういう子を「描けた!」と思った瞬間、それに費やした分のエネルギーが補給されてるんです。不思議でしょう。お金や人からの評価だけでは続けられないです。その達成感があるから、続けられるんだと思います。
創作の芯の部分はなかなか変わらないですよね。新しい自分になろうとか、ぜんぜん違うものを描いてみようと意気込むこともあるんですけど、ムリムリ(笑)。そういうものでは変わりません。でも、読者にはいろいろな人がいて、私の作品にピンとくる人が新しく現れる。そういうことが繰り返されて、40年続けてこられたのでしょう。

先日、体を壊して、タクシーで病院に向かったときのことです。気持ちが悪く、お腹も痛くてエビのように丸まってやっとタクシーに乗ったら、運転手さんが一言。「おばちゃん、大丈夫? 病院?」。こんなにはっきり「おばちゃん」と言われたのは初めてで、「おばちゃーん」という声が、しばらく頭のなかをリフレインしていました(笑)。そのショックもさめぬまま、今度は救急病院の若い研修医さんから、「じゃあ、フリースを脱いで横になってください」との指示が。着ていたのはカシミアなのに…!(笑) いや、もう、体を悪くするといけませんね。自分でもその時の私を客観視したら、おばちゃんだと思いますし、そんなよれよれのおばちゃんが着てる毛玉の浮いたカシミアは、フリースに見えるでしょう。パーンと気を張って、キリッとしてないと、もう「おばちゃん」なんだなって実感しました。
私はずっと、誰かの可愛いアクセサリーでなくて、自立した人間、自立した女性として懸命に生きようよと、うたってきました。名前で呼ばれる存在になろう、成熟した大人を目指そうって。だからこそ「おばちゃん」って呼ばれたことがショックだったんですよね。でも、おばちゃんと呼ばれるなら、いいおばちゃんを目指さないとダメだ、とも思いました。「あらあら!」と言いながら、転んだおじさんに手を貸したり、子どもに飴をあげたりする、バイタリティあふれる快活なおばちゃん。こういうおばちゃんがいるから、世界はうまく回っているんです。ぼやーっと、その日の快不快だけで物事を判断するようなおばちゃんにはなりたくない。名前で呼ばれる大人の女になるか、世界を救ういいおばちゃんになるか、決めなければいけない歳になったってことですね。