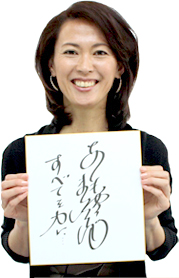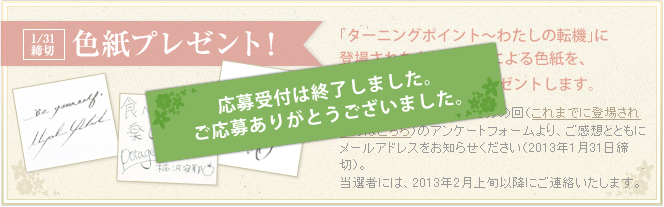-

- ありもり・ゆうこ/1966年、岡山県生まれ。就実学園高等高校、日本体育大学を卒業して、株式会社リクルート入社。バルセロナオリンピック、アトランタオリンピックの女子マラソンでそれぞれ銀メダル、銅メダルを獲得。カンボジアでのチャリティーマラソン参加をきっかけに、1998年、NPO法人「ハート・オブ・ゴールド」設立、代表理事就任。2002年、アスリートのマネジメント会社「ライツ(現:RIGHTS.)」を設立。2007年、プロマラソンランナーを引退。スペシャルオリンピックス日本 理事長。ほか、国際陸連(IAAF)女性委員会委員、日本陸上競技連盟理事、国連人口基金親善大使等を歴任。2010年6月、国際オリンピック委員会女性スポーツ賞を日本人として初めて受賞。同年12月、カンボジア王国ノロドム国王陛下より、ロイヤル・モニサラポン勲章大十字を受章。

私、実はマラソンが好きではありません。一心不乱に打ち込めて、評価してもらえるものなら、スポーツじゃなくても、何でもよかったんです。何のとりえもない私が、初めて1番になれたのが、中学生の時の800m走でした。その輝きが忘れられなくて、私のランニング人生が始まりました。
好きなことは大成しないというのが、私の持論です。よく「好きこそものの上手なれ」と言いますが、それでは「上手」どまり。好きなことは続けたいから、嫌になるまでやりこむことができないですし、何かをなし得るほどのレベルには達しないでしょう。「私にはこれしかない」と追い込まれて、初めて結果を出せる。大事なのは好き嫌いじゃなくて、出会ったことに、どう意味を持たせていけるか。可能性を見出せるか。可能性はもともと「ある」ものじゃなくて、「生む」ものなんです。

走ることを決めたものの、高校に入ってからはなかなか結果が出ませんでした。特に都道府県対抗駅伝に3年連続で出場できなかったのは、大きな挫折でした。3年目でまた補欠だと告げられた時、もう走ることを諦めようと思ったんです。でも、高校の陸上部の監督が「あんなに頑張った有森を出せなくて、自分もつらかった。駅伝はまだあるから、また一緒にやらないか」と言ってくださったんですね。それは衝撃的な言葉でした。結果や実績でなく、自分の人間性を認めて応援してくれる人がいる。走り続ける勇気がわいてきました。そこで、絶対に、国民体育大会(国体)か都道府県対抗駅伝に岡山県代表として出場して、恩返しがしたいと思ったんです。
リクルートの実業団に入って最初の年の国体は、恩師のこともあり、どうしても岡山県代表として出場したいと思っていました。そして、1万メートル走の最終予選で、ぶっちぎりの1位になりました。これで出られる! と喜んだのもつかの間、なんとマネージャーの手続きミスで岡山県代表として登録されていなかったことが発覚。マネージャーに抗議したら、「岡山にいたときの記録がよくなかったからじゃないの」と自分のミスを認めてくれなかったのです。監督にも「お前に実績があれば、こんなことにはならなかった。悔しかったら人に覚えてもらえるような選手になるしかない。」といわれました。悔しさと憎しみがない混ぜになったような感情でいっぱいになり、実績を残さないと存在すら認めてもらえないことを痛感しました。ここがプロの選手としての自覚が生まれた転機でしたね。

バルセロナオリンピック
日本代表ユニホーム

バルセロナオリンピック
銀メダル
その後、必死のトレーニングを重ね、バルセロナオリンピックで銀メダルを獲得しました。幸せの絶頂にいたはずなのだけれど、それからが地獄でしたね。実績を出せば、もっと走ることに対して自由になれると思ったのに、周囲からは「燃え尽き症候群だ」「わがままになった」などと批判される。次の目標が見えない。そんななか、足底腱膜炎という病気になり、痛みで走れなくなりました。
この行き詰まりを打破するために、両足を手術しました。本当のところでは、治したかったというよりも、手術の結果で選択肢をしぼりたかったんです。手術が成功しても悩んでいるくらいなら、走ることをやめる。成功して、「よかった、また走れる」と思ったら、続ける。失敗したら、諦める。このどれかに決めたかった。
でも、病院には、普通に生活できるかどうかという瀬戸際で戦っている方々がたくさんいました。走れるかどうか、というのはとても贅沢な悩みだったんです。そして、入院している皆さんが「有森さん、またオリンピック出るんですよね」と期待してくれる。私にはチャンスがあるのだから、それを活かさなければという使命感に目覚めました。
人生で一番幸せなことは、チャンスがもらえることなんです。火をつける能力があっても、マッチがないと意味がない。そのマッチにあたるチャンスを、みんな欲しがっている。これは、インドの女性から聞いた言葉です。インドの女性は、能力も高いし、パワフルです。でも、社会的に抑圧され、チャンスを与えられない。私が理事長を務めている、スペシャルオリンピックス(知的障がいのある人たちの社会参加を、スポーツを通じてサポートする国際組織)のアスリートの多くも、以前はそうでした。どんな人間も、チャンスさえあれば可能性を開くことができる。そう信じているので、チャンスをつかむエネルギーだけは、捨てたくありません。

1996年、2度目のオリンピックに出場し、銅メダルを獲得したあと、カンボジアのチャリティーレースに招待されました。最初は、正直、食べることにも困るような状況下でマラソン大会をすることに意味があるのかと思いましたね。でも、2回目のお話をいただいて行ってみたところ、子どもたちがマラソン大会をすごく楽しみにしてくれていて、いい意味での変化が見られたんです。しかも、その時は2人の首相が並び立つ不安定な政情だったのですが、マラソンでその2人が一緒に走ったのです。そうすることで、カンボジアが平和であることを内外に強くアピールすることができました。ざっと流れが変わった瞬間を目の当たりにして、初めて心から「走ってきてよかった」と思えました。自分が成長するための有効な手段だったマラソンが、自分だけでなく、社会に対してもいい変化をもたらすことを実感したんです。
誰もが一緒に参加できるのがマラソンのいいところです。スタートラインにつけば、プロもアマも大人も子どももありません。訴えたいメッセージを発信するには、もってこいの場です。ハート・オブ・ゴールド(1996年12月に行われたアンコールワット国際ハーフマラソンに関わった人々により、「スポーツを通じて希望と勇気をわかちあう」ことを目指して設立されたNPO。代表は有森裕子)の活動でも、エイズや地雷除去のことを子どもたちに伝える上で、スポーツイベントが効果的です。深刻な問題も、スポーツを楽しみながら学べるので、ちゃんと覚えて帰ってもらえるんです。

私がメダリストになった頃は、スポーツ選手として仕事をする道筋がありませんでした。自分の名前を使って、得意なことでお金を稼ぐ。その当たり前のことが、スポーツ選手には許されていなかった。自分の肖像権すら持てなかったんです。私は、マラソンランナーとして仕事がしたかったのに、名前を使って稼ぐならタレントになりなさいといわれました。その状況に意義を唱えるためにも、2回目のオリンピックでもう一度メダルをとることが必要だったんです。結果を出して、人生を自分で切り開きたかった。それが「生きる」ということだと思っていました。いま考えると、すごく不器用ですね。
最近、穏やかでほどほどな生きかたを選ぶ人が増えているように思えますが、私は不器用でも、必死に、本心でぶつかっていきたい。だって、生きている感じがするじゃないですか。考えたり、戦ったりしながら、躍動感のあるエネルギーを生みたいんです。それがまわりの意向と合致しないこともありますが、「有森裕子でありたい」というこだわりは捨てられません。
でも、頑固さゆえに、進歩できなくなっていると感じることもあります。自分のチャレンジする場を選んでしまっている。不得意なものを避けて、できる範囲のことをしている。それはやっぱり、マラソンの成功体験がネックになっているのだと思います。成功した上で、別の角度からそれをまた変えていくというのは、よほどのことがない限りむずかしいですね。いまも、ぜんぜん満足はしていません。進歩を求めて、次のターニングポイントを模索する日々です。