- こくみん共済 coop の公式ホームページ
- あんしんのタネ
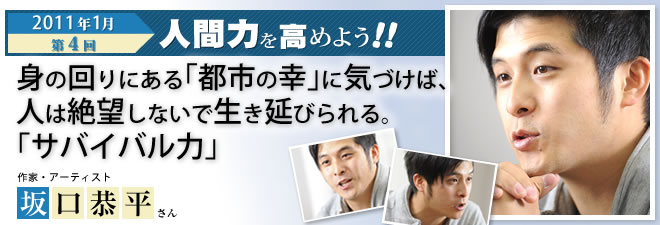
現代の社会を、より良くそして健やかに生き抜いていくために、私たちは、人間の持つさまざまな「力」を体得し高めていく必要があります。「生きる意味を見つけること」「コミュニティーの一員として自分に何ができるかを考えること」「現実をクールに分析・理解すること」「自分に尊厳を持つこと」等々──。そうした一つひとつの「人間力」こそが、私たちの人生を豊かで実りの多いものに導いてくれるはずです。
今月のテーマは、「サバイバル(生存)力」。
路上生活者の暮らしから「都市型狩猟採集生活」という独自の概念を生み出した、作家・アーティストの坂口恭平さんに、生き延びるための術についてうかがいました。
坂口さんは処女作『0円ハウス』を刊行して以来、路上生活者の住居や暮らしに
注目されています。そのきっかけは、なんだったのでしょうか?
![]() 僕がまだ、早稲田大学理工学部建築学科の学生だった時のことです。同級生の多くはゼネコンや大手設計事務所、あるいは名のある建築家の事務所に就職しようとしていましたが、僕はそういったところに入って働く気にはなれずにいました。「働く」ということに対して、納得できる答えが出せなかったんです。
僕がまだ、早稲田大学理工学部建築学科の学生だった時のことです。同級生の多くはゼネコンや大手設計事務所、あるいは名のある建築家の事務所に就職しようとしていましたが、僕はそういったところに入って働く気にはなれずにいました。「働く」ということに対して、納得できる答えが出せなかったんです。
他人のアイディアで建築を作るということに関しても、僕には「罪」に思えました。「こんなにたくさんビルが建っているのに、なぜ、また新しく建物を作らなくちゃいけないのか」という疑問を払拭できずにいたんです。同級生たちにそう言うと、「だって、それが仕事だから」と。けれども、それは単なる「無知の労働」であって「仕事」とは呼べないんじゃないか、と僕は思っていました。
それで、授業もロクに出ないで、多摩川の河川敷で仲間と酒を飲んで騒いだり、竹で筏を作ったりして過ごしていました。そんなある日、河川敷の竹藪にトンネルがあるのを発見したんです。中に進むと、竹垣があって、その奥に家があった。「なんだろう?」と思って訪ねたら、そこに20年間、猫数匹と一緒に住んでいる路上生活者のおじさんがいました。
彼はさまざまな廃材を拾ってきて、自力で家を建て、自然と一体化した暮らしをしていました。しかも、小さな畑を耕し、菜の花やきゅうり、トマト、モロヘイヤなどの野菜も育てていた。「なんなんだ、これは?」と、思いました。その頃、僕は家賃29,000円のアパートに住み、それすら払えなくて、数ヵ月分を滞納していたんです。同じ東京に暮らしていながら、「こんな生活があったのか」と、衝撃をおぼえました。
それで、「このおじさんは、お金も仕事もないのに、なぜ、不安を感じずに生きていられるのか調べてみよう」と思ったのが、そもそものはじまりです。
おじさんと話をしているうちに親しくなって「お前らもここに住んでみろ」と言われました。「住めるんですか?」って聞いたら、竹藪のどんずまりのスペースを紹介してくれて、「ここをお前らにあげるから」と。「あげる」って言っても、その土地はべつにおじさんが所有している訳じゃないんです。だけど、20年間住んでいて、誰も欲しがらない土地だということはわかっている。一般常識からするとおかしいんですけれど、感覚的にはとてもよくわかる気がしました。
実際に、路上生活も体験されたようですね。
![]() 2009年に一ヶ月間、多摩川のロビンソンクルーソーと僕が呼ぶ、20年もの間自給自足を続ける都市生活の達人のところで暮らしました。その時に、僕が家の中にパソコンを持ちこんだんですね。なんとなく気が引けて、「すんません、こんなところに人工物なんか持って来ちゃって」と言ったら、「坂口さんや」と。「僕にはそれも自然に見えます」と言われ、延々と説教されました。
2009年に一ヶ月間、多摩川のロビンソンクルーソーと僕が呼ぶ、20年もの間自給自足を続ける都市生活の達人のところで暮らしました。その時に、僕が家の中にパソコンを持ちこんだんですね。なんとなく気が引けて、「すんません、こんなところに人工物なんか持って来ちゃって」と言ったら、「坂口さんや」と。「僕にはそれも自然に見えます」と言われ、延々と説教されました。
彼はもともと、エンジニアだったんです。「超理系」ですから、パソコンの表面に使用されているボディーはどういう素材で、液晶は何と何でできている、ということを、まずは滔々と僕にレクチャーしてくれる。揚げ句に、「お前はなんで、人間が作ったものが人工物で、自然に備わっているものが自然だと考えるんだ」と徹底的に怒る。彼に言わせると、人工物と自然を分けて考えること自体がおかしいんだ、と。
僕は、びっくりしました。考えてみれば、コンクリートも自然にある砂や砂利をセメントで固めている。そういう意味で、人間はもともと身の回りにあるさまざまな「幸」を利用しながら生きてきた。だとすれば、おじさんのような生活はむしろ自然なことなんじゃないか。山には「山の幸」があり、海には「海の幸」があるように、都市には「都市の幸」がある、と考えればいいんじゃないか、と気づかされたんです。
坂口さんが言う「都市の幸」とは、一般的には「ゴミ」と考えられているものですよね?
![]() 社会におけるゴミとは、「他人が最も欲しがらないもの」なんです。だから、それを「一番欲しいもの」にすれば、最も効率よくモノが手に入る。実際、僕が知っている路上生活者の方たちはほぼ「0円」で生活し、時にはお金まで稼いでいます。
社会におけるゴミとは、「他人が最も欲しがらないもの」なんです。だから、それを「一番欲しいもの」にすれば、最も効率よくモノが手に入る。実際、僕が知っている路上生活者の方たちはほぼ「0円」で生活し、時にはお金まで稼いでいます。
彼らは、各地のゴミ置き場を大地の恵みをもたらす畑、公園の水道を自然の湧き水のように利用しています。ス―パーの掃除をしては廃棄食材を分けてもらい、パチンコ店で忘れ物のタバコを探す。多摩川の河川敷のスペースも、公園にある水も、アルミ缶もコンビニの売れ残り弁当も、タダで手に入る情報も、彼らにとっては立派な「幸」なんです。
そういう視点で彼らの暮らしを眺めると、都市そのものが彼らの「貯金」であることにも気づきます。彼らは必要な都市の幸を収穫しては生活の糧とし、余った分をお金に換えている。毎日がその日暮らしのように見えますが、所持金ゼロになっても絶望して死ぬようなことはありません。なぜなら、明日になればまた、都市の幸が実ることを知っているからです。
つまり、極めて高い解像度で都市を見つめ、多くの人が不要だと思うものに「幸」を見いだし、創造力を限界まで駆使すれば、人は絶望しないで生き延びられる。僕は、路上生活者たちから学んだそうした暮らしを、「都市型狩猟採集生活」と名付けました。
それは、「都市に寄生する」ということとは違うのでしょうか?
![]() 僕はむしろ、そう言う人たちに逆に問いたいんです。「じゃあ、あなたたちは都市に寄生していないんですか?」と。
僕はむしろ、そう言う人たちに逆に問いたいんです。「じゃあ、あなたたちは都市に寄生していないんですか?」と。
例えば、僕は妻と二歳半になる子どもと3人暮らしですが、家族全員でお風呂だけでも一日160リットルの水を使っています。隅田川で路上生活をしている鈴木さんの場合、一日に使う水の量を合わせても40リットルです。公園の水道をタダで使わせてもらっているのは悪いかも知れないけれど、金を払って無駄に水を使用するのと、金を払わずに必要最小限の水だけを使って生きるのと、果たしてどちらが問題なんでしょうか?
金持ちが土地を占有して、投機目的のマンションを次々と建設することに疑問を持たずに、そうでない路上生活者が、誰も欲していない土地をタダで借りることに文句を言う。それって、おかしくないですか?
僕が29,000円の家賃も払えずにいた時、知り合いのおばさんが応援してくれて、「頑張ってよ」と食べ物をくれました。それって、あたりまえのことだと思うし、すべてが貨幣中心で回る世の中の方がおかしい、と思います。
僕が考える経済というのは、先人たちが僕に贈与したものを、僕がまた別の人に贈与する。贈与するのはお金ではなく、文化です。そういう「ギブ&ギブ&ギブ」の経済こそ自然だと思う。僕が路上生活者に興味を持ったのは、彼らがそういう原始的な経済の中で生き延びている先人だ、と思ったからです。
水も空気も土地も、生きていくために必要なものはすべて社会共通の資本です。だったら、お金を払わなければそれらが手に入れられない状況があるのはおかしい。
仮に、1人の人間が生きていくために70リットルの水が必要だとすれば、その70リットル分までは無料にして、それ以上は有料にすればいいじゃないですか。そうすれば、無駄に水を使う人はほとんどいなくなるはずです。社会共通の資本であるインフラに値段をつけるから、「お金を払ったんだからいくらでも自由に使っていいんだ」という、おかしな発想が生まれるんです。
社会通念上の「働く」ことに疑問を感じつつ、坂口さん御自身はこれまで、
どうやって生き延びていきたのでしょうか?
![]() 僕にとっての生き延びるための術は、芸術です。僕は今、海外でアーティストとして活動をしているんですが、そのきっかけは2006年、カナダのバンクーバーにあるギャラリーの展覧会に出品したことでした。
僕にとっての生き延びるための術は、芸術です。僕は今、海外でアーティストとして活動をしているんですが、そのきっかけは2006年、カナダのバンクーバーにあるギャラリーの展覧会に出品したことでした。
海外には、寄付金だけで運営している非営利のギャラリーがけっこうあります。そのなかで、僕に興味を持ってくれた人たちがいて、そこにタダで作品を送るんです。そこには僕なりの作戦があります。非営利である彼らは年に一度、次の年の運営費を獲得するためにコレクターたちを集め、チャリティーオークションを開催します。そこで僕の絵が売れる。もちろん、僕には一円も入らないけれど、オークションを通じて世界中のコレクターと関係を結ぶことができる。
絵を買った人がいれば、キャラリストから、その人の住所や連絡先、性格、どういう仕事している人なのか、などのインフォメーションをもらいます。そしたら、僕はその人たちに連絡をとって会いに行く。そして、今度は絵を彼らに直接売るんです。A1サイズのドローイングで一枚50万円で売っています。僕と妻と二歳半の娘が一ヵ月間、生きていける金額が約25万円ですから、50万円はちょうどその二ヵ月分です。つまり、タダで絵を提供するだけで、欧米のお金持ちと交渉するきっかけを作る。これが、僕にとっての「狩猟採集生活」でもあります。
アルバイトをした経験はありますか?
![]() ありますよ。ホテルのラウンジボーイ、とか。「労働」はしたくなかったので、「これはおれのアートワークだ」と思ってやっていました。
ありますよ。ホテルのラウンジボーイ、とか。「労働」はしたくなかったので、「これはおれのアートワークだ」と思ってやっていました。
僕、英語はそれほど流ちょうじゃないんですけれど、相手を笑わせるジョークを言うのは得意なんです。だから、ホテルに住んでいるようなVIPの客にも気に入られる。「君、何やっているの?」って聞かれたから、「こういう本、書いてます」って言ったら、その日のうちに本を100冊買ってくれたお客さんもいました。
僕にとっては、一発逆転する以外、方法がなかったんですよ。中途半端に就職して出世するアイディアは、まったくなかった。
僕は労働の「対価」をもらって生きていこう、とは思っていません。作家として本も書いていますが、原稿料や印税で稼ごうという気持ちは、さらさらない。著作権もいらない、と思っています。それよりも、「0円で生きる」という態度を貫いて、智恵もお金も、それを持っている先人たちからさずけてもらえばいい、と思っています。
僕にとっては、「お金がありすぎる人」と「お金がなさすぎる路上生活者」はまったく同じ。いずれも、僕が「すごいなあ」と思うことを実践して生きている人たちだ、という感覚しかありません。僕は、そういう人たちのところに訪ねていって、「どうすればそんなことができるのか教えて下さい」と聞いているだけ、なんです。
坂口さんの親世代はおそらく、いい大学に入って、いい会社に入って、マイホームを持つことを夢見て働いてきたと思います。坂口さんのお話をうかがっていると、そうした生き方に対する強烈なアンチテーゼを感じます。
![]() だって、そうやって生きてきて、幸せになった人っていないじゃないですか?僕は今、路上生活者じゃない普通に働いている人にインタビューしていますけれど、みんな、すごく困っていますよ。
だって、そうやって生きてきて、幸せになった人っていないじゃないですか?僕は今、路上生活者じゃない普通に働いている人にインタビューしていますけれど、みんな、すごく困っていますよ。
おやじに言われたこと、あるんですよ。「お前なら、超エリートのサラリーマンになれるよ」って。僕は、それに対して「じゃあ、おやじはそれ、実現したことあるの?」と聞きました。そしたら、おやじは「ない」と。「じゃあ、ほんとうのところはわからないんだね」って言ったら、おやじは正直だから「わからない」って言いましたよ。
僕は、「実現したことがある人」の言葉しか信じないんです。イデオロギーで動いている訳ではなくて、ただひたすら、そういう人たちの言葉を信じて、実行している。だから、僕自身に軸があるとすれば、それは「先人たちを信じる」という以外、ありません。
モデルはたくさんいます。高校時代はつげ義春や森山大道、建築家の石山修武にも衝撃を受けました。南方熊楠やガンジー、マザーテレサにもなりたい。憧れの人が見つかったら、完全に同一化するまで実行します。
普通のサラリーマンだったおやじの生き方は、かなり反面教師にはなっていますが、同時に僕はおやじに「自分の夢を信じて、仕事を徹底してやり続ければ、どんなことだってできる」ということを自分が体験することで伝えたいと思っているんですよ。しかも、僕が小学生の時に「建築家になれ」と言ってくれたのはおやじだったんです。つまり、彼は直感で言ったのだろうけど、それが完璧な教育になっていた。僕がやりたいと思っていることは、親世代に対するアンチテーゼではなく、マイホームなんて建てられても嬉しくはないけど、あなたたちから得たインスピレーションはとてつもなくかけがえないものだったと伝えたいんです。
バックナンバー
過去に掲載されたバックナンバーをご覧いただけます。
お問い合わせ[お客様サービスセンター]


- ※電話番号のお掛け間違いにご注意ください。
- ※自動音声でご案内後、担当者におつなぎします。
- ※休み明けは電話が混み合うことがございます。ご迷惑をおかけしますが、ご了承ください。



















