- こくみん共済 coop の公式ホームページ
- あんしんのタネ
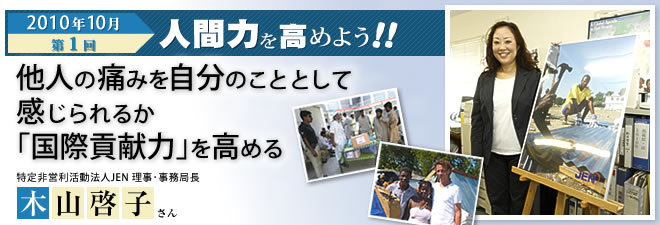
現代の社会を、より良くそして健やかに生き抜いていくために、私たちは、人間の持つさまざまな「力」を体得し高めていく必要があります。
「生きる意味を見つけること」「コミュニティーの一員として自分に何ができるかを考えること」「現実をクールに分析・理解すること」「自分に尊厳を持つこと」等々 ─ ─。そうした一つひとつの「人間力」こそが、私たちの人生を豊かで実りの多いものに導いてくれるはずです。
今回のテーマは「国際貢献力を高める」。紛争や自然災害で、厳しい生活を余儀なくされている人々を助けたい ─ ─。そう思う人は大勢います。熱い気持ちを「成果」に結びつけるためには、どのような心構えが必要なのでしょうか。また、ふだんの生活の中に、国際貢献につながるヒントはないのでしょうか。
シリーズの1回目は、NPO法人「JEN(ジェン)」の理事・事務局長、木山啓子さんに登場していただきました。国際支援の現場で学んだこと・考えたことをベースに、真の「国際貢献力とは何か」について語っていただきます。
自立を目指した支援プロジェクトこそが基本
JENはこれまで、旧ユーゴスラビア地域の難民支援や
アフガニスタン帰還民の支援、イラク復興など、国際的にさまざまな
支援活動をされています。まずは、組織の体制について教えて下さい。
![]() JENのスタッフは、本部で採用している「国際スタッフ」(約25人)と現地事務所で採用する「現地スタッフ」(約100人)を中心に構成されています。そこに随時、インターンの方や「サポーター」とお呼びしているボランティアスタッフやアルバイトの方々が加わる形です。
JENのスタッフは、本部で採用している「国際スタッフ」(約25人)と現地事務所で採用する「現地スタッフ」(約100人)を中心に構成されています。そこに随時、インターンの方や「サポーター」とお呼びしているボランティアスタッフやアルバイトの方々が加わる形です。
国際スタッフは原則、いついかなる時でも支援の現場へ駆けつける、つまり、海外転勤を伴うことが前提となります。資金調達などのようにおもに国内で活動するスタッフでさえも出動することもあります。
紛争であれば、日頃から注意深く情報を集めることで、ある程度「この地域が危ない」と予想することはできますが、自然災害の場合は、いつ起こるか予想もつきません。いつでも出られるよう、パスポートなどの出来る準備と「心の準備」だけはしておきます。
インド、パキスタン、中国の国境にある山岳地帯、カシミール地方で地震が起きた時、その第一報は、隣国アフガニスタンのカブール事務所にいたスタッフから入りました。「相当大きい地震のようだが支援しなくていいか」という連絡を受け、調べてみると被害も大きい。日本の新聞やテレビではまだ、大きなニュースにはなっていませんでしたが、現地からの連絡で、わたしたちはすぐにカブールと東京から一人ずつ、スタッフを現地へ派遣することができました。
スタッフを派遣する際、多くの場合は、どこかで活動している人を「引きはがして」派遣することになります。インド洋沖津波の際は、発生が12月26日で、年末に日本に帰国する予定でいたヨルダンのスタッフとわたしが急遽、現地入りしました。
インターネットが発達したおかげで、海外の情報を集めるのは随分と楽になりました。派遣されるスタッフは急な出発準備に追われるので、残るスタッフはインターネットや人脈などを駆使して必死で資料をかき集めて渡し、「あとはお願い」と送り出しています。
支援すると決める際の判断基準はあるのでしょうか?
![]() 信頼できる通訳が確保でき、十分なニーズ調査ができる状態かどうか、そして適切な支援を出来る行動の自由が確保されているか、を重視します。国や地域によっては、災害支援であっても住民が外国人と接触するのを嫌がったり、治安が悪すぎたり、と活動にさまざまな制約を受けることがあります。制約が大きく、自立に向けた十分なサポートができないと判断した場合は、あえて出動しないこともあります。
信頼できる通訳が確保でき、十分なニーズ調査ができる状態かどうか、そして適切な支援を出来る行動の自由が確保されているか、を重視します。国や地域によっては、災害支援であっても住民が外国人と接触するのを嫌がったり、治安が悪すぎたり、と活動にさまざまな制約を受けることがあります。制約が大きく、自立に向けた十分なサポートができないと判断した場合は、あえて出動しないこともあります。
緊急だから、とにかく物資を配る。あるいは、トラックの上からそれを放り投げる。わたしたちは、こうした支援の方法は好ましいとは思いません。緊急支援においては、物資の種類も量も、配布される地域も「モレまくり」「ダブリまくり」です。幹線道路沿いには支援物資が溢れているのに、少し離れた場所にはまったく物資が届いていないということもよくあります。
報道機関が集まる目立つ場所で活動したいという気持ちは、わたしたちにも理解できます。活動を知っていただかないと資金が集まらず、資金がないと活動を続けられないからです。しかし、そうした場当たり的な援助を続けていると、力の強い者だけが物資を独占し、自立どころか、依存を高めるだけの結果に終わらないとも限りません。こうしたことは、最も避けたいことだと考えています。わたしたちは、支援事業が完了した後の現地の人々の暮らしにこそ責任を持つべきなのです。
最近支援活動に入ったハイチでは、これまで20年間もの間、ずっと食糧支援のプロジェクトが続けられていたと聞きました。20年間も食糧を配り続ける間には、食物のタネを配ったり、スキやクワを配って耕作指導をしたり、ということをできたのではないでしょうか。JENのスタッフはみな、憤っています。
長期間の援助活動に依存してしまうと、自立したいという意欲や自立しようという気持ちをくじいてしまい、いつまで経っても援助を終えることができません。紛争や災害の現場では、時間の経過とともにニーズが刻々と変化します。ひとまず命の危険性を回避したら、次は住宅再建や心のケア、教育、続いて職業訓練という風に、自立に向けたプロジェクトをニーズに合わせて次々と立ち上げていくことでより効果が上がると考えています。そのためには、最初から「自立」を念頭に置いた十分なニーズ調査が欠かせません。そうして初期段階から自立に向けた支援活動を計画することで、復興はよりスムーズに進みます。
支援活動の成功は「一日も早く撤退できる状態にすること」です。これを、一般的なビジネス活動と同様に、最小限の費用と期間で最大の効果を上げるにはどうしたらいいかを、いつも考えながら活動しています。
自立を早めるには、物資以外に何が必要でしょうか?
-

-
2010年7月25日~8月2日にかけて
大洪水に見舞われたパキスタン北西辺境州。
被害は死者1600人以上、被災者1700万人以上と
言われている。 -

-
パキスタンの大洪水の被災者に
生活支援物資を配布するJENのスタッフ。
![]() 紛争や災害で、ただでさえ厳しい暮らしを強いられている上に、復興してゆくのは並大抵ではありません。ですから、みなで支え合える環境を作っていくことが必要不可欠だと思います。
紛争や災害で、ただでさえ厳しい暮らしを強いられている上に、復興してゆくのは並大抵ではありません。ですから、みなで支え合える環境を作っていくことが必要不可欠だと思います。
カシミールでの地震で多くの集落が破壊された時、わたしたちはあえて、物資を配布する家族のリストを現地の各集落の住民に作ってもらいました。そうすることで、自分たちで生存者を確認することになり、コミュニティーの再生が早まるだろう、と考えたのです。
リストに不正がないよう、内容を厳しくチェックもしました。緊急時でも、というより緊急時だからこそ「適切な仕事をしたら支援してもらえる」「ルールを守れば、約束も守ってもらえる」ということをわたしたちが行動で示すことを重視したのです。地震は彼らの元々の価値観まで破壊してはいないという安心感を取り戻して欲しかったからです。
「自立支援」で難しいのは撤退のタイミングです。わたしたちも人間ですから、頼りにされれば嬉しいですし、いつまでも支援していたいという気持ちにもなります。しかしそれは、いい結果をもたらしません。「信頼していたのに裏切られた」「この先、あなたたちがいなくなってどうやって生きていったらいいのか」とすがられたとしても、そこは支援のプロとして冷静に判断し、撤退します。
慣れないスタッフは、難民キャンプで現地の子どもたちと仲良くなり、別れがたくなることもあります。気持ちはわかりますが、「自分たちは支援のプロなのだから」と注意します。支援の目的は「自立」であり、「撤退」がゴール。それを忘れては良い支援が出来ません。
異なる意見に耳を傾けること。それが国際貢献への第一歩
「人の役に立つ仕事がしたい」「国際貢献したい」という若い人が増えています。
企業で働くことが「人の役に立っている」と実感できない時代の裏返しなのだろうか、
とも感じます。企業での勤務経験もある木山さんにとって、企業のなかで働くことと、
国際支援の現場で働くことの違いは何でしょう?
![]() 違いは、ほとんどありません。強いて違いを探すと、NGOやNPOでは「金銭的利益を追求」しないので、頻繁に「理念に忠実に」と意識している、ということだと思います。
違いは、ほとんどありません。強いて違いを探すと、NGOやNPOでは「金銭的利益を追求」しないので、頻繁に「理念に忠実に」と意識している、ということだと思います。
NPO・NGOといえども、良質な活動を続けていくためには、適切な組織運営や資金調達は重要です。企業の方も、利益を追いかけるだけではなく、理念が大事だ、と広く認識されています。とすれば、二つの違いは利益を分配するかどうか、だけ。企業が利益優先に走ることがあるとすれば、それは、分配の誘惑が大きすぎるからだろう、と思います。
国際貢献は、わざわざ現地へ赴かなくても、自分が今いる場所で十分にできるものです。JENでは、「知ること、行動すること、継続すること、忘れないこと、伝えること」を5つのお願いとして掲げていますが、そのどれもが国際貢献につながる行為です。
94年に初めて旧ユーゴスラビアの支援活動に参加して以来、「なぜ、戦争や争いごとがなくならないのか」を考え続けてきました。紛争の現場に行くたびに、現地の人たちに何千回その質問をしたかわかりません。そうして見えてきたのは、「自分が一番正しい」と思い込み、その価値観を相手に押しつけようとすることから争いが始まる、という単純な事実でした。
わたしたちが支援に入ったブコバルは、旧ユーゴの中でもサラエボと並ぶ戦闘が激しい地域でした。当時はセルビア人の占領地域で、セルビア人は「ここはもともと自分たちの土地だった」と主張していました。ところが、クロアチア人の難民に言わせると、「いやいや、70年前は自分たちの土地だった」ということになり、その疑問を再びセルビア人にぶつけると、「だけど、200年前はセルビア人の土地だった」となる。どこまでいっても意見がまじわることがなく、きりがないのです。
考えてみれば、似たような場面はわたしたちの生活の中にもあります。意見がどうしても一致しない時、相手を武力で屈服させようとするのが戦争です。そのことを痛感して以来、わたしは「戦争は日々の暮らしの中にあり、わたしたちの心の中にある」と考えるようになりました。
国際貢献をしたいと思うのであれば、まずは、異なる意見の人の話に耳を傾けることから始めてください。ただ聞くだけではなくて、自分の中にいったんその意見を取り込んで消化し、その上で、自分はこうだと意見を言う。一人ひとりがそれを心がけるだけで、世界は少しずつ変わっていくと思います。
若い頃と経験を積んだ今で、木山さんの何が大きく変わりましたか?
![]() それは、自己肯定力です。支援活動を通してというよりも、中国古典の先生に言われたひとことが、大きかったと思います。
それは、自己肯定力です。支援活動を通してというよりも、中国古典の先生に言われたひとことが、大きかったと思います。
電機メーカーに就職し、「女性だから昇進できない」という慣習が不適切だということを伝えたいのに、説得力をもって話すことが出来ず落ち込みました。説得力を持って話せる力を持ちたいと海外留学した頃は、いつも「自分はなんてダメなんだ」とばかり思っていました。くだらないことですが、「朝、ちゃんと起きられない(だから自分はダメだ)」「部屋が散らかっている(こんなんじゃダメだ)」という風に、すべてが自己否定の材料になっていたのです。
国際支援の現場に行くと、厳しい状況に置かれている難民の方たちが、「身体に気をつけてね」「スタッフの人たちも疲れているんじゃないの?」と心配してくださる。「日本にいるあなたの家族が元気でいるよう祈っているわ」と声をかけてくださる方もいました。なんて素晴らしい人たちなのだろうと思うと、それがまたプレッシャーになり「それに比べて自分は……」と落ち込むことも多かったのです。
そんなある日のこと、習い始めた中国古典の先生に、こう言われました。「そんなあなたも生きているだけで満点なんですよ」と。「でも先生、わたしは、これもあれもできないダメな人間なんです」と、できないことをいくつ並べても「そんなあなたも、生きているだけで満点なんです」と。ああそうか、とすごくほっとして、心がとても柔らかくなりました。
心が柔らかくなると、人ははじめて冷静になれると思います。「自分はダメだと思っていたけれど、その状況を変えるためにできることはすべてやったか」と考え始め、何もやっていないじゃないか、と気づきました。今では、「自分はダメ」ということを、何もやらない言い訳に使っていたのかもしれないとすら思います。「ダメだ」と落ち込む暇があったら、何か一つでもできることをやればいいんだ、と思えるようになり、人生が大きく変わり、すっかり楽しくなりました。
人は誰しも非難されるのが怖いし、褒められたい。そのために、誰もが大なり小なり殻を被っていると思います。けれども、その殻が厚すぎると、肥大化した自我に押しつぶされて自分自身がどんどん苦しくなっていく。わたしにとって、その殻を柔らかくしてくれたのが、先生の言葉でした。殻が少しだけ柔らかくなった分、外部との見えない交流が盛んになっていった気がします。
大切なのは「他人の痛みを感じ取る力」を養うこと
支援活動を続けていく上で、木山さんにとって最も重要なことは何でしょう?
![]() 自立を支えることです。そのためには、他人の痛みを自分のことのように感じられるかどうか、だと思います。旧ユーゴ滞在中、チェチェン紛争の激化により、大量の難民が発生したことがありました。その支援のため、わたしもチェチェンに向かったのですが、その時にふと、「この仕事を続けていく限り、世界中、どこへ行っても悲しい人に出会い続けることになる。そんな仕事を続けられるだろうか」と考え、つらくなったことがありました。
自立を支えることです。そのためには、他人の痛みを自分のことのように感じられるかどうか、だと思います。旧ユーゴ滞在中、チェチェン紛争の激化により、大量の難民が発生したことがありました。その支援のため、わたしもチェチェンに向かったのですが、その時にふと、「この仕事を続けていく限り、世界中、どこへ行っても悲しい人に出会い続けることになる。そんな仕事を続けられるだろうか」と考え、つらくなったことがありました。
もちろん、一番苦しいのは被害を受けた方々で、その方たちの悲しみに比べたら、わたしの感じるつらさなど、全く取るに足らないものです。それでも、自分としては苦しいものですから、ひとしきり悩みもしました。
出した結論は、「この人たちの痛みを悲しいと感じられるから、自分は支援を続けられるのではないか」ということでした。
人々の悲しみを見て痛みを感じないようになったら、いい仕事が出来ないのではないかと思っています。今でも、どんな現場に行っても、感情が「慣れる」「麻痺する」ということはないようです。
恥ずかしい話ですが、この仕事を始めるまで、水道のありがたみというものを意識したことはありませんでした。暑くてのどが渇いたら、蛇口をひねれば水が出る。それは、あたりまえのことだと受け止めていたのです。
被災地や発展途上国に行けば、そんなあたりまえのことさえ手に入りません。わたしはこの仕事を通じて初めて「のどの渇き」がいかに辛いことか、を知りました。どんなに多く紛争や災害のニュースに触れても、被災者という大きなくくりで考えているうちは、そういう具体的なことまでなかなかイメージできません。痛みをわがことのように感じるには、被災者という大きなくくりではなくて、個人に焦点を移して考える必要があるのかも知れません。
手前味噌になりますが、JENのホームページではあえて、大げさな被災の状況だけではなく、「顔がみえる○○さん」のニュースを流すように心がけています。被災者は、わたしたちと何ら変わりがない人間です。怒られれば萎縮し、褒められれば嬉しい。そんな同じ一人の人間が、家族に十分な食べ物を与えたいと願いながら、現実には、満足に水も飲めない状況にいるのだと思うと、痛みの感じ方が少し違うのではないか、と思います。
あたりまえのようにわたしたちが水を口にできるのも、水道管を作り、それを敷設した人たちの力があってこそ、です。そう思うと、ふつうに水を飲み、飲める水でシャワーを浴びられることさえ、感動的です。
多くの人たちの支えがあり、自分はその絆によって生かされていると感じられれば、人は絶望できないと思います。180度違う意見の人とも心を開いて話し合うことができるはず。そういう意味で、より良い支援活動をするためにはまず、自分自身が感謝の心を持ち続け、幸せでいることが大事だと、今は思っています。
※活動現場の写真は、JENホームページより転載。
バックナンバー
過去に掲載されたバックナンバーをご覧いただけます。
お問い合わせ[お客様サービスセンター]


- ※電話番号のお掛け間違いにご注意ください。
- ※自動音声でご案内後、担当者におつなぎします。
- ※休み明けは電話が混み合うことがございます。ご迷惑をおかけしますが、ご了承ください。


















