- こくみん共済 coop の公式ホームページ
- あんしんのタネ
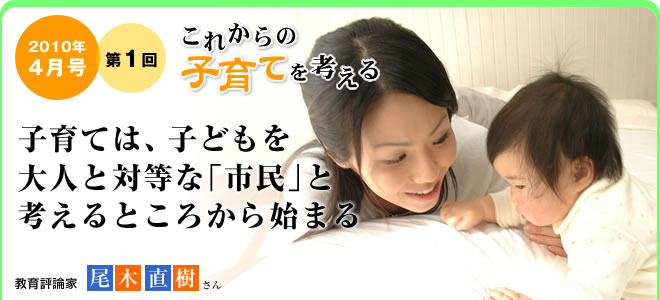
子どもたちの幸せな明日を作り出すことをめざす新シリーズ「これからの子育を考える」。その第1回として、教育評論家の尾木 直樹(おぎ なおき)さんのインタビューをお送ります。尾木さんは大学卒業後、私立高校、公立中学校教師を経て、教育評論家・大学教授として、子ども第一の心の通う教育を求め、現場に密着した調査・研究、講演、評論活動を展開しています。今回は、子育てと子ども教育をめぐる問題を俯瞰的にお話いただき、解決への提言をお聞きしました。
成績という数値目標だけにとらわれ、子育てモデル不在の日本
教育評論家の立場から見て、現在の子育ての問題点はどこにあるとお考えですか。

![]() 現在の子育ての問題点は、親に「どういう子どもに育てるか」という人格形成のイメージができていないことです。「テストでよい成績をとる」「一流大学に入る」など目標を数値で表せるものは誰の目にも見えやすいので、多くの人が同意します。東大合格のための様々な受験テクニックや勉強法が盛り込まれて、評判になった漫画『ドラゴン桜』のように、大手進学塾から中高一貫校を経て、東大法学部に入学するという子育てモデルは多くの親に人気があります。そういう人がいてもよいのですが、東大法学部の定員は現在1学年400人です。そうすると、圧倒的多数の人は東大法学部には入れないわけで、そのモデルとは異なった生き方をするわけです。そうした大多数の人のモデルを国の政策のレベルでも、市民のレベルでも、学校の教師も持てていないのです。
現在の子育ての問題点は、親に「どういう子どもに育てるか」という人格形成のイメージができていないことです。「テストでよい成績をとる」「一流大学に入る」など目標を数値で表せるものは誰の目にも見えやすいので、多くの人が同意します。東大合格のための様々な受験テクニックや勉強法が盛り込まれて、評判になった漫画『ドラゴン桜』のように、大手進学塾から中高一貫校を経て、東大法学部に入学するという子育てモデルは多くの親に人気があります。そういう人がいてもよいのですが、東大法学部の定員は現在1学年400人です。そうすると、圧倒的多数の人は東大法学部には入れないわけで、そのモデルとは異なった生き方をするわけです。そうした大多数の人のモデルを国の政策のレベルでも、市民のレベルでも、学校の教師も持てていないのです。
多くの親が生活費を削ってまで、
子どもの教育にお金をかけています。
![]() 親もどうしていいか分からないので、成績を上げるという分かりやすいやり方になびいてしまいます。そこで、塾や習い事から始まって、お金をかける。学校の授業料も高等学校以上の場合、公立・私立を問わず、親が払わなければなりませんから、教育費の私費負担率は33%と世界最高レベルにまでなってしまっています。しかし、教育とは本来、国家的な大事業で、社会的な営みです。その大原則がおろそかにされ、「個人が自分の責任でお金を払って、子どもに受けさせるものだ」という意識が世の中の主流になってしまっているところに大きな問題があります。ですから、社会的な営みという原則をはっきりさせたうえで、社会の中で、教育をどう位置づけるかを考えなければなりません。
親もどうしていいか分からないので、成績を上げるという分かりやすいやり方になびいてしまいます。そこで、塾や習い事から始まって、お金をかける。学校の授業料も高等学校以上の場合、公立・私立を問わず、親が払わなければなりませんから、教育費の私費負担率は33%と世界最高レベルにまでなってしまっています。しかし、教育とは本来、国家的な大事業で、社会的な営みです。その大原則がおろそかにされ、「個人が自分の責任でお金を払って、子どもに受けさせるものだ」という意識が世の中の主流になってしまっているところに大きな問題があります。ですから、社会的な営みという原則をはっきりさせたうえで、社会の中で、教育をどう位置づけるかを考えなければなりません。
現在、社会における教育を考えるときに、指針になるのがOECD(経済開発協力機構)の考え方です。OECDは今日の世界を、(1)知識基盤社会、(2)リスク・格差社会、(3)成熟した市民社会、(4)多文化共生社会、の4つに特徴づけています。そして、教育の目標は、そこから生まれる様々な問題を解決していくことができる人材を育てることであるとして、学力の定義もそこから導き出しています。
ところが日本ではそうした考え方は受け入れられておらず、たとえば「漢字や英語の検定に合格することが学力向上だ」と多くの人が信じています。そんな状態の問題点を文科省も少しは気がついているところがあり、全国一斉学力テストでも「新しい知識や情報が社会の全ての活動の基盤として重要性を増す知識基盤社会に入っているので、知識を活用する学力の育成が必要だ」と、知識力を問う旧来タイプの問題(A)と併せて、知識を活用する新しいタイプの問題(B)を出題しています。しかしこの中でも、OECDがいう4つ目の特徴である、多くの民族や文化が共存する多文化共生社会の観点は全く視野に入っていません。
先日、スウェーデンを訪れたら、7年前に行ったときと比べて、人口が200万人も増えていました。増えたのはほとんどが移民で、今スウェーデンには100カ国近い国から来た人が住んでいるといいます。それで文部省の課長に「生活習慣や文化も違い、大変ですね」と日本人の感覚丸出しで聞いたら、「いや、ありがたい、すばらしいことです。100カ国の人がいながらにして、スウェーデンの文化を体得してくれる。私たちもいながらにして、100カ国の文化に接することができるのです」というのです。多文化共生を名実共に実践している、その姿を見て、思わず「負けた」と思いました。
大人と対等な「子ども市民」ととらえて、社会との関係を築く
大人は子どもをどのようにとらえればよいのでしょうか。

![]() 日本では子どもは成人に向かう発達途中の状態というとらえ方が圧倒的です。ですから、教師も含めて大人は子どもたちを下に見て、上位下達で色々なことを教え、学力を注入して、競わせるわけです。それに対して、ヨーロッパでは大人と対等な子ども市民、今このときを一緒に生きている仲間だという考え方に立っています。
日本では子どもは成人に向かう発達途中の状態というとらえ方が圧倒的です。ですから、教師も含めて大人は子どもたちを下に見て、上位下達で色々なことを教え、学力を注入して、競わせるわけです。それに対して、ヨーロッパでは大人と対等な子ども市民、今このときを一緒に生きている仲間だという考え方に立っています。
たとえば、オランダでは子どもたちは重要な議題に対する承認権と勧告権を持っていて、授業の時間割を決める際には、子どもたちの承認を受けなければなりません。また、ノルウェーでは道路行政にまで参加して、子どもが遊ぶ場所は地図に色を塗り、そこを外して道路を作ります。デンマークでは学校運営の評議会があり、小学校でも13人のうち7人が子どもで構成されています。そして、大人たちと同じ1票の表決権を持っているので、子どもたちが反対すれば、提案は通りません。私は以前、「子どもがわがままになりませんか」と、わざと日本人を代表するような感覚で尋ねたことがあります。そうしたら、「子どもは徹底して責任を感じるから、大丈夫です」という答えが返ってきました。
このようなやり方をすることで、子どもは大人が自分たちのいうことを聞いてくれると大人を信頼するし、学校などの教育機関や地方自治体などの行政に対する信頼も生まれます。そして、その過程を通して、モラルが形成され、子どもと大人、子どもと社会の相互信頼にもとづいた豊かな関係が作られていくのです。
社会や国にとって、子どもはどのような意味を持つ存在なのでしょうか。
![]() ヨーロッパでは、子どもは「未来からやってきた宝物」、あるいは「未来からの使者」といわれます。10年後、20年後の社会は今の子どもたちが担うわけですから、国が発展していくには、子どもたちが十分な教育を受けて、OECDがいう現代社会がかかえる諸問題を解決する力を身につける必要があります。その意味で、教育は国のライフラインです。一方で、海外で活動したり、外国から来た人と一緒に仕事をしたりすることも当たり前になっているわけですから、誰もが知識を生かして物事の本質を見抜いて、様々な問題を解決できる力を持たなければなりません。そして、それを保障するのが教育です。ですから、教育はこれからの社会を生きていくためのセーフティネットであり、人生前半における社会保障だということができます。
ヨーロッパでは、子どもは「未来からやってきた宝物」、あるいは「未来からの使者」といわれます。10年後、20年後の社会は今の子どもたちが担うわけですから、国が発展していくには、子どもたちが十分な教育を受けて、OECDがいう現代社会がかかえる諸問題を解決する力を身につける必要があります。その意味で、教育は国のライフラインです。一方で、海外で活動したり、外国から来た人と一緒に仕事をしたりすることも当たり前になっているわけですから、誰もが知識を生かして物事の本質を見抜いて、様々な問題を解決できる力を持たなければなりません。そして、それを保障するのが教育です。ですから、教育はこれからの社会を生きていくためのセーフティネットであり、人生前半における社会保障だということができます。
そうした観点に立つと、教育は誰でもが無償で受けられるものでなければなりません。オランダは今から97年前の1917年に憲法を改正して、授業料を一律で無償にしました。フィンランドは1994年の教育改革で、保育園から大学院までの授業料を無償にしました。日本ではすぐに財源をどうするかという議論になるのが実情ですが、教育をライフラインだと明確にしたうえで、予算を優先して確保し、私立も公立も各種学校もすべて無償化することが必要です。
孤独を感じる比率が飛び抜けて多い日本の子どもの危機
子どもの幸せとは何なのでしょうか。
![]() ユニセフが2007年に発表したOECD加盟24カ国の15歳の子どもたちの中で、「孤独を感じる」割合がどのくらいかという調査があります。ほとんどの国が5~6%程度という中で、ひとつだけ29.8%と異様なほど突出している国があります。ほかならない、日本です。2位のアイスランドの3倍、一番低いオランダの実に10倍です。
ユニセフが2007年に発表したOECD加盟24カ国の15歳の子どもたちの中で、「孤独を感じる」割合がどのくらいかという調査があります。ほとんどの国が5~6%程度という中で、ひとつだけ29.8%と異様なほど突出している国があります。ほかならない、日本です。2位のアイスランドの3倍、一番低いオランダの実に10倍です。
先日、オランダから研究者が来日したので、子どもの幸福度が世界一高い理由と孤独を感じる子どもが少ない理由を聞きました。そうしたら、「ワークシェアリングなので、親がいつも一緒にいてくれるから」という答えが返ってきました。両親は曜日をずらして休むし、午後6時になれば帰ってくる。つまり、子どもが幸せを感じる大前提、「日常的に親がそばにいる」ということです。
子どもが幸せを感じるには、そのほかに「学校の楽しさ」と「自分が認められ、誉められる」「居場所があること」が必要です。ところが日本では、子どもたちはお互いに競争させられ、多くの場合、学校でのテストの成績ですべてを見るという基準と同じ価値観を親たちが持っています。そうすると、テストで20点しか取れないと先生に怒られ、家でも親に怒られる。怒られる子どもにとって、学校は楽しさもなく、自分を認めてくれるところでもありません。家庭も同じで、誉められることもなければ、居場所もありません。その結果が鬱病、躁鬱病にかかる子どもの急増です。2007年に文科省の委託を受けて北海道大学の先生たちが調査をしたら、中学1年生で有病率10.7%という結果が出ました。中学3年生では20~30%になるかもしれません。こうした危機的な状態に対する懸念の声は以前から上がっており、1998年には国連が「日本の子どもたちが高度に競争的な教育制度のストレスの結果として、発達障害にさらされている」と改善を求める勧告を出しました。ところが政府はそれを無視したため、国連は2004年に再度の警告を出しましたが、全く改善されることなく、現在の深刻な事態が生み出されています。
世界に開かれた広い視野を持てば、立て直しは可能
お話を聞くと、「日本の常識は世界の非常識」という気がします。

![]() 「日本には資源がないので、人材を国力の源にしよう」として、日本は教育立国を進めてきたと、私も含めて皆が思い込んできました。実際、1970年代には日本の教育予算は世界の国の中でトップグループでした。その感覚からすれば、国が教育予算を減らし、教育をおろそかにしているとは誰も考えても見なかったのです。しかし、気がついたら、とんでもない危機的な状態になっていたのです。そんな状態になってしまったのは、日本がアメリカ流の経済至上主義的な教育理念を導入してしまったことにあります。アメリカにも進んでいる面はあります。しかし、日本はフィンランドやオランダなど教育に投資して立ち直ったヨーロッパの国々に目を向けなければいけないのに、アメリカ一辺倒で世界の動きが見えなくなってしまったのです。
「日本には資源がないので、人材を国力の源にしよう」として、日本は教育立国を進めてきたと、私も含めて皆が思い込んできました。実際、1970年代には日本の教育予算は世界の国の中でトップグループでした。その感覚からすれば、国が教育予算を減らし、教育をおろそかにしているとは誰も考えても見なかったのです。しかし、気がついたら、とんでもない危機的な状態になっていたのです。そんな状態になってしまったのは、日本がアメリカ流の経済至上主義的な教育理念を導入してしまったことにあります。アメリカにも進んでいる面はあります。しかし、日本はフィンランドやオランダなど教育に投資して立ち直ったヨーロッパの国々に目を向けなければいけないのに、アメリカ一辺倒で世界の動きが見えなくなってしまったのです。
どうしたら、この危機的な状態を変えることができるのでしょうか。
![]() フィンランドやオランダなど北欧諸国の例はとても参考になると思います。フィンランドは1994年、失業率20%という大変な経済的危機に直面して、「教育で国を立て直す」という戦略のもと、教育改革への取り組みを開始しました。そして、すべての子どもに平等な教育機会の保障と子どもたちの洞察力を豊かに育てる学力構造を開発し、最優先で教育に予算を回した結果、2000年には学力が世界一であることが証明され、経済的な競争力も世界トップになりました。そこから分かるように、まず大切なのは、日本ではほとんど実現していない「子どもの参加」を、学校・家庭、社会のあらゆる領域に拡大することです。そうすると、子どもたちは斬新なアイデアを提示して、大きな力を発揮してくれるようになると思います。そのために、必要なのは世界の人々と共生、協働できる力を持つ、たくましい子ども市民を育てることです。親が成績至上主義にふりまわされず、子ども市民を育てるために力を尽くすことで、日本の子どもたちはどの子も息を吹き返し、それに励まされて、社会全体が活力を取り戻すことができると確信しています。
フィンランドやオランダなど北欧諸国の例はとても参考になると思います。フィンランドは1994年、失業率20%という大変な経済的危機に直面して、「教育で国を立て直す」という戦略のもと、教育改革への取り組みを開始しました。そして、すべての子どもに平等な教育機会の保障と子どもたちの洞察力を豊かに育てる学力構造を開発し、最優先で教育に予算を回した結果、2000年には学力が世界一であることが証明され、経済的な競争力も世界トップになりました。そこから分かるように、まず大切なのは、日本ではほとんど実現していない「子どもの参加」を、学校・家庭、社会のあらゆる領域に拡大することです。そうすると、子どもたちは斬新なアイデアを提示して、大きな力を発揮してくれるようになると思います。そのために、必要なのは世界の人々と共生、協働できる力を持つ、たくましい子ども市民を育てることです。親が成績至上主義にふりまわされず、子ども市民を育てるために力を尽くすことで、日本の子どもたちはどの子も息を吹き返し、それに励まされて、社会全体が活力を取り戻すことができると確信しています。
尾木直樹さんより、素敵なプレゼントがございます。
バックナンバー
過去に掲載されたバックナンバーをご覧いただけます。
お問い合わせ[お客様サービスセンター]


- ※電話番号のお掛け間違いにご注意ください。
- ※自動音声でご案内後、担当者におつなぎします。
- ※休み明けは電話が混み合うことがございます。ご迷惑をおかけしますが、ご了承ください。















