- こくみん共済 coop の公式ホームページ
- あんしんのタネ
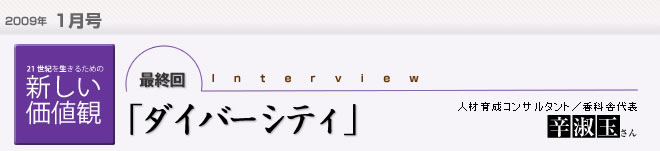
「ダイバーシティ」は日本語では「多様性」と訳されます。多くの企業が、近年、ダイバーシティの重要について語り始めていますが、なぜ企業や社会にとってダイバーシティが必要であり、それが実現することによってどんなメリットがあるかは、必ずしも明確にされていません。企業にとって、社会にとって、さらには私たち一人ひとりにとってのダイバーシティの意義を、人材コンサルタントの辛淑玉(シン・スゴ)さんが熱く、かつ、わかりやすく語ってくださいました。
ダイバーシティの根底にあるのは、生産性の問題
はじめに、ご自身で会社を立ち上げるに至った経緯についてお聞かせください。
 辛 私が在日朝鮮人で、企業への就職が難しかったというのがひとつの理由です。起業前は広告代理店に籍を置いていたのですが、あくまでも契約社員という立場でした。在日が企業社会で生きようと思ったら、自分で会社を興すのが一番の近道なんですよ。
辛 私が在日朝鮮人で、企業への就職が難しかったというのがひとつの理由です。起業前は広告代理店に籍を置いていたのですが、あくまでも契約社員という立場でした。在日が企業社会で生きようと思ったら、自分で会社を興すのが一番の近道なんですよ。
もうひとつもやはり似たような理由で、私は画一化した学校教育に常々疑問をもっていたのですが、日本国籍がないために日本の教育システムに関与できなかったわけです。そこで、企業内の社員教育だったら教育にも職場にも関わることができるので、一石二鳥だったのです。社員研修をビジネスにすれば、外国人である私も教育に関われるし、日本の企業の中にどんどん入っていくことができます。
在日って、日本人からはずっと見えない存在だったでしょう。だから、できるだけ目につくところで生きようと思ったんです。それが研修ビジネスの会社を立ち上げた理由です。
でも、最初の10年間は本当にたいへんでしたよ。私が「あちらの方(在日)」だからという理由で研修を拒否する人がいたりね。そういうことは往々にしてありました。もっとも、企業社会は合理的ですから、生産性の向上や売り上げの増加にこちらが貢献できれば、それで認めてもらえるわけです。そうやって、常に結果を出しながらここまでやってきました。
香科舎は「ダイバーシティ」をミッションに掲げています。「ダイバーシティ」という言葉が現在のように使われるようになったのはいつ頃ですか?
辛 アメリカでは、70年代の半ばくらいから使われています。「多様性」という意味ですが、日本語の「多様性」よりは、もう少し積極的で肯定的な語感があるように思います。
この言葉が使われるようになった背景には、産業構造の大きな変化があります。それまでの社会は、基本的に肉体労働によって生産性が上がる仕組みになっていました。肉体労働が得意なのは体力のある男ですから、男が生産の中心にいて、金を持ち、社会を握るという構造がずっと続いてきたわけです。
それが、70年代に知的労働が価値を生み出す社会に大きく変化しました。知的労働に男女の本質的な差はありません。体力などに関係なく、女も仕事ができるわけです。逆に企業にとっては、女を活用しなければ生産性が上がらなくなってくる。競争力を上げるためには、男一色の組織ではどうしようもない。
そのような国際社会の流れと産業社会の必要性が女性を社会に押し上げ、女の社員が増えていった。それが企業におけるダイバーシティの始まりです。
そこから、様々なダイバーシティの取り組みがスタートしたわけですね。
辛 重要なのは、ダイバーシティは「愛」とか「優しさ」みたいなものに基づいたものではなくて、企業や社会が生産性を上げるために何が必要かという観点から始まったものだという点です。
アメリカには、ダイバーシティを促すたくさんの法律があるのですが、その中で、例えば公的機関に納入する業者は、「障害者も同じように使えるものを生産している」ことが求められます。
これはちょっと極端な訳し方ですが、要するに、企業は社会の多様性を前提に、マイノリティも使えることを常に念頭において商品をつくらなければならないということです。
そのマイノリティには、障害者だけでなく、妊婦、少数民族、言語上の少数派、様々な病歴をもった人──つまり、何からの事情で不利益を受ける人たちすべてが含まれます。
そういう視点で商品を作ろうと思ったら、企業の側にマイノリティがいなければなりません。健常者の男だけが働いているような会社では、商品を開発することもできないし、利益を上げることもできないんです。社会を構成している様々な人が、企業の中にも同じようにいる。そういう状態があって初めて、社会に受け入れられる商品を販売できる。つまり、商売を合理的にやって利益を上げようと思ったら、企業内のダイバーシティがどうしても必要だということです。
それがなければマーケットから退場するほかないんですよ。これは、グローバルスタンダードを標榜する企業の常識となっている考え方です。
お仕事の中でクライアントにダイバーシティの考え方が受け入れられるようになったのは、いつ頃からですか?
辛 業種にもよりますが、ただ金儲けのみに走っている帝国主義的な企業はまだまだ多いですよ。
企業のダイバーシティの実現率は、おそらくまだ1割くらいではないでしょうか。
たしかに、ここまで来るにはかなりの時間がかかっていますが、これが2割か3割くらいまで広がっていけば、あとは一気に拡大していくと私は思っています。
経済状況が今とても悪いですよね。おそらくあと5年はよくならないでしょう。ここでどういう行動をとるかが経営者の分かれ道になると思います。今がチャンスと、ダイバーシティの実現によって難局を乗り切るか、それとも、過去の栄光にすがり、ごく少数の男たちの尻を叩いて会社を維持しようとするのか。
時代のニーズを読み間違え、儲けるためにエコカーを撤退させ、大型ガソリン車で勝負をし続けたアメリカのGMが破綻に瀕しているように、次々と破綻する企業が出てくることは間違いないでしょう。
「嫌いな奴」と一緒に生きていくために
ビジネスを離れて、「社会」というもう少し広い共同体の中で考えた場合のダイバーシティの意義については、どうお考えですか?
 辛 群馬県の大泉町をご存知ですか? ブラジルやペルーから働きに来た日系人が人口の1割を占めている町です。
辛 群馬県の大泉町をご存知ですか? ブラジルやペルーから働きに来た日系人が人口の1割を占めている町です。
そこでは、外国人が増えることによって、新しい文化や産業が生まれています。ブラジル料理の店とかね。(※)
それから、これは福島県のある町の話ですが、ずっとたばこ栽培が盛んだったのだけれど、たばこ産業全体が縮小したために、ほぼ全滅してしまったわけです。しかしそこには、お母ちゃんたちが、タバコ畑の隅で、せっせと小遣い稼ぎでやっていたかすみ草の栽培があったのです。
気がつくと、日本有数のかすみ草の産地になっていた。
当初、男たちは馬鹿にして見向きもしなかったのですが、女たちはせっせとかすみ草を作っていた。それが今、その町の経済を支えているわけです。
何が言いたいかというと、少数派、少数の意見、自分たちとは違う人たち──そういう存在があることによって、地域から新しいものが生まれ、それでその地域社会全体がよくなっていくということです。ダイバーシティにはものを生み出す力があり、それが社会の進歩や発展につながるわけです。ですから、ダイバーシティの実現は、社会全体の課題であると言えるんです。
それでは、私たち一人ひとりにとってのダイバーシティの意義とはどのようなものでしょうか?
辛 日本には、同調圧力の中で生きる苦しさがあります。いわゆる「世間の目」です。みんな同じことをしてないと排除されてしまう。
しかし、赤も、青も、黄色も、緑もといろいろあれば、あっ、この色でも、この個性でも、この私でもいいんだと思える。それが大事なのです。
自分の隣に違う人が生きていて、現実に顔を合わせてともに生きる。自分を豊かにするだけでなく、それが人間の幅の広さになることは間違いないですよ。
ダイバーシティとは、企業の課題であり、日本社会の課題であり、さらには、一人ひとりの生き方における課題でもあるということですね。
辛 そのとおりだと思います。国際化社会っていうでしょう。「国際化」ってどういう意味だと思います? 私は「嫌いな奴と一緒に生きていくこと」、それが国際化だと考えています。
人間誰だって、他人と全身全霊で仲良くなることなんかできないでしょう。たとえ夫婦だってそうですよ。
こいつには気に入らないところがある、むしろ大嫌いかもしれない。でも、そういう奴と一緒に働かなければならないし、一緒に生きていかなければならない。そして、何かあったら手を取り合って助け合わなければならない。それが国際化社会の基本的な考え方です。
では、気に入らない奴と一緒にやっていくためには何が必要か。相手を認めた上での調整力です。互いの距離感やズレをうまく調整しながら、暴力や戦争に訴えることなく、共生を実現させていく。結局のところ、ダイバーシティとはそういうことなんです。だから、国家レベルで考えれば、ダイバーシティとは一種の安全保障であると言ってもいいと思いますね。
誰もが悲しみを表現できる社会になってほしい
会社を始めた頃の目標やビジョンは達成できましたか?
 辛 ずっと達成し続けてきていると思います。当初に想定していたラインははるかに超えていますね。でもそれも、踏ん張って踏ん張ってやり続けてきたからだと思っています。人間、無我夢中でやらなければならない時期ってあるじゃないですか。その時期を越えると、自分でも驚くような力がついているものなんです。
辛 ずっと達成し続けてきていると思います。当初に想定していたラインははるかに超えていますね。でもそれも、踏ん張って踏ん張ってやり続けてきたからだと思っています。人間、無我夢中でやらなければならない時期ってあるじゃないですか。その時期を越えると、自分でも驚くような力がついているものなんです。
会社の経営で悩んだこと、嫌がらせを受けたこと、テレビの討論番組に出て叩かれたこと──そのすべてが力になっているし、無駄だったことはひとつもない。50を過ぎてそういうことがよくわかるようになりましたね(笑)。
これからの目標や夢はありますか?
辛 いろいろありますが、ひとつ挙げると、組織の中でヒューマニズムを醸成する仕組みを作ること。
パワハラ、セクハラ、モラハラなど、限りなく多くの暴力が組織の中では飛び交っています。相手への理解不足と、競争原理によって人々が分断されているのです。そういう状況を変えるために、「ライセンス制度」をどうやって築くか。つまり、いたわり合ったり、手を取り合ったものが評価される仕組みです。
問題が起きてから対処するのではなくて、人権感覚を広めていくことで問題が起きないようにする。向こう10年間で、その仕組みづくりに取り組んでいきたいと考えています。
最後に、辛さんにとっての理想の社会のイメージとは、どのようなものかお聞かせください。
辛 はっきりしていますね。「悲しみを表現できる社会」です。痛かったら痛い、辛かったら辛い、そう誰もが言える社会。失敗をしてもそれをなかったことなどにせず、許し合える社会。いろいろな悲しみが吐き出せる社会──。そういう社会が実現すれば、誰もが人の苦しみや悲しみがわかるようになるでしょう。そうすれば、みんなが心の底から笑えるようになると思うんです。本当の笑顔は、本当の悲しみがわかる人だけが持てるものですから。
(※)大泉町経済課作成「統計調査結果概要」(2008年4月)によれば、大泉町住民全体42,113人中、外国籍住民は6,878人で、総人口に占める割合は16.3%にのぼる。
-

-
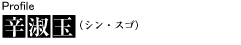
1959年、東京生まれ。博報堂の特別宣伝班を経て、85年、26歳の時に人材育成会社「香科舎(こうがしゃ)」を設立。ビジネスショーや万博などのパビリオン運営、人材育成、企業研修を手がける。会社経営のかたわら、大学、専門学校、ビジネススクール、企業、自治体などでの講義や、各種社会活動などにも積極的に取り組んでいる。近著に『その手に乗ってはいけない!』(ちいさいなかま社)がある。
バックナンバー
過去に掲載されたバックナンバーをご覧いただけます。
お問い合わせ[お客様サービスセンター]


- ※電話番号のお掛け間違いにご注意ください。
- ※自動音声でご案内後、担当者におつなぎします。
- ※休み明けは電話が混み合うことがございます。ご迷惑をおかけしますが、ご了承ください。













