- こくみん共済 coop の公式ホームページ
- あんしんのタネ
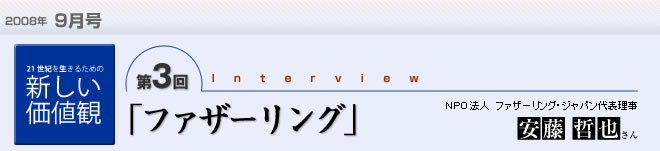
「ファザーリング」という聞き慣れない言葉を掲げたNPO法人ファザーリング・ジャパン。この団体を2006年に旗揚げしたのが安藤哲也さんです。「ファザーリング」という言葉にはどのような意味が込められているのでしょうか。また、その背景にはどのような考え方があるのでしょうか。「21世紀を生きるための新しい価値観」の第3回は、ファザーリング・ジャパン代表理事の安藤哲也さんに、「ファザーリング」という言葉の意味や、安藤さんが考える父親観などについてお話しいただきました。
父親であることを楽しむために
まずは、「ファザーリング」という言葉の意味について教えていただけますか
 安藤 「父親であることを楽しもう」といった意味の言葉です。父親ほど素晴らしい仕事はないんだよ、子育てをすることは義務ではなくて権利なんだよ、みんなで子育てを楽しもうよ──そんなメッセージを伝えるために考えた一種の造語ですね。英語には「マザーリング」という言葉はあるのですが、僕が調べた限りでは、「ファザーリング」という言葉は使われていないようです。
安藤 「父親であることを楽しもう」といった意味の言葉です。父親ほど素晴らしい仕事はないんだよ、子育てをすることは義務ではなくて権利なんだよ、みんなで子育てを楽しもうよ──そんなメッセージを伝えるために考えた一種の造語ですね。英語には「マザーリング」という言葉はあるのですが、僕が調べた限りでは、「ファザーリング」という言葉は使われていないようです。
僕は常々、日本語には父親の育児参画をポジティブに表現する言葉がないと感じていました。一般的には、「育児参加」とか「家族サービス」というわけですが、これって表現としておかしいですよね。そもそも育児という行為や家族という集団の中に父親は含まれているはずなのに、「参加」とか「サービス」というと、父親はどこか遠い離れたところにいて、時々育児や家事を手伝いにやってくるみたいなニュアンスになってしまう。だから、あえて「ファザーリング」というこれまでになかった言葉を使って、父親が育児をすることのポジティブな意味を際立たせているわけです。
ファザーリング・ジャパンを設立した経緯についてお聞かせください。
安藤 設立したのは2006年の11月で、僕はまだ会社勤めをしていました。その頃、父親支援事業をやっている人はほとんどいなくて、しかし一方には、育児や家庭のことで悩んでいる父親がとても多いという現実があったわけです。父親の育児に関する情報を発信していくことで、お父さんたちに笑顔が戻り、子供たちも笑顔で暮らせるようになるのではないか、そうなったら気持ちいいだろうなと、そのくらいの動機で設立したんです。とくに、使命感のようなものがあったわけではないんですよね。
もっとも、父親のあり方については、僕自身、父親になった10年前からずっと考えていました。最近になってようやく、父親としてどう生きればいいかが自分なりに何となく見えてきた。そう感じられるようになったので、 NPO設立に踏み切れたように思います。
収入の面では会社員時代の4分の1になりましたが、産まれて間もない赤ちゃんと一緒に過ごす時間も確保できるし、夕方には上の娘たちと事務所で話したりもできるし、今の方が断然ハッピーですね。
具体的にはどのような活動をしているのですか?
安藤 父親の子育てを支援する様々な事業をやっていますが、メインはセミナーやワークショップの開催です。企業や自治体などに呼ばれて講演することも最近は増えていますね。そういった活動を僕らは「地上戦」と呼んでいます(笑)。
一方、「空中戦」の方は、「パパ検定」を実施したり、インターネットでオリジナルの「おとうさんソング」を配信したりということをやっています。「パパ検定」は、正式には「子育てパパ力(ちから)検定」といって、試験を通じて父親であることの楽しさを知ってもらおうという趣旨で今年の3月から実施しているものです。1回目の今年は、下は19歳の学生から、上は75歳のおじいちゃんまで、全部で1040名の方々が参加してくれました。メディアも120社くらいが取材に来て、ロイターやAPなどの通信社も世界に向けて紹介してくれたんですよ。今後も毎年1回は開催していく予定です。
目標とすべき父親のモデルは存在しない
安藤さん自身が積極的に育児をしようと思ったきっかけは何だったのですか?
 安藤 最も強いモチベーションは、自分の父親のようにはなりたくないということでした。僕の父親は昭和3年生まれの国家公務員で、頭が固く、母親にいつも威張り散らしている男でした。家父長的で、男尊女卑で、僕は10代の頃から「絶対親父みたいな男にはならないぞ」と考えていました。
安藤 最も強いモチベーションは、自分の父親のようにはなりたくないということでした。僕の父親は昭和3年生まれの国家公務員で、頭が固く、母親にいつも威張り散らしている男でした。家父長的で、男尊女卑で、僕は10代の頃から「絶対親父みたいな男にはならないぞ」と考えていました。
しかし、そういう父親の元で育ったわけですから、僕自身、同じことをやってしまう可能性があるわけです。実際、結婚生活において妻と喧嘩になると、昔、親父がおふくろに対して振る舞っていたような態度をとってしまうことがありました。そして冷静になってからものすごい自己嫌悪に陥るわけです。だから僕は、「内なる父親」と闘って、強引にギアチェンジをして、何とか親父のようにならないように努力しました。積極的に育児を楽しもうと思ったのも、その一環ということです。
僕は父親の伝統的な役割を否定しているわけではないんです。家族を扶養したり、家族の衣食住に責任をもつということは当然しなければならない。しかし、だからといって育児をしなくてもいいということにはなりません。だって、出産と授乳以外のたいていのことは、男だってできるわけですから。
日本では、「父親が育児を楽しむ」という文化がこれまであまりなかったので、 モデルとすべき父親像を見つけるのが難しいように思います。
安藤 モデルはないですよね。僕自身はロックが好きだったので、ジョン・レノンを父親のモデルとして考えていました。パートナーを尊重し、積極的に育児に取り組んで、ラブ・アンド・ピースを目指す(笑)。まあ、あそこまではできないにしても、ジョンのようなマインドをもちたいとは思っていましたね。
しかし現実問題としては、身近なところに理想的な父親のモデルはないと思います。ないからこそ、自分で一からつくっていかなければならない。それは悪いことではないんです。自分自身が理想の父親になっていけばいいわけですから。
例えば僕の本を読んで僕と同じようにやろうと思っても無理だし、無意味です。一人ひとり価値観も生き方も違いますからね。自分で試行錯誤して、自分なりの父親のあり方を実践するということが大切ですし、それは自分の子供の家族観や結婚観にも影響すると思うんです。父親がどう生きていたかということを子供は憶えていてくれるはずです。自分がこの世からいなくなっても、自分がやったことはずっと残っていく。そう考えれば、「よし、かっこいいパパになってやろう」という気になりますよ(笑)。
閉じこもらずに、パパ友をつくることが大切
これからファザーリングを実践しようと考えている人に、アドバイスをいただけますか。
 安藤 大切なのは、「閉じこもらない」ことです。地域の活動などに参加して、他者と積極的にコミュニケーションして、自分をさらけ出す。そうすると、父親としての自分のやり方、生き方を客観視できるようになるんです。僕らが「パパ友をつくろう」と言っているのもそのためです。
安藤 大切なのは、「閉じこもらない」ことです。地域の活動などに参加して、他者と積極的にコミュニケーションして、自分をさらけ出す。そうすると、父親としての自分のやり方、生き方を客観視できるようになるんです。僕らが「パパ友をつくろう」と言っているのもそのためです。
男はたいてい、「泣き言を言うな」とか「歯を食いしばって頑張れ」とか言われて育ってきてますから、威厳とか沽券とかプライドとかが身についてしまって、人に相談したり、弱みを見せたりすることが苦手。だから育児でも一人で頑張ってしまう。でも育児は大変で、とても一人でできるものではない。だから父親も地域でネットワークを持つ必要があるわけです。それに「男のプライド」なんて、実はたいしたものではないですよ。そういうものにこだわっていることの方がはるかにかっこ悪い。僕はそう思っていますね。
女性は子供が生まれると子供が一番になりますが、男性はどうもそうではないですね。仕事、キャリア、交友関係、趣味、実家──そういうものが大切だと考えてしまう。僕自身、最初はそうでした。だから、子供が病気になっても、接待ゴルフに出かけちゃったりするパパがいるわけです。それでだんだん奥さんと感覚がずれていって、ついに修復不可能になってしまう。そういうことを避けるためにも、ほかのパパとどんどん交流して、自分の生き方や価値観を客観視することが必要なんです。
仕事と家庭・育児のバランスを上手にとるコツはありますか?
安藤 「バランス」と考えないことですよね。僕は「寄せ鍋理論」と言っていますが、仕事か育児かみたいに考えるのではなく、ひとつの鍋の中に仕事も育児も趣味も全部入れてしまえばいいと思うんです。それで、その全部を楽しめばいい。それぞれについて「完璧」ではなくて「最善」を目指す。「成功」ではなく「成長」を心掛ける。そう考えれば、気持ちが楽になりますよ。
最後に、これからの目標についてお聞かせください。
安藤 NPOとしては、ファザーリングの認知と浸透のために、面白くって身のある事業を進めていきたいですね。そのうち父親が主体的に関わる保育園をつくることも考えています。個人的には、ラジオのDJをやったり、小学校のそばに喫茶店を開いたりと、いろいろな野望がありますが、言い換えればいろいろな人と交流しながら、楽しく暮らして生きたいってことですね。今住んでいる地域にパパ友が40人くらいいますから、僕はこの地域で年を取っていくことに全然不安はありません。これからは仕事一辺倒の生き方ではなく、そういうスタンスがクオリティ・オブ・ライフに繋がるし、一番大切だと思っています。
-

-
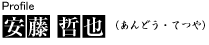
1962年、東京・池袋生まれ。明治大学卒業後、出版社、書店、IT系企業など計9回の転職を経て、2006年11月にNPO法人ファザーリング・ジャパンを立ち上げる。また、2003年より「パパ's絵本プロジェクト」のメンバーとして、全国の書店、図書館、保育園、自治体などで「パパの出張 絵本おはなし会」を開催している。10歳(女)、7歳(男)、0歳(男)の3人の子供の父親で、娘と息子の通う小学校のPTA会長を務めている。
バックナンバー
過去に掲載されたバックナンバーをご覧いただけます。
お問い合わせ[お客様サービスセンター]


- ※電話番号のお掛け間違いにご注意ください。
- ※自動音声でご案内後、担当者におつなぎします。
- ※休み明けは電話が混み合うことがございます。ご迷惑をおかけしますが、ご了承ください。













