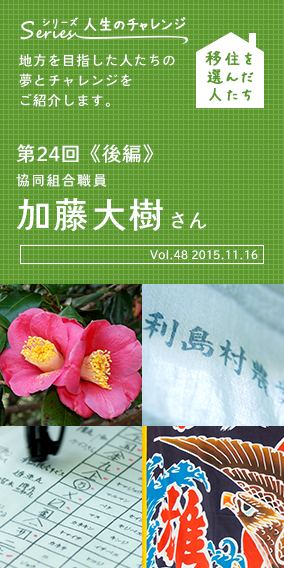- こくみん共済 coop の公式ホームページ
- あんしんのタネ
-

- かとう・だいき/埼玉県出身。自然環境に恵まれた地域に生まれ育ったが、都会に憧れ、地元を離れたい一心で、高校卒業後は東京の美容学校に通う。美容学校を選んだのは、母親が自宅で美容院を経営していたため。サロンで働いたのち、幼なじみと共同で出店も果たし、美容師として7~8年頑張るも、一生の仕事とは思えず、都会暮らしにも違和感を覚える。田舎に目覚めて地域おこしに関心を持ったことから、やはり一次産業が重要と思い至り、農業法人で農業にかかわるイロハを習得。35歳で東京都の離島・人口300人余りの利島(としま)村に家族3人で移住。日本一の椿油の産地をいかに持続可能にするかで奮闘中。
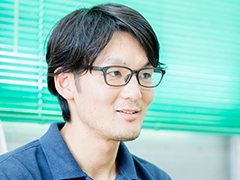
― え?では、下調べはナシですか。
加藤さん:はい。移住前に一度だけ見に来ましたけど、そのときは特段強い印象もなく、「ふうん、こんな感じなのか」くらいでした。住んでみないとわからないですよね。住んでみないとわからないものは住んでみないことには(笑)。300人ちょっとの島での生活なんて未知に決まってますもん。
― その通りと言えばその通りですが、奥さまもそれで問題なく?
加藤さん:彼女は僕よりうんと楽観的なんですよ。僕はこれでもけっこう考え込むタイプで、意外と慎重なの。彼女はとても柔軟で、どこでも生きてゆける人ですね。だからここに来ることにも抵抗がなかったし、来てからもマイペース。そんな奥さんで良かったです。移住前に気になったのは、娘の小学校のことだけです。ひとりだけの新入生ということも容易に考えられるわけで。そしたらなんと、8人もいたんですよ。
― この少子化の時代に、人口300人の島で8人の新入生は多いですよね!加藤さんのようなIターンのご家族が多いのですか?
加藤さん:そうなんです。僕の職場も、漁協も、役場も、Iターンだらけ。30代中心かな。
― そうなんですか。担い手が外から入ってきている形なんですね。唯一の心配だった娘さんの、島での学校生活はいかがですか。
加藤さん:上々ですよ!外遊び大好きで、ほとんど家にいませんね。虫やら草やらいろんなものを持って帰って来ます(笑)。習い事も、フラ(ダンス)にサッカーに剣道、ピアノもやっています。どれも島のサークル活動だったり、できる人がボランティア的に教えてくれるものなので、ほとんどお金はかかっていません。子育ての環境は都会より充実しています。
― それは素晴らしい。加藤さんご自身はいかがですか。暮らしてみて意外だったことはありますか。

![]()
加藤さん:僕も楽しんでます!人口が人口なだけに、みんなが知り合いですが、一緒に飲んで騒げるいい仲間にも恵まれて、農業も、趣味程度ですが野菜づくりを個人的に続けていて、いいペースでやれています。そうそう、地元では、名前のほかに「屋号」と「しるし」というのがあって、呼ぶ人によってその都度使い分けるんです。例えば、仮に苗字が「加藤」でも、屋号は「キョク」だったりして、似ていない(笑)。しるしは、漢字一文字+αのロゴマークのようなものです。仕事でときどき配達に行くのですが、荷物にしるしだけが書かれていることもあります。この習慣は意外でした(笑)。島では当たり前に使われるので、3つをひもづけて覚えておかないと不便なんです。僕はまだ全員分を覚え切れなくて、一覧表を持って歩いています。

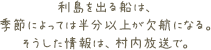
― へー、面白い!同じ東京都なのに。加藤さんはとてもいい具合に馴染んでいらっしゃるご様子ですが、厳しい面としてはどうでしょう。
加藤さん:それももちろんありますよ。「椿で日本一」ということで、勝手に勢いがあるイメージを持っていたのですけれど、ふたを開けてみると、抱える課題は日本のほかの田舎と同じでした。でも、だからこそ呼ばれたんだろうと思うのです。厳しくとも与えられたミッションに挑戦しなくては。ここでこの先もみんなが生きてゆくために、最大の産業である椿油の生産や販売の管理…さらに言うと経営全体になのですが、もっともっと力を入れないといけません。それを考える日々です。
― 椿油の生産日本一で、Iターンも続々来る、といった明るい材料が挙げられましたが、今のままでは将来的にむずかしいですか。

![]()
加藤さん:実際のところ、最大の産業である椿油の、原料の椿農家にしても加工の担い手にしても、それだけで食べてゆける状態ではありません。また、利島は、サザエや伊勢海老といった素晴らしい海産物の豊かな漁場に恵まれていて、かつ、そうした海洋資源を無理なく守りながら漁をする取り組みをしてきた島でもありますけれど、漁業だって将来が明るいとは言いがたいですよね。一次産業は大事だけど、それだけでは立ち行かない。高校のない島で、一度外に出た子どもたちが、当たり前に帰って来られるだけの経済基盤が、ここにはないんです。

― 島の面積の8割を占めているのは椿ですから、最大の特徴であることは言うまでもないですよね。加藤さんのミッションも、やはりその椿で、今後島をどうやって持続可能にしてゆくか、なんですよね。
加藤さん:そうです。椿は、農業というより林業のような側面を持っていて、長い目での先行投資が必要なんです。というのも、実をつけるまでに20~30年かかるんですよ。加えて、農産物としてマイナーなので、研究も進んでいません。いかにして収量を上げるかもですし、ちょうど僕が越して来た年は、害虫が発生して相当な被害を受けているのですが、そうしたケースでどんな対策が効果的なのかであるとか、調査データが少ないんです。日本一と言えど、支えているのは副業的にかかわっている年金受給者という所以は、そんなところにもあると思います。山を持っている個人が、その年にできた実を拾って、それを売って、ぼちぼちやってきています。

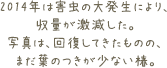

![]()
― なるほど。そこがのどかでいい気もしますけれど、経済基盤としては脆弱なんですね。その分、加藤さんの活躍の余地がありそうですね。
加藤さん:実は最初は、この島にいるのも15年くらいかなぁ、なんて気持ちがあったんです。けれどそれでは、新たに種まいた椿の実の、収穫まで立ち会えないですよね。縁あって来たからには、代々守られてきたものへの責任を、少しでも果たさなければと考えるようになりました。海外からの引き合いもあるし、ビジネスとしてもっと育つ可能性があると思うんです。
― 300人の島ですから、頑張って成果を出せたら、全体に与えるインパクトが大きいですよね。目に見えやすいですしね。
加藤さん:そうなんですよ!まずはここ2~3年で、ある程度の目鼻をつけたいと思っています。やるべきことは、目先のことも、先を見据えても、山ほどありますが、僕なりに精一杯やってみる覚悟です。
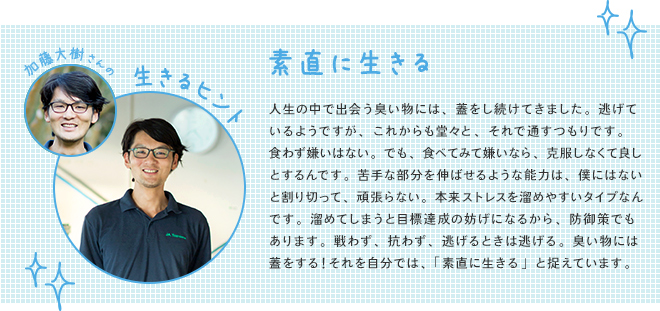
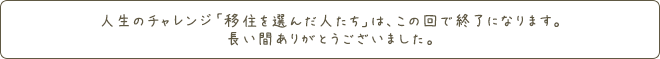
バックナンバー
過去に掲載されたバックナンバーをご覧いただけます。
お問い合わせ[お客様サービスセンター]


- ※電話番号のお掛け間違いにご注意ください。
- ※自動音声でご案内後、担当者におつなぎします。
- ※休み明けは電話が混み合うことがございます。ご迷惑をおかけしますが、ご了承ください。