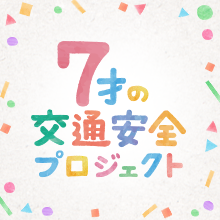- こくみん共済 coop の公式ホームページ
- あんしんのタネ
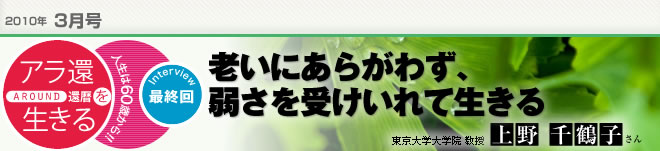
「アラ還(還暦=60歳前後)」の方々にお話をうかがうシリーズ「『アラ還』を生きる」。最終回は、東京大学大学院教授、上野千鶴子(うえの ちづこ)さんのインタビューをお送りします。日本における女性学のパイオニアである上野さんは、近年、高齢者の介護問題に研究領域を広げています。75万部のベストセラーとなった『おひとりさまの老後』、『男おひとりさま道』の著者である上野さんに、これまでの研究や老後の生き方についてうかがいました。
「女の、女による、女のための学問」としての女性学
研究者を目指した理由をお聞かせください。
 上野 私はもともと研究者をめざしていたわけではありません。モラトリアムで大学院に入り、たまたま、女性学と出会った結果、研究者の道を歩むことになったのです。当時、「女性学」という研究領域は、学問としては存在していませんでした。ですから、研究者になった当初は、女性学でメシが食えるとはこれっぽっちも思わず、趣味だと思って研究していました。しかし、いろいろな種をまきながら女性学を育てていった結果、なんとか自分たちが始めた学問の分野でメシが食えるようになりました。いわば、学問の世界のベンチャーとして、女性学をテーマに研究活動に取り組んできたわけです。
上野 私はもともと研究者をめざしていたわけではありません。モラトリアムで大学院に入り、たまたま、女性学と出会った結果、研究者の道を歩むことになったのです。当時、「女性学」という研究領域は、学問としては存在していませんでした。ですから、研究者になった当初は、女性学でメシが食えるとはこれっぽっちも思わず、趣味だと思って研究していました。しかし、いろいろな種をまきながら女性学を育てていった結果、なんとか自分たちが始めた学問の分野でメシが食えるようになりました。いわば、学問の世界のベンチャーとして、女性学をテーマに研究活動に取り組んできたわけです。
女性学とはどんな学問なのでしょうか。
上野 女性学は当事者研究の一種です。学問の世界では長い間、「研究は中立で客観的なものでなければならない」と言われてきました。それゆえ女性が女性研究に取り組もうとすると、「主観的だ」という批判を受けてきました。「客観的な」女性研究に取り組むとすれば、女性以外、つまり男性がやるしかありません。そういう男性による女性論は、ショーペンハウエルや渡辺淳一のように「女についての男の妄想」になってしまうことがほとんどでした。それに対して、女性自身が女性研究に取り組めば、女性のことは女性が一番よく知っているわけですから、そこに妄想の入り込む余地などなく、したがって実態に即した研究ができます。こうした観点から、女性学者の井上輝子さんは女性学を「女の、女による、女のための学問」と定義しました。
「おひとりさま」として切実な介護が研究テーマに
研究領域は障害者や高齢者まで大きく広がりました。その理由をお聞かせください。
 上野 それには2つの理由があって、ひとつは、女性学が女性が自らについて研究する当事者研究であること、今ひとつは、私自身の研究者としての立場の変化です。
上野 それには2つの理由があって、ひとつは、女性学が女性が自らについて研究する当事者研究であること、今ひとつは、私自身の研究者としての立場の変化です。
前者についていえば、女性学は当事者研究なので、年齢を重ねるにつれて自分にとって切実な問題が変化すれば、それにしたがって研究テーマも変化します。一般的に、女性にとって切実な課題としては、若い時なら出産、育児、セクシュアリティ、容貌や身体などが中心になります。それが年を取るにつれて、そのなかに更年期というテーマが入ってきます。そこでは、自分自身の老い方、介護することやされることが研究の主題になっていきます。私も30代から40代、50代へと年齢を重ねるなかで、研究テーマが変わってきました。
一方、研究者にとって、50代というのはなかなか微妙な年代です。40代まで持っていた創造力が低下し新しい研究成果を生み出すことは難しくなり、今まで蓄積してきたものを繰り返すようになりがちです。にもかかわらず、大学や学会で重要なポストを担うようになり、社会的地位は上がっていきます。そのギャップを誰よりも自覚しているのは本人です。
そんななかで、私が50代になった2000年、介護保険が施行されました。そこで「研究領域をシフトするにはちょうどよい機会。これは渡りに船だ」と考え、介護をテーマに研究することに決めました。何よりも、私自身が「おひとりさま」なので、介護の問題は切実なテーマでした。介護保険は日本社会にとってまったく新しい経験だっただけでなく、私自身も福祉の業界には新参者でした。そのため、過去の研究の蓄積は基本的に役に立ちません。ですから新しいテーマにチャレンジすることができたのです。そういうわけで、2000年から現在まで10年余り、自分にとっては未知のテーマだった介護の問題に取り組んできました。
2007年に出版された『おひとりさまの老後』が75万部のベストセラーになりました。
どんな目的で書かれたのでしょうか。
上野 少子高齢社会の今、長生きすればするほど、みんな最後はひとりになります。結婚した人も、しなかった人も最後はひとりになるわけです。だとすれば、ひとりで暮らすためのノウハウを準備した方がよいと考えました。とりわけ、これまで女性の「おひとりさま」はそれだけで、同情と差別の対象でしたから、「大きなお世話だ」という思いもありました。それで、「女性はひとりになっても生きていけるよ」という励ましのメッセージを送りたいと思い、本書を書きました。そして、脱血縁、脱地縁、脱社縁の、加入脱退が自由で包括的帰属を要求しない選択縁の関係をたくさん持つ「人持ちになること」が大切だと強調しました。
勝ち負けを争うパワーゲームから降り、「助けてくれ」と人にいう
続いて、2009年には『男おひとりさま道』を出版されました。
 上野 2008年の統計によれば、65歳以上の「女おひとりさま」は5人にひとり、対するに「男おひとりさま」は10人にひとりと半数に近く、これからも増える一方です。また昨今では、ひとり暮らしに限っていえば、女性より男性の方が同情と憐憫の対象になってきました。そこで、「男おひとりさまに生きる道はあるか?」「イエス」という答えを出したのが、この本です。この本のなかで一番いいたかったことは、「現役時代に会社でやっていたような上昇指向を持ち続けたり、勝ち負けを争うパワーゲームから降りよう。降りないとつらいのは、あなた自身ですよ」ということです。男の人はデイサービスに行ってまで、頭のなかは社長だったり、先生だったりします。それをやめようということを、愛情込めて書きました。ですので、読者からは「やさしい」とか「身につまされる」などの感想を多くいただきました。なかでも、「私はこれまで上野千鶴子を男の敵だと思ってきましたが、この本で認識を改めました(70代男性)」という便りをもらったことが一番嬉しかったですね。
上野 2008年の統計によれば、65歳以上の「女おひとりさま」は5人にひとり、対するに「男おひとりさま」は10人にひとりと半数に近く、これからも増える一方です。また昨今では、ひとり暮らしに限っていえば、女性より男性の方が同情と憐憫の対象になってきました。そこで、「男おひとりさまに生きる道はあるか?」「イエス」という答えを出したのが、この本です。この本のなかで一番いいたかったことは、「現役時代に会社でやっていたような上昇指向を持ち続けたり、勝ち負けを争うパワーゲームから降りよう。降りないとつらいのは、あなた自身ですよ」ということです。男の人はデイサービスに行ってまで、頭のなかは社長だったり、先生だったりします。それをやめようということを、愛情込めて書きました。ですので、読者からは「やさしい」とか「身につまされる」などの感想を多くいただきました。なかでも、「私はこれまで上野千鶴子を男の敵だと思ってきましたが、この本で認識を改めました(70代男性)」という便りをもらったことが一番嬉しかったですね。
勝ち負けの争いから降りるにはどうしたらいいのでしょうか。
上野 人生には「上り坂」と「下り坂」があります。そのピークは50代でしょうか。上り坂の時期は、昨日までもっていなかった能力や資源を今日は身につけて、どんどん成長・発展していく。その反対に下り坂は、昨日まで持っていた能力や資源を次第に失っていく過程です。老後は下り坂ですから、そこを生きるためには「下り坂を降りるスキル」が必要です。そこでは、相手を威嚇するために、自分の手札を実際よりも強く見せるようなやり方とは対極の、自分が持っていない能力や助けを相手から引き出すための「弱さの情報公開」が欠かせません。なお、この「弱さの情報公開」という言葉は、北海道浦河町にある精神障害者のための共同体「べてるの家」の標語のひとつです。私は2002年に、24時間介助を必要とする重度の障害者でも地域で自立した生活を送ることができるように自立生活センターの運動を担っていた中西正司さんと出会い、障害者の人たちとのおつきあいを深めてきましたが、そのなかでこの言葉と出会いました。
「弱さの情報公開」という発想は、当事者性の問題とリンクします。すなわち、精神障害者の人たちは、当事者性というものを一番奪われてきました。彼らは何を言っても、真に受けてもらえないという経験を、イヤというほどしてきたわけです。たとえば彼ら/彼女らは、時として自分で自分をコントロールできなくなったり、パニックに陥ったり、身体が固まってしまったりします。しかしこれまでは、そうした「当事者」の状況をなかなか理解されずにきました。そこで、「自分で自分をどうしようもできなくなったら、誰かの助けを求めたらよい」「障害によって自分でトイレに行けなくなったら、介助してもらえばよい」という発想が生まれました。そして、その助けの求め方の白眉ともいえるのが「弱さの情報公開」です。すなわち、「弱いことは悪いことでも、恥ずかしいことでもない。過労になれば身体は壊れるし、追いつめられたら心が壊れる。だから、自分の弱さを引き受けて、誰かに助けてもらおう」というのです。
基本は社会的弱者が安心して暮らせる社会を作ること
実際問題として、「助けてくれ」とはなかなかいえません。
 上野 最近、「老いる」とは「老い・衰える」とセットでいうようにしています。昔のように人生50年であれば、ポッキリ矢が折れるように、現役の最中に死ねたかもしれません。しかし、栄養水準も向上し、医療水準や衛生水準、介護水準が高くなった今の日本社会では、「ピンピンころりと死にたい」といっても、突然死は期待できません。脳血管障害を経験しても多くの人が半身マヒや言語障害などの後遺障害を残して、かなりの期間、生き延びることになります。すなわち、誰でも老いれば平等に衰え、中途障害者になる可能性を持っているのです。ですから、「生涯現役などといえばいうだけ、いったあなたご自身がつらいでしょう」と思うのです。それゆえ虚勢を張らずに、自分の弱さを人に見せて、「助けてくれ」といえるようにすることが大切なのです。
上野 最近、「老いる」とは「老い・衰える」とセットでいうようにしています。昔のように人生50年であれば、ポッキリ矢が折れるように、現役の最中に死ねたかもしれません。しかし、栄養水準も向上し、医療水準や衛生水準、介護水準が高くなった今の日本社会では、「ピンピンころりと死にたい」といっても、突然死は期待できません。脳血管障害を経験しても多くの人が半身マヒや言語障害などの後遺障害を残して、かなりの期間、生き延びることになります。すなわち、誰でも老いれば平等に衰え、中途障害者になる可能性を持っているのです。ですから、「生涯現役などといえばいうだけ、いったあなたご自身がつらいでしょう」と思うのです。それゆえ虚勢を張らずに、自分の弱さを人に見せて、「助けてくれ」といえるようにすることが大切なのです。
安心して暮らしていくには、一人ひとりの生き方だけでなく、社会の仕組みも変えていかなければなりません。そのあたりをどうお考えですか。
上野 先ほども述べたように、老いとは衰えること、つまり中途障害者、社会的弱者になることです。ですから、社会的弱者に安心してなれる社会を作ろう、ということが基本です。安心して老いられない社会では、人は安心して生き続けられません。高齢者の安心は高齢者だけの安心ではない。歳をとってから切り捨てられるような社会で、若い人も含めて誰が安心して働き続けられるでしょうか。安心して社会的弱者になれない社会は、弱者でない人も生きづらい社会です。そこで、障害者の人たちを見ると、運動神経が冒されて全身の筋肉が衰えていく難病の筋萎縮性側索硬化症(ALS)など最重度の障害を持っていても、尊厳を持って地域で自立生活を送っている人たちがいます。だとすれば、その人たちに学べばよい。高齢者が学ぶべきモデルはすでにたくさんあります。
それを社会的に支えるものとして、介護保険が施行されたことは、とても大きな変革でした。それまでは弱者は家族がお世話をするものでした。それが社会の側に責任があるという介護の社会化の第一歩が踏み出されたわけですから。しかし、そうした大きな期待を担って始まった介護保険ですが、3年に一度の改定の度に、利用制限が増えてどんどん使い勝手が悪くなり、介護報酬も抑制されるなど、改悪に次ぐ改悪で困ったものだと考えています。何とか、改悪を食い止め、使い回しながら、使い勝手のよいものにしていかなければなりません。
障害者のように、高齢者が地域で生きられる社会を目指す
具体的にはどうすればよいのでしょうか。
上野 障害者運動に学ぶことは、とてもたくさんあると思います。障害者運動はこの30年余り、施設で暮らすのではなく、地域で自立した生活を送るという「脱施設化」を進めてきました。ところが、高齢者を対象にした介護保険のもとでは、強い施設志向が生まれました。実際に調査をしてみると、自分から進んで、デイサービスやショートステイ、養護老人ホームなどの施設に行きたいと考えている高齢者はほとんどいません。施設を望むのは、少しの間でも家から出て行ってほしいと考える家族の方です。そうすると、施設志向は当事者のニーズではありません。かつて、施設利用者である障害者本人とその家族の利害が対立することをはっきり示したのが障害者運動でした。それと同じで、家族は決して当事者である高齢者の味方とは限らないのです。
障害者の方たちは命がけで、地域で自立生活をして、脱施設化を果たしてきました。重度の全身性障害者が24時間介護を受けて、自立生活ができるのであれば、どうして高齢者ができないのか。私には不思議でなりません。自治体が保育園の待機児童ゼロ作戦を進めるのは賛成ですが、「もっと施設を」という待機高齢者ゼロ作戦だけは絶対に止めてほしいのです。高齢者を1か所に集める施設ではなく、年をとっても、要介護になっても、行きたいところに自由に行けるための外出介助サービスの提供や誰でも自由に利用できるバリアフリーの都市インフラを作ることが何よりも、優先されるべきだと思います。
-

-

-
東京大学 大学院人文社会系研究科 教授(社会学専攻)
1948年富山県生まれ。京都大学大学院社会学博士課程修了。1993年東京大学文学部助教授(社会学)、1995年東京大学大学院人文社会系研究科教授。専門は女性学、ジェンダー研究。この分野のパイオニアであり、指導的な理論家のひとり。『近代家族の成立と終焉』(岩波書店)、『当事者主権』(中西正司と共著・岩波書店)、『老いる準備』(朝日文庫)、『「女縁」を生きた女たち』(岩波現代文庫)、『世代間連帯』(辻元清美と共著・岩波書店)など著書多数。近年は高齢者の介護問題に関わり、『おひとりさまの老後』(法研)はベストセラーに。2009年には『男おひとりさま道』を刊行。
バックナンバー
過去に掲載されたバックナンバーをご覧いただけます。
お問い合わせ[お客様サービスセンター]
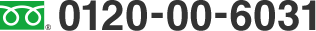

- ※電話番号のお掛け間違いにご注意ください。
- ※自動音声でご案内後、担当者におつなぎします。
- ※休み明けは電話が混み合うことがございます。ご迷惑をおかけしますが、ご了承ください。