- こくみん共済 coop の公式ホームページ
- あんしんのタネ
今月の「生きるヒント」
一生のうち、住まう家は限られています。長く過ごすところだから、できるだけ居心地よく、自分らしく保ちたい。常に最高のモノに囲まれて生活したり、時間をかけてお手入れしたりは無理でも、それぞれのペースで、日々の豊かさを感じられる暮らしがしたい。こころも充実、エコで豊かな「生きるヒント」をお届けします。
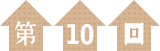
冬といえば鍋料理!コロンとした見た目にも親しみがわく土鍋は、長く日本の食卓をあたためてきました。みんなで囲む楽しさはもちろん、ひとりでだって栄養をたっぷりととれて、心まで満足です。実は年中さまざまな使い方ができて多機能な土鍋の魅力を、老舗専門店でお聞きするとともに、料理家の枝元なほみさんには、冬の新定番鍋を教えてもらいました。


長谷園
長谷伊佐子さん
長谷園(ながたにえん)は、土鍋に適した陶土の産地として知られる三重県伊賀市に窯を構えて現在8代目の老舗。お名前でわかる通り、長谷さんはその経営者一家のおひとりで、「東京店イガモノ」の店長さん。伊賀焼愛、土鍋愛にあふれています。
長谷園公式サイト
日本中の家庭で親しまれている土鍋。改めて目を向けてみると、ほかにはない特長を多く持ち合わせていることがわかります。天然の土からつくられた昔ながらの焼物ゆえに見過ごされがちですが、特筆すべきはまずその機能。長谷さんによると、食材を加熱するとき、酵素の働きで特に旨味を増す温度帯が40~60度。一気に熱が通る金属の鍋に比べ、ゆっくり温めゆっくり冷めるのが特徴の土鍋は、その温度帯をじっくり通るので、「勝手においしくしてくれる」のだそうです。原料が土であるため無数の気孔を持ち、そこから出てくる細かい泡がコトコトと食材を調理する。火から下ろしてからも余熱でじんわり味が染み込む。土鍋の実力、恐るべし。

忍者の里として有名な伊賀ですが、質の高い陶土を産出し、伊賀焼が生まれた地でもあります。直火にかけられるほどの耐火性を有する焼物用の土は、日本でほかにないとも言われます。驚くことにその伊賀の陶土、400万年前に琵琶湖の湖底にあったものなんだとか。あれ?だって伊賀って三重県、琵琶湖は滋賀県…。と思いますが、琵琶湖固有のそれとされる地層が現在の伊賀にあって、「古琵琶湖層」と呼ばれているそう。焼物のための薪に最適なアカマツが豊富だったこともまた、伊賀焼が盛んになった理由のひとつです。製造において工場での工程が増えた今も、鍋底の削り出しや、取っ手をつける作業は職人が行うのが基本。自然の材料と人の手によるものだからこそのあたたかみも、土鍋の魅力です。
写真:鍋底の削り出しは、機械が自動的に行ってはくれない。

日本の優れた調理道具である土鍋を、もっともっと使ってほしいとの思いから、時代に合い、誰にでも扱いやすい商品の開発に努めてきたという長谷園。蒸し用(30年来のロングセラー!)、火加減いらずの炊飯用、卓上の燻製用といった用途別の土鍋のほか、電子レンジやIHに対応した土鍋もそろっています。けれどそれにも増して大事な土鍋の機能を、長谷さんは、「囲みの良さ」と表現。「知らない人同士でも、囲むと和み、会話が弾みますよね。なんといってもこれは、土鍋の持つ最も代えがたい機能です」。…納得!
写真:左は燻製、右は蒸すための土鍋。真ん中は少量の調理に便利な「エッグベーカー」で、レンジやオーブンでも使えるほか、器にしてもカラフルで楽しい。
新品の使い始めには、残りごはんでお粥を炊き“目止め”します。これを怠るとひび割れなどの原因になるため、「不要」とある製品を除いては一手間かけましょう。使用後は底を上にして、十分乾燥させてからしまいましょう。


料理家
枝元なほみさん
自由な発想で、どんな人にもつくりやすい家庭料理を生み出し続ける「エダモン」こと枝元なほみさん。提案される料理と同様、あたたかみあるキャラクターで人気の料理家です。職業柄、調理道具には相当のこだわりをお持ちの枝元さんも、土鍋を絶賛。今回はスペシャルレシピをご紹介いただきます。
チームむかご公式サイト
「土鍋の良さ?それはもう、いっぱいありますよ。つくったまんま出せてひとつで済むから、片付けが楽でしょ。あったかいまま食べられるでしょ。あとね、鍋物だけじゃなくてね、煮物をつくっても仕上がりが違うんです。熱の当たりがじんわりやわらかいんでしょうね、素材が喜んでる感じ」と、枝元さん、もう止まりません。「調理道具や熱源の違いで、同じ料理でも味が変わってくるんです。だから、金属の鍋でつくるのと違うの。土鍋はまぁるい味になる」と、膨大な時間を料理に費やしてきたプロがおっしゃるのだから説得力があります。

この日は、枝元さんの大のオススメ土鍋レシピを教えてもらいました。鍋物の定番野菜、白菜を主役にした鍋です。ただし白菜はそのままでなく、いったん漬物にしてから使います。発酵食品の健康効果は広く知られるところですが、それを抜きにしたとしてもオツな味を楽しめます。ちょっと大人な滋味深い味わいで、とっても簡単なのに、料理の上級者気分になれますよ。ぜひお試しを!
まずは白菜の古漬け(枝元さんは「白菜のザクザク漬け」と命名)をつくります。
- 白菜4分の1個を、芯をつけたまま洗って水気を切り、まな板に横に置いたら、繊維を断ち切る方向に1cmずつ、ザクザクと切ってゆきます。
- 保存袋に入れ、白菜の重さの1~1.5%(白菜4分の1個に対して小さじ1.5~2)の塩を加え、ざっと揉みます。
★酸味が出てきたら冷蔵庫に。一冬保存できて、ご紹介する鍋料理のほか、お味噌汁や炒め物、卵とじにしてもおいしい。
白菜のザクザク漬けと豚肉の鍋
材料(4人分)
- 白菜の古漬け 4分の1個分
- 豚バラ肉の薄切り 200g
- しめじ 1パック
- 片栗粉 大さじ1
- 鶏がらスープの素 小さじ2
- 醤油 小さじ1
- 酒 小さじ1
つくり方
- 土鍋に4カップの水を入れて沸かし、鶏がらスープの素を入れる。
- 豚肉は1cmくらいに切ってボウルに入れ、醤油、お酒を加えて片栗粉をもみ込む。
- スープが煮立ったら、白菜の古漬けを味を見ながら漬け汁ごと入れ、しめじ、豚肉と一緒に火を通したら出来上がり。お好みで、醤油やナンプラーで味を整えます。刻んだホアジャオ(花椒)や辣油、一味などを入れてもおいしい。具には豆腐も合います。
古漬けを使った鍋なので、その酸味が真骨頂です。だけど酸味がちょっと苦手という方は、浅漬けでもできます。浅漬けの場合は、鶏がらスープではなく昆布と鰹節でとったお出汁であっさりと。
土鍋料理は、みんなではもちろん、ひとりでも楽しんでもらいたいです。完成して供されるのが皿の上ではない分、途中で味を変えつつ食べてもいいし、経過に参加する感じがいい。キッチンに立ち慣れていない人も、時間による変化を過程ごと楽しみながら、味わってくださいね。

なりたちや文化に、シンプルな道具である土鍋の、懐の深さを見たようでした。ここで、「機能」という言葉で表されるものは、「性格」に近くて、土鍋は「性格」が良い気がします。丸くてあたたかで、料理の味まで丸くする。周辺に人が集まり、笑顔になる。ぜひとも、末長く仲良くしたいです。
お問い合わせ[お客様サービスセンター]


- ※電話番号のお掛け間違いにご注意ください。
- ※自動音声でご案内後、担当者におつなぎします。
- ※休み明けは電話が混み合うことがございます。ご迷惑をおかけしますが、ご了承ください。


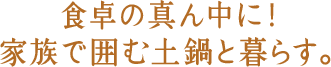
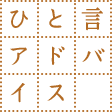














寒い季節が終わってもしまい込まずに、ぜひ年中使ってもらいたいです。私たちが行う料理教室では、土鍋でつくった煮物や蒸し料理のおいしさに「驚いた!」とおっしゃるお客様が多いです。用途が広いんですよ。いったん水を含ませるだけで保冷もできるため、夏場は、白ワインのボトルを入れたり、畑で採れた野菜の容れ物にも。土鍋には使い込むと“育つ”ような経年変化があるので、それも楽しんでください。