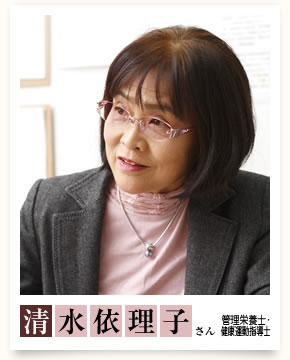- こくみん共済 coop の公式ホームページ
- あんしんのタネ

-
家族と食卓を囲みながら、ゆったりとした時間を過ごし地域のことにも思いをはせるーー。そんな、あたりまえの「豊かな暮らし」を求める人が増えています。「食の安全」「地産地消」「スローフード」などのキーワードがしばしばメディアを賑わすのも、そうした表れの1つ。このシリーズでは、「食」と「暮らし」を巡って議論されている、古くて新しい豊かさと幸福、持続可能なライフスタイルとは何か、を探っていきます。
第9回目にご登場いただくのは、管理栄養士の立場から介護食をはじめ、健全な食生活を送るための食事の実践に力を注いでこられた清水依理子さん。健康寿命を延ばすための「食」のあり方についてうかがいます。
管理栄養士として介護福祉士の養成に尽力
管理栄養士である清水さんが介護との関わりを深められたきっかけは何ですか?
また、現在は主にどのような活動をされていますか?
![]() そもそものきっかけは、日本の高齢化が急速に進むなか、1987年(昭和62年)に「社会福祉士及び介護福祉士法」が制定されたことにあります。介護福祉士の養成を行う学校(施設)では、介護福祉士として必要な知識と技術を教える教員の確保が急務となり、私は周囲の勧めもあって、ある学校の専任教員になりました。
そもそものきっかけは、日本の高齢化が急速に進むなか、1987年(昭和62年)に「社会福祉士及び介護福祉士法」が制定されたことにあります。介護福祉士の養成を行う学校(施設)では、介護福祉士として必要な知識と技術を教える教員の確保が急務となり、私は周囲の勧めもあって、ある学校の専任教員になりました。
ただし、当時は「介護」と「看護」の定義についてようやく議論が始まった頃で、介護は看護の一部であるという考え方が支配的でした。ちなみに当初、教員の大半を占めていたのは看護師の方たちで、管理栄養士や栄養調理、家政をバックグラウンドとする専任教員は私を含め、全国で4人だけという状況でした。
その後、カリキュラムの一環として特別養護老人ホームで行う学生実習などを通して介護食の現状を目の当たりにし、問題意識を持つようになりました。端的にいえば、介護の現場で何より必要なのは既存の介護食に代わる「食」、1人ひとりの状況に合わせたおいしい「食」であるという強い思いです。
現在は、非常勤としていくつかの講座を受け持ちながら、基本的にはフリーとしての立場から一般の方たちをはじめ、調理師や介護食士の方たち、さらにケアスタッフやケアマネージャーの方たちを対象に、健康科学や栄養調理についての講演・講習などを行っています。
必要なのはオーダーメイドのおいしい介護食
介護食の現状と問題点についてどうお考えですか?
![]() 一般に「食」には「人」を「良」くするという意味が込められているといわれますが、人は「食」なくして生命を維持することはできません。また、「食」を通して体のための栄養素だけでなく、心や精神のための栄養素も得ています。つまり「食」とは、人それぞれの楽しみや生活文化の充実、人間としての尊厳に深く関わっている行動であり、生きる意欲や心の平安・豊かさをもたらしてくれるものなのです。
一般に「食」には「人」を「良」くするという意味が込められているといわれますが、人は「食」なくして生命を維持することはできません。また、「食」を通して体のための栄養素だけでなく、心や精神のための栄養素も得ています。つまり「食」とは、人それぞれの楽しみや生活文化の充実、人間としての尊厳に深く関わっている行動であり、生きる意欲や心の平安・豊かさをもたらしてくれるものなのです。
そうした観点から見ると、医療における「食」と介護における「食」は、目的がまったく違います。前者が「生命の長さ(Length of Life)」に重きを置く「食」とすれば、後者は「生命の質(Quality of Life)」に重きを置くべき「食」といえます。「食」は日常生活において「当たり前」のことだけに、ともすれば大切さや難しさは意識されない傾向にありますが、介護の現場においてもその「当たり前」を継続させていくことが最も大切なポイントであり、同時に難しい点でもあります。
より具体的にいえば、「刻み食」「ペースト食」「流動食」に代表されるこれまでの介護食は、言葉を換えれば食を取り戻す段階の「治療食」の範疇に属するものといえます。これらの介護食は、あくまでも「食べられない」という結果にもとづいた「技法」に過ぎません。本当に必要なのは、咀嚼や嚥下の能力に合ったオーダーメイドの介護食、食の専門家である調理師によるおいしい介護食です。和食の料理人である稲葉恭二先生と協力して出版した『長続きするおいしい介護食』では、そうした思いを込め、介護する方はもちろん、介護される方にも分かりやすい形で介護食の基礎知識や多彩なレシピなどを提案しています。
かつて研修で訪れた福祉先進国のデンマークでは、認知症の患者の方がきれいにセッティングされたテーブルで、楽しみながら食事をされていました。それは、日本の介護の現場においても決して実現不可能な光景ではないと思っています。
健全な食生活を送るための『四群点数法』
高齢化が進むなか、介護食に加え、健康寿命を延ばす「介護予防」という
考え方を提唱されています。
![]() 総務省の推計によると、2010年9月15日時点で日本の高齢者(65歳以上)人口は2944万人となり、総人口に占める割合は23.1%と、過去最高を記録しました。少子化の影響もあり、高齢化が加速しているのは間違いありません。また、痴呆性高齢者は、2025年には323万人、2030年には353万人に達するという推計データもあります。
総務省の推計によると、2010年9月15日時点で日本の高齢者(65歳以上)人口は2944万人となり、総人口に占める割合は23.1%と、過去最高を記録しました。少子化の影響もあり、高齢化が加速しているのは間違いありません。また、痴呆性高齢者は、2025年には323万人、2030年には353万人に達するという推計データもあります。
人が「老化」「加齢」を迎えるのは自然な流れです。「老化」「加齢」のスピードには個人差がありますが、介護の要・不要にかかわらず、身体状況・生理機能は確実に衰えていきます。しかしその一方で、人は最期まで「よりよく生きたい」「より楽しみたい」という希望や欲求、心地よさや安らぎを求め続けるのも事実です。それを実現するためには健康寿命を延ばす必要があり、その鍵を握っているのが「食」なのです。
医学には「予防医学」という分野があります。食生活を中心に、生活習慣を健全に保つことで病気になりにくい心身を作るという考え方にもとづいた医学です。これに対して「介護予防」は、簡単にいえば高齢者が要介護状態になることを防ぎ、健康的な生活を維持するという考え方であり、食生活が重要な鍵となる点は予防医学と同じです。
では、どうすれば健全な食生活、バランスのよい食事を実現できるかという問題ですが、私が推奨しているのは『四群点数法』です(下の表を参照)。これは、女子栄養大学の創立者・故香川綾先生が考案された食事法で、すべての食品をその栄養学的な特徴から4つのグループ(食品群)に分類し、それぞれの食品群からバランスよく食品を選択することで、栄養の心配をせず、変化に富んだ食事を楽しむことができます。
もう少し詳しくいうと、食品のエネルギーを「80kcal=1点」という単位で表し、1日20点(1600kcal)の場合、第1~第3の食品群から3点ずつ、合計9点を優先的に食べ、第4の食品群で残りの11点をバランスよく食べると、体に必要な栄養素を過不足なく摂取することができます。
点数法と聞いて「面倒そうだ」と思われる方もいらっしゃるでしょうが、大まかな分類と量を頭に入れておき、買い物の際に目安にする習慣を身につければ、簡単に実践することができます。また、たとえ偏った食事をした場合でも、次の食事で全体のバランスを調整するという意識を持って実行することで、健全な食生活を保つことができます。
手軽においしくできる「家庭版低温真空調理」
老化が進むと、どうしても咀嚼や嚥下の能力が低下します。栄養バランスがよく、
食べやすい食事をより手軽においしく調理する方法はありますか?
![]() 咀嚼や嚥下の能力は個人差がありますので、まずは程度をよく見きわめたうえで食材を咀嚼・嚥下しやすい硬さに調節する必要があります。しかし高齢者の場合、身体機能や体力の低下によってうまく調理ができなかったり、時間がかかったりするケースも少なくありません。そこでご紹介するのが、電気湯沸かしポットとポリ袋を使った「家庭版低温真空調理」です(下の図を参照)。真空調理は、もともとフランスで生まれた調理法で、焼く・煮る・蒸すに次ぐ第4の調理法ともいわれています。
咀嚼や嚥下の能力は個人差がありますので、まずは程度をよく見きわめたうえで食材を咀嚼・嚥下しやすい硬さに調節する必要があります。しかし高齢者の場合、身体機能や体力の低下によってうまく調理ができなかったり、時間がかかったりするケースも少なくありません。そこでご紹介するのが、電気湯沸かしポットとポリ袋を使った「家庭版低温真空調理」です(下の図を参照)。真空調理は、もともとフランスで生まれた調理法で、焼く・煮る・蒸すに次ぐ第4の調理法ともいわれています。
ただし、電気湯沸かしポットを調理に使うのは本来の使用法ではありませんので、あくまでもご自身の判断で、自己責任のもとに実践していただく必要があるという点をあらかじめお断りしておきます。また、ポリ袋はスーパーのレジの近くに置いてあるロール状のポリ袋のような、薄い半透明の高密度ポリエチレン袋を使用します。
調理法はいたって簡単で、食材を(必要に応じて調味料も一緒に)ポリ袋に入れて空気を抜き、上端を結んだら水を入れたポットに沈め、あとはスイッチを入れて出来上がるのを待つだけです。調理に要する時間は、食材の種類や出来上がりの硬さ、ポットの性能によって異なりますので、状況に応じて調節してください。
空気を抜く方法としては、手でしごく、水を張ったボウルに沈めるといった方法がありますが、いずれの場合も加熱することでポリ袋は膨張しますので、できるだけ開口部に近い箇所でしっかりと結びます。また、使用するポットは縦長のもので、水は容量の3分の1、3リットルのポットであれば1リットルを上限とします。
この調理法には「食材が酸化しにくく、本来のうまみが閉じこめられておいしい」「煮くずれしにくく、目減りしない」「味が安定して軟らかく、内部まで味が浸透する」「少量の調味料で味付けができ、減塩・減脂効果につながる」といったメリットに加え、「火を使わないので安全」「複数の食材を同時に調理できる」「時間・労力・光熱費を節約できる」といったメリットもあります。
「食」はすべての人にとって共通のテーマ
健康長寿の実現に向けた今後の活動目標についてお聞かせください。
![]() 「食」は生命の源であり、生活の主体者として自分らしい暮らしをより長く維持・継続するためには、健全な食生活、バランスのよい食事が不可欠です。言葉を換えれば、「食」は高齢化社会における大きな「生活目標」の1つといえます。そこで、まずはその実現に向けて、介護食に関わる人材の育成や、高齢者の方たちへの食事指導などに力を注いでいきたいと思っています。
「食」は生命の源であり、生活の主体者として自分らしい暮らしをより長く維持・継続するためには、健全な食生活、バランスのよい食事が不可欠です。言葉を換えれば、「食」は高齢化社会における大きな「生活目標」の1つといえます。そこで、まずはその実現に向けて、介護食に関わる人材の育成や、高齢者の方たちへの食事指導などに力を注いでいきたいと思っています。
もう1つの目標は、介護する方たちへの啓発・サポート活動です。在宅での介護であれ、施設での介護であれ、介護は多大なエネルギーを要します。よりよい対人サービスを提供するためには、自分自身が健康でなければなりません。そこで、一般の方たちや医療・保健・福祉関係の方たちを対象に、いろいろな機会を通じて「食」を中心とした自己管理の大切さをお伝えしていきたいと考えています。
約60兆の細胞で形成されているという点で、人はみな同じです。ただライフステージが違うだけです。つまり「食」は年齢に関係なく、すべての人にとって共通のテーマなのです。今後ともご要望がある限り、健全な食生活の実現に向けて全国どこへでも足を運び、幅広い活動を展開していきます。
![]()
-
第一群:乳・乳製品、卵
日本人が不足しがちな栄養素を含み、栄養バランスを完全にする食品群。毎日欠かさずとってほしい。
-
第二群:魚介、肉、豆・豆製品
肉や血を作る良質たんぱく質の食品群。体のたんぱく質はつねに作りかえられるので、毎日適量を食べたい食品。
-
第三群:野菜、芋、果物
体の調子を良くする食品群。野菜は、緑黄色野菜 120g以上、淡色野菜(キノコ、海藻を含む)230g
-
第四群:穀物、油脂、砂糖、その他
力や体温となる食品群。この群では自分の体重などを考慮して増減し、ふさわしい量をとる。
![]()
四つの食品群から一日に3・3・3・11点ずつバランスよく食べると、体に必要な栄養素を過不足なくとることができます。
| 食品群 | 食品例 | 点数 | 特徴 | ||
| 第1群 | 乳 | 牛乳 2/3杯(120ml) | 1 | 3点 | 良質たんぱく質、ビタミンA・B2、更に乳にはカルシウム、卵には鉄分など各種の栄養素を幅広く含んでいます。 |
| 乳製品 | プレーンヨーグルト(130g) | 1 | |||
| 卵 | 卵1個(50g) | 1 | |||
| 第2群 | 魚介 | サバ 1/2切れ(正味 40g) | 1 | 3点 | 良質たんぱく質の供給源。身体を構成している細胞を作る成分です。ビタミンA・ビタミンB1・B2、鉄、カルシウムなどを豊富に含む。 |
| 肉 | 牛ヒレ肉(60g) | 1 | |||
| 豆製品 | 木綿豆腐 1/3丁(110g) | 1 | |||
| 第3群 | 野菜 |
人参 1/3本(100g) プチトマト 3個(30g) レタス 3枚(60g) きゅうり 1/2本(50g) 大根 5cm(150g) えのき 1/2袋(50g) わかめ(戻し) (10g) (350g以上) |
1 | 3点 | ビタミンA・C、ミネラルの供給源。食物繊維源となる食品群。芋類の主成分はでんぷんであるためエネルギーも多いがビタミンC・B1、カリウムなどミネラル、食物繊維も含まれ野菜と同じ一面をもっています。 |
| 芋 | じゃがいも 1個(100g) | 1 | |||
| 果物 |
みかん大 1個(90g) バナナ 1/2本(50g) |
0.5 0.5 |
|||
| 第4群 | 穀物 |
パン 6枚切り1枚(60g) ごはん 茶碗軽く2杯(200g) ゆでうどん 1玉(250g) |
2 4 3 |
11点 | 糖質や脂肪の多い食品群で、おもにエネルギー源となる。活動量や体重に応じて、この4群で調節するとよい。 |
| 砂糖 | 砂糖 大さじ1(9g) | 0.5 | |||
| 油脂 | 油 大さじ1強(13g) | 1.5 | |||
![]()
-

切った食材と調味料をポリ袋に入れます。
-

ボールに張った水に袋をつけて、水圧により空気を抜きます。
-

ポリ袋の上のほうでしっかり結び、水を張った縦長タイプの電気ポットに入れて、加熱・保温。時間は食材により異なりますが、一人分30分が目安です。
-

できあがり!
お問い合わせ[お客様サービスセンター]


- ※電話番号のお掛け間違いにご注意ください。
- ※自動音声でご案内後、担当者におつなぎします。
- ※休み明けは電話が混み合うことがございます。ご迷惑をおかけしますが、ご了承ください。