私は5歳くらいまで満州(現・中国東北部)に住んでいて、1945年の終戦時に日本に帰国しました。帰国するときは日本赤十字社(以下、赤十字)の腕章をした人たちに支援していただいた記憶があり、その後、赤十字の活動内容を知って大変感銘を受けまして、「自分も誰かのためになる活動をしたい」という思いから赤十字のボランティアに関わるようになりました。赤十字が実施する講習を通じて「救急法指導員」や「家庭看護法介助員」などの資格を取得し、今は人命救助や看護に関する基本的な知識や技術の普及に努めています。
防災の大切さは、ボランティアを通じてわかっているつもりでしたが、自分自身が被災者になってみて、あらためて備えておくことの大切さを学んだ気がします。
健康維持を忘れずに、
人が喜ぶことを続けていたい。

千葉県在住
中島 淑郎(なかじま よしろう)さん [78歳]
PROFILE
60歳で退職後、「人が喜ぶことをする」をモットーに自治会の役員、社会福祉協議会の福祉委員など、さまざまなボランティア活動に参加。高校生のころから続けているノルディック・ウォークは指導者の資格を持つほど。
幼少時代の思い出がきっかけで、日本赤十字社のボランティアに参加

3.11直後はボランティアで都内の帰宅困難者をサポート
2011年3月11日の東日本大震災のときは、都内の専門学校で救急指導員として講習をしている最中だったのですが、大きな揺れで授業どころではなくなりました。
ホールのような広い場所で授業をしていたので、上から物が落ちてきたり、何かが倒れたりするような心配はなかったのですが、今まで体験したことのないような大揺れで生徒たちはパニック状態。私も冷静になるようにと呼びかけるのが精一杯でした。
揺れがおさまり、生徒たちにけががないことを確認してホっとしたものの、携帯が使えない、電車がストップしたなど、都内のあちこちで地震の影響が出ていることを知り、近年まれに見る大震災であることを実感しました。
私と一緒に講習に参加していたボランティアスタッフ3人と今後について話し合いました。「自宅に帰ろうにも、電車がストップしているのだから、今は自分たちのできることをやろう」との結論になり、学校から一番近くにある赤十字の支部へ行くことにしたのです。
大勢の帰宅困難者が行き交う道をもみくちゃにされながら、新大久保にある赤十字の東京支部に到着したときは、すでに夜でした。
支部の1階のロビーには、予想通り200人以上の帰宅困難者が避難場所を求めて集まってきていました。支部に詰めていた職員らの指示を受け、避難者に食べ物や飲み物を配ったり、病気の人がいないか声をかけて回ったりと、できるかぎりのサポートをしているうちに深夜になり、その日は支部に宿泊することになったのです。
開かないドア、傾いた床……半壊した自宅を共済金で修理する
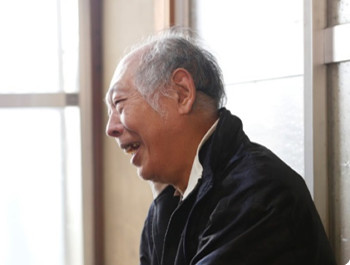
翌日から電車は正常に動き始めていたので、いつでも帰ることはできたのですが、赤十字の支部で雑事に追われているうち2日、3日と過ぎてしまい、結局帰宅できたのは4日目の朝でした。
自宅に着いて最初におかしいと思ったのは入口のドアでした。鍵を差し込んでノブを回しても開きません。よく見ると地震のせいでドアの枠が歪んでいました。ノブを力いっぱい引いて中に入ると、床が傾いた場所があったり、本棚が倒れた場所にあったガラス戸が割れて破片が散らばっていたりとさんざんな状態でした。
他人の心配をしているうちに、自分の家がこんな目にあっているとは思ってもみませんでした。すぐに知り合いの大工さんを呼んで修理をしてもらうことにしたのです。
全労済に連絡を入れたのは、震災から半年くらい経ってからだったと記憶しています。修理をしてくれた大工さんから「保障には入っているの? それならダメもとでいいから聞いてみなよ」と言われて全労済に加入していたのを思い出しました。
電話をかけると「すぐにお伺いします」との返事で、それから2~3日ほどで担当者が訪ねてきてくれました。
担当者とのやりとりで覚えているのは、家の中に入ってすぐ立ちくらみをされていたこと。他人の目からは、平衡感覚が変になるくらい床が傾いたのだと実感した瞬間でした。半壊との審査認定となり、後日共済金を振り込んでいただきました。対応がスムーズだっただけでなく、入口のドアや部屋の傾きなど自宅の修理に共済金がたいへん役立ちました。本当にありがたかったですね。
自分ができることで、これからも社会に貢献したい
2人の娘が結婚して家を離れ、20年前に妻が他界してから“一匹狼”の暮らしです。昔から「人の上に立つより人のためになることをしたい」という気持ちがあり、さきほど話した赤十字のほかにも、自治会の役員や社会福祉協議会の福祉委員、介護施設のボランティアなど、あちこち駆け回っていますね。
趣味は「ノルディック・ウォーク」で、かれこれ10年以上になります。活動を推進する連盟に所属して試験を受けているうちに「ノルディック・マイスター」という指導者を育成できる資格を持てるくらいになりました。2本のポールを使って歩くのですが、健康にいいし、けがはしにくいし、シニアの健康維持にぴったりだと思います。

人のためになることで世の中に貢献したいのはもちろんですが、そのためには健康維持が欠かせません。健康維持とボランティアの両輪で毎日がんばりたいです。
※ノルディック・ウォーク…フィンランドで生まれた2本のポールを使ったウォーキング・スタイル。クロスカントリー選手の夏場のトレーニングとして活用されたのが始まりで、その後、全身運動効果の高いエクササイズとして日本を含め世界各地に広まった。
編集後記
忙しくも充実した毎日を過ごしているとお話されていた中島さん。写真撮影の間は、いろいろなポーズをとってカメラマンを楽しませてくれました。人のためになることで人を喜ばせたいという、その素敵な考え方や行動が、多くの人に頼りにされる理由なのだろうと強く感じたインタビューでした。

