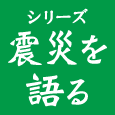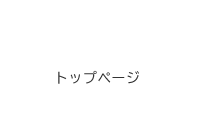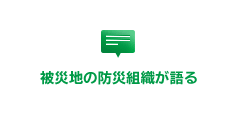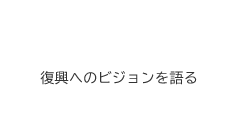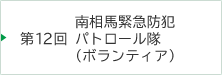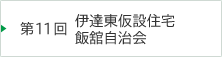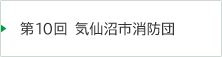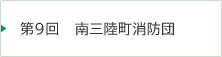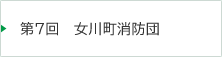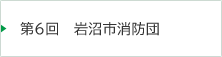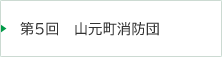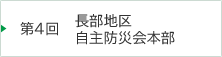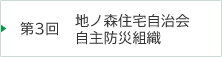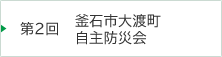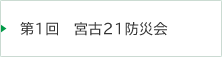- PROFILE
- 宮城県の中部に位置する東松島市。日本三大渓のひとつである嵯峨渓を有する風光明媚な土地だ。市長が「安全・安心なまちづくり」をかかげていることもあり、防災意識を高める活動が盛んな地域でもある。かねてから大地震が起きて、津波が来るということも予想されていた。そのため、地域のコミュニティセンターに災害科学の専門家である東北大学大学院の今村文彦教授を招き、学校関係者や自主防災組織、市議会議員なども参加して、防災の講習会を行うなどもしていた。防災マニュアルが90%できていた状態での、東日本大震災。それは、すべてが想定外だった。震災当時の様子を、消防団長の雫石さんにうかがった。

港から住宅地を抜け、船が運河まで流されてきた
消防団ではいつも、消防や水防の訓練をしていました。津波が来るといっても、せいぜい2mくらいだといわれていたんです。あの日は、すべてが特別でした。地震後、電気をはじめとするライフラインがすべてストップ。そして46分後には津波が来ました。早く逃げれば助かることは、みんなわかっています。しかし、まさかここまで来ないだろうというところに津波が到達したので、対応しようがなかったのです。全体で死者は1,000人を超え、全住宅の3分の2以上が全半壊しました。消防団員も8名が殉職しました。主に、避難誘導、人命救助、水門操作中に亡くなっています。水門も3mしかないんです。この津波に対しては意味をなしませんでした。

遺体を捜索する仕事も消防団が請け負った
この非常事態に、消防団員も人命救助活動に奔走しました。しかし、海岸から流れてきた松の木で国道が完全に封鎖されている。この事態も想定外で、これまでつくっていた救助のマニュアルでは対応できないことがわかりました。地域の方が歩いて市役所まで来て、「あのあたりに被災者がいるらしい」と伝え、また消防団員が歩いて現場に向かう。1日がかりの救助になり、すでに亡くなってしまっている方もたくさんいました。そんな体験から、震災後トラウマを抱える消防団員も出ています。団員の心身の健康管理も、今後の課題です。

復興だけでなく高齢化の進む地域の活性化も課題
溺れている人がいたら助けるのが消防団員です。無理だと思っても、水に飛び込んでいく。今、消防団員の安全マニュアルをあらためて作成していますが、どこで活動を線引きすればいいのか、結論は出ていません。また、消防団員の中には、この震災で仕事と家の両方をなくし、県外に出ていってしまっている人もいます。これまでのメンバーで、活動していくのは難しいでしょう。地域全体でも、高齢者は地元に残りたいと願い、若い家族は出ていってしまう。農業の後継者不足も深刻です。行政の力を借りながら、みんなで頑張っていくしかありません。
-
 救助活動で、必要を感じたものはありますか。
救助活動で、必要を感じたものはありますか。
-
 連絡を取るための無線機です。電話はすべて通じなくなりました。電気がないので、携帯電話も充電できないのです。発電機で無理に充電すると、電圧が低いためバッテリーが壊れてしまうことも。車から充電できるアダプターを購入する人が増えたようです。
連絡を取るための無線機です。電話はすべて通じなくなりました。電気がないので、携帯電話も充電できないのです。発電機で無理に充電すると、電圧が低いためバッテリーが壊れてしまうことも。車から充電できるアダプターを購入する人が増えたようです。
-
 今、消防団員は何名くらいいるのでしょう。
今、消防団員は何名くらいいるのでしょう。
-
 震災前は650人くらいいたのですが、今は名簿上で620人程度、実際に活動できるのは400?450人ほどでしょうか。消防団も高齢化が進んでいるため、新しく若い団員を募集したいですね。今後は女性団員も増やしていきたいと考えています。
震災前は650人くらいいたのですが、今は名簿上で620人程度、実際に活動できるのは400?450人ほどでしょうか。消防団も高齢化が進んでいるため、新しく若い団員を募集したいですね。今後は女性団員も増やしていきたいと考えています。

- 消防団の団長としての誇りを感じることができました
-
職や家を失う人、他県へ引越す人による団員減少や若手の団員の減少等さまざまな課題がある中、常に課題を克服していこうという団長の熱い思いに感動いたしました。また、こくみん共済 coop へ期待することとして、地域の活性化のための活動を今後も継続してもらいたいとお言葉をいただき、ありがとうございました。
こくみん共済 coop 総務部 社会貢献推進課 主任
長倉博志
取材協力:東松島市消防団 団長 雫石堅持さん 東松島市 総務部 防災交通課 主事 内海直樹さん
取材日:2012年10月25日