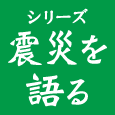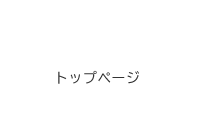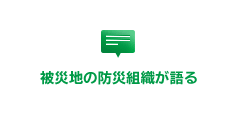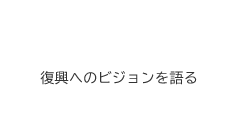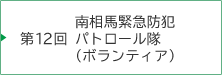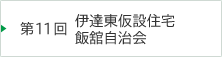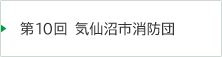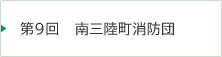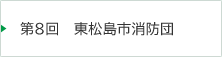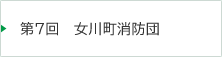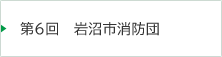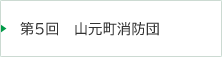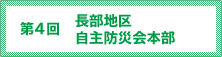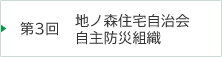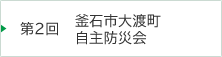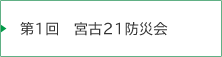- PROFILE
- 陸前高田市は、宮城県の気仙沼市と隣接する三陸海岸沿いの町だ。この地域は津波が多く、2010年のチリ地震でも警報が出され、津波への意識が高まっていた矢先、東日本大震災が起こった。津波で市の中心部は大きな被害を受け、市の全世帯中7割以上が被害を受けた。高田松原の防潮林で1本だけ残った松は「奇跡の一本松」とよばれ、震災後希望のシンボルとなった。陸前高田市の長部地区には、2004年から自主防災組織がある。毎年5月には避難訓練をし、緊急時の役割分担も事前になされていた。それが震災時にどう機能したのか、自主防災会本部会長の菅野さん、長部地区コミュニティ協議会事務局長の小泉さんにうかがった。

30mを超える津波はまったく想定されていなかった
ここは、いつか大きな地震が来るといわれていた地域です。なので、自主防災会では、役割によって班を分け、毎年避難訓練をしていました。まず、班長としてなるべくいつも自宅にいられる方を選出します。そして、災害情報を周知する「情報連絡班」、避難誘導・人命救助にあたる「避難救助班」、炊き出しを行う「炊出給食班」、病人やけが人の手当を行う「救急救護班」をあらかじめ決めていました。震災当日は情報連絡班が大声で避難をうながし、避難救助班は軽トラックでけが人や高齢者などを運びました。通常は車で避難することは勧められませんが、軽トラックであったことと、道が通れたことで結果的に速く救助ができたのです。

自主防災会メンバーは徹夜で避難所の見張りをした
私は消防団に32年いましたが、こんなに大きな津波は初めてでした。震災の3日前にも地震があったのですが、そのときは津波が来なかったので油断していた人もいたようです。また、揺れが収まってから自宅を見に戻って、津波に飲まれた人もいました。津波の中には、がれきや材木が流れています。それにあたってしまうと、もう助かりません。避難所で、夜になってからあまりに寒くて焚き火をしました。それから炊き出しの用意です。ここで、日頃から電気・水道が停止した状態で炊き出しを行う訓練をしていた、炊出給食班が活躍しました。

米がなかったらと思うとゾッとすると語るお二人
国道ががれきで寸断され、実質この地区は1週間ほど陸の孤島となってしまいました。ひとつ幸運だったのは、ガスがプロパンガスだったことです。各家庭や施設などからガスボンベを集め、米を炊きました。米は各家庭に備蓄していたのを集め、自家発電機を動かして精米しました。支援物資が届くというニュースが流れてからも、ここには物資が届かなかったのです。支援は各地域の状況を把握して行ってほしいと感じました。また地域の住民同士も、行政に頼るのではなく、助け合い一緒に組織をつくっていくことが必要です。
-
 避難時、もしくは避難生活中で、必要を感じたものはありますか。
避難時、もしくは避難生活中で、必要を感じたものはありますか。
-
 震災の経験を活かし、各支部にマイクを常備することにしました。やはり、危険をよびかけるにも肉声では限界があります。あとは、救急箱、ふろしきなども、けが人の救助をするときには必要だと感じました。ポータブルトイレも、あると便利です。
震災の経験を活かし、各支部にマイクを常備することにしました。やはり、危険をよびかけるにも肉声では限界があります。あとは、救急箱、ふろしきなども、けが人の救助をするときには必要だと感じました。ポータブルトイレも、あると便利です。
-
 長部地区には7つの支部がありますが、防災意識の差を感じることはありましたか。
長部地区には7つの支部がありますが、防災意識の差を感じることはありましたか。
-
 過去に津波が来たことがある地域とない地域では、だいぶ差がありました。避難訓練の参加実績にもそれは表れています。悲しいことにそれは死傷者の数にも反映されてしまいました。もっと、研修会をやるなど防災意識を高める活動を日頃から行うべきでした。
過去に津波が来たことがある地域とない地域では、だいぶ差がありました。避難訓練の参加実績にもそれは表れています。悲しいことにそれは死傷者の数にも反映されてしまいました。もっと、研修会をやるなど防災意識を高める活動を日頃から行うべきでした。

- 助けを待つだけでなく協力して乗り切ろうという姿勢に感動しました
-
陸前高田市は、市街地の家屋建物のほとんどすべてが津波に流されてしまい、そこに町があったことが信じられないほどでした。そのような状況でも、ただ助けを待つだけでなく、みんなでできることからやっていこうと活動されたため、死傷者を最小限に食い止めることができたのではないかと思いました。
こくみん共済 coop 岩手県本部 事業推進部 部長
佐藤雅喜
取材協力:長部地区自主防災会本部 会長 菅野征一さん 長部地区コミュニティ協議会事務局長 小泉正喜さん
取材日:2012年10月10日