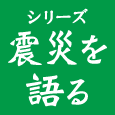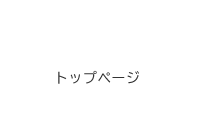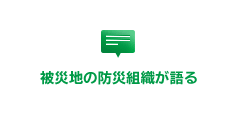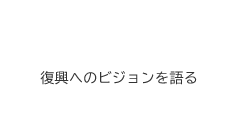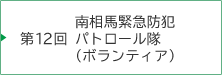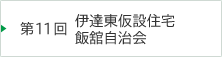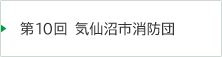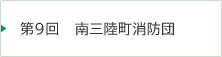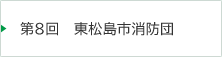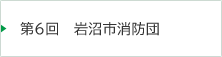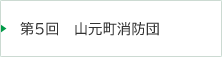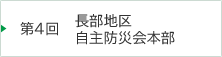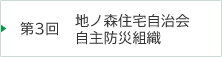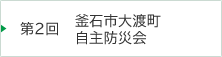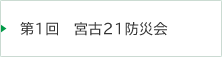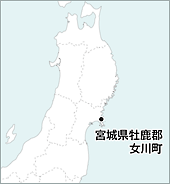
- PROFILE
- 豊かな水産資源に恵まれたリアス式海岸と、日本屈指の女川漁港を有する女川町。町中心部から約16km、太平洋に面した場所に女川原子力発電所がある。東日本大震災では、最大高14.8mもの津波に襲われたが、高台にある女川原発は直撃をまぬがれた。「津波が来ることは想定していた」と語る鈴木正文さんは、この町の安全を守る女川町消防団の団長でもあり、地域の行政区長でもある。日頃から高い防災意識を持ち、原子力防災訓練や、離島でのヘリコプター離着陸訓練などのほか、地域への啓発活動を活発に行っていた。今、求められている地域ぐるみの防災意識と、消防団の活躍について、鈴木さんに話をうかがった。

平野部は津波の被害と地盤沈下により壊滅的な状態
浜で仕事をしているときに、震災が発生しました。みんなに「避難しろ」「戻るなよ」と声をかけながら自宅に戻り、車で役場へ向かいました。私が住んでいる地域には約80名の住民がおり、高齢者も多いので心配でした。震災の翌日、全員が無事だという知らせが入ったときには、本当に嬉しかったですね。毎年、地域の総会で、「津波が来たら、高台に逃げろ」とくり返し伝えてきました。このくり返しが大事なんです。特に高齢者は、ふだん行きなれた集会所に避難しようとするので、丁寧に、正確に「津波が来たら高台」と伝えなければいけない。あわせて、広報誌やチラシでの啓発や、ふだんの声かけを積極的に行ってきました。

「町をまとめ孤立を防ぐことが大事」と鈴木さん
女川は壊滅的な被害を受けましたから、仮設住宅を建てるための土地が足りず、300世帯の住民が、石巻の仮設住宅に移り住んでいます。地元への愛着から、女川の団員たちが、火の用心のステッカーやチラシを配りに行くだけでも「顔を出してくれて安心した」と喜ばれます。「何かあったら、女川の消防団に来てほしい」とも言われるのですが、石巻の管轄なので、不都合もあります。例えば、消火栓は石巻のものですから、女川の消防団が勝手に使うわけにはいきません。そこで、仮設住宅に住む人たちによって、自営消防団を結成する計画を立てています。

復興への一歩として土地のかさ上げ工事が始まった
震災後、約10名の団員が入団しました。40代の新規入団もあり、これは過去にはなかったことです。今回の消防団の活動を目の当たりにした地域の皆さんが、「消防団に協力したい」と思ってくれたんですね。一方で、就業や子どもの教育の問題から、女川を離れた団員たちもいます。増えた団員よりも、減った団員のほうが多いため、団員の確保が課題となっています。「戻りたい」という連絡をくれる団員もいるのですが、仮設住宅の空き待ちが80名以上いて、戻りたくても戻れないのが現状です。国の復興整備が進むことを願っています。
-
 震災直後の消防団の活動について教えてください。
震災直後の消防団の活動について教えてください。
-
 人命捜索や遺体収容作業にあたったのですが、正直、目にする光景が日を追うごとにつらくなっていきました。作業の合間にも余震が続き、何度も警報が鳴り響きます。離島や半島ではさらに危険が大きいため、団員たちがお互いを見渡せる範囲のみで活動しました。
人命捜索や遺体収容作業にあたったのですが、正直、目にする光景が日を追うごとにつらくなっていきました。作業の合間にも余震が続き、何度も警報が鳴り響きます。離島や半島ではさらに危険が大きいため、団員たちがお互いを見渡せる範囲のみで活動しました。
-
 震災の前と後で、思いや行動に変化はありましたか。
震災の前と後で、思いや行動に変化はありましたか。
-
 地域の人たちに頼りにされていることを実感しました。震災後、女川の中学生が「防火防災に関する作文コンクール」で最優秀賞を受賞しました。作文には、消防団への感謝の言葉が綴られていて、胸が熱くなりましたね。これからももっと頑張ろうと思いました。
地域の人たちに頼りにされていることを実感しました。震災後、女川の中学生が「防火防災に関する作文コンクール」で最優秀賞を受賞しました。作文には、消防団への感謝の言葉が綴られていて、胸が熱くなりましたね。これからももっと頑張ろうと思いました。

- 自らよりもまず町を助けたいという強い思いと決意を感じました
-
平成23年度「防火防災に関する作文コンクール」の最優秀賞作には「自らが被災しているにもかかわらず、町のために働いてくれる消防団はとても頼もしい存在だった」ということが書かれていました。女川町消防団の、自らよりもまず町を助けたいという強い思いが、住民にも勇気を与えたのだと思います。
こくみん共済 coop 総務部 社会貢献推進課 主任
加藤麻実子
取材協力:女川町消防団 団長 鈴木正文さん 女川町 企画課防災係 災害対策本部事務局 係長 阿部清人さん
取材日:2012年10月23日