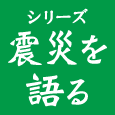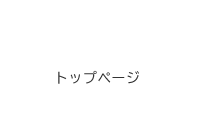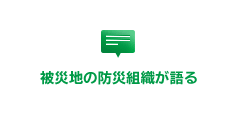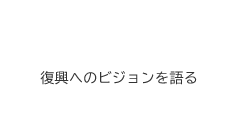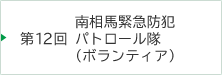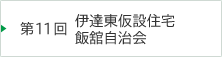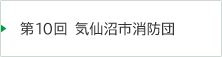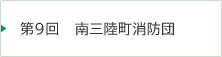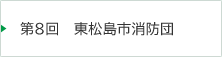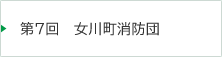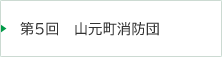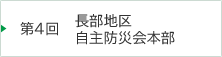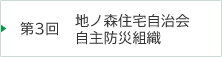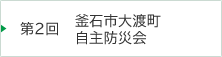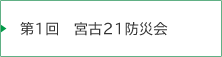- PROFILE
- 宮城県の中央部、仙台市の南17.6kmに位置する岩沼市。太平洋に面した町を津波から守るため、高さ7.2mの海岸堤防を築いていた。しかし、東日本大震災で発生した津波は、この堤防を軽々と越えて町を襲った。高い建物が少ない同市では、太平洋岸からわずか2kmにある仙台空港や、仙台東部道路が急遽、避難場所となったという。「堤防があることでかえって油断し、亡くなった人たちもいた。日頃の防災意識が命運を分けた」と岩沼市消防団の団長 田村善洋さんは語る。地震発生から津波到達までの間、岩沼市消防団の活躍により、多くの命が救われた。そのときの様子と得た教訓について、田村さんにうかがった。

震災直後、何も情報がない中で活動を続けた
津波の犠牲者の大半は、逃げなかった人たちです。2010年にチリ地震が発生したときには、50cm程度の津波しか来なかったので、今回も大丈夫だろうと楽観視した人たちが多かった。防波堤を越える津波なんて来るわけない、と思っていたんです。団員たちはできる限りの説得をしながら避難誘導を行い、震災後には多くの感謝の声をいただきました。しかし、6名の団員が殉職しました。津波が引いた後、消防団の車の座席に、高齢者がシートベルトをした姿で見つかりました。団員が助けようとして車に乗せ、そこで津波に襲われたのでしょう。6名はまじめで一生懸命だったからこそ、ギリギリまで救助を続け、命を落としてしまったのです。

「新規団員を増やすことも課題です」と田村さん
今思うと、まずは団員の安全を確保すべきでした。津波警報が発令された場合、団員は地域の人たちを避難誘導し状況を本部に報告することを、平時より定めていました。しかし、団員の避難基準については、取り決めていなかったのです。今後は、遅くても津波到達の10分前には活動を停止し、高台などの安全な場所に避難するよう取り決めました。また、震災時には携帯電話が不通になったことから、デジタル式の携帯無線機と車載無線機を増設しました。消防本部からの情報が直接届けられるので、状況をリアルタイムで確認しながら活動できます。

消防団も平時の訓練を活かして多くの住民を救った
地震が起きたらとにかく逃げる。また、どこに逃げるか、日頃から意識を持って訓練しておくことが大切です。海から200mの場所にあった老人ホームでは、寝たきりの入居者がいたにもかかわらず、約100名の入居者と40名の職員全員が助かりました。このホームでは常に高い防災意識を持って、地域の人たちと一緒に避難訓練をしていたのだそうです。今回の震災では、想定より高い津波が来ると知り、職員のとっさの判断で、近くの仙台空港に避難場所を変えました。機転を利かせ無事に避難できたのも、訓練していたからこそでしょう。
-
 震災後、地域や消防団の取り組みに変化はありましたか。
震災後、地域や消防団の取り組みに変化はありましたか。
-
 2012年9月に、仙台東部道路を避難場所として訓練を行ったところ、これまでにないほど多くの方が参加されました。震災時、仙台東部道路に逃げて助かった人がたくさんいたので、道路に上る階段を設置し、緊急避難場所として活用できるようにしています。
2012年9月に、仙台東部道路を避難場所として訓練を行ったところ、これまでにないほど多くの方が参加されました。震災時、仙台東部道路に逃げて助かった人がたくさんいたので、道路に上る階段を設置し、緊急避難場所として活用できるようにしています。
-
 救助活動やその他の活動を通して、どんな思いをお持ちでしょうか。
救助活動やその他の活動を通して、どんな思いをお持ちでしょうか。
-
 団員たちも被災者です。家族や家を失った団員もいて、退団届けが出されてもおかしくない状況でしたが、1枚も出されなかった。東北の人間は、朴訥で口に出さない気質です。大変でも何も言わず、ただ一生懸命活動する。そんな団員たちを誇りに思います。
団員たちも被災者です。家族や家を失った団員もいて、退団届けが出されてもおかしくない状況でしたが、1枚も出されなかった。東北の人間は、朴訥で口に出さない気質です。大変でも何も言わず、ただ一生懸命活動する。そんな団員たちを誇りに思います。

- 「まずは団員の安全の確保が重要」が印象的でした
-
以前は「地震が起きたら海を見に行け」と言っていたこともあったそうです。今回の東日本大震災で団員の方が亡くなられた経験から、安全確保の重要性を最も訴えていたことが印象的でした。また、若い入団者が少なく、団員の平均年齢が高齢化していることなど、消防団の課題についても語っていただきました。
こくみん共済 coop 宮城県本部 事業推進部 部長
白川尚正
取材協力:岩沼市消防団 団長 田村善洋さん 岩沼市消防本部 総務課長 司令 相原照義さん 岩沼市消防本部 総務課 主幹兼係長 村上良幸さん
取材日:2012年10月17日