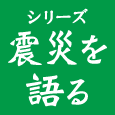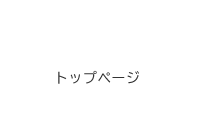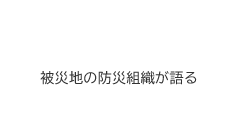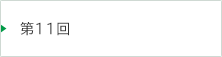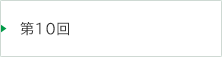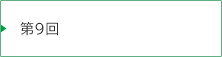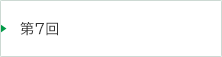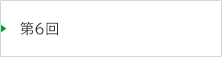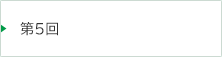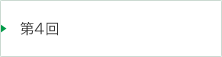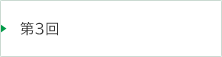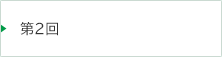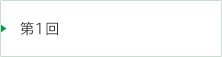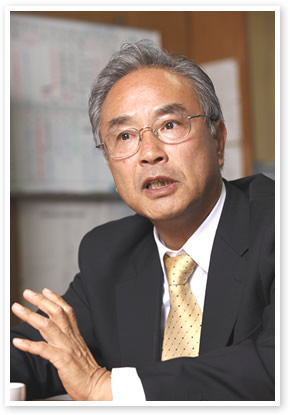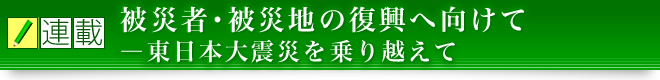
“スタンド・バイ・ミー”の思いで、子どもたちへの支援を続ける
「すたんどばいみー」 チュープ・サラーンさん、NPO法人教育支援グループ「Ed.ベンチャー」/神奈川県大和市立引地台中学校校長 柿本隆夫さん
3月11日に東日本をおそった未曾有の大震災。地震と津波の甚大な被害に加え、福島第一原子力発電所の事故による二次被害が震災をさらに深刻なものにしているのが現状です。
こうした状況の下、私たちに何ができるのでしょうか。
本連載では、東日本大震災の復興に向けた様々な取り組みやビジョンをレポートすることで、よりよい復興に対する理解と議論を深めていきたいと考えています。
神奈川県大和市を中心に、在日外国人の子どもたちへの教育支援活動を続けるNPO法人「Ed(エド).ベンチャー」のメンバーである大和市立引地台中学校校長 柿本隆夫氏と外国人当事者グループ「すたんどばいみー」のチュープ・サラーンさんに、岩手県陸前高田市と宮城県石巻市の子どもたちへの支援活動について聞きました。
 外国人の子どもたち自らがグループを結成、それを日本人が支援
外国人の子どもたち自らがグループを結成、それを日本人が支援
「すたんどばいみー」と「エドベンチャー」の設立経緯や活動について
教えて下さい。
 神奈川県大和市と横浜市にまたがる県営いちょう団地には、インドシナ難民や中国帰国、南米日系人など多くの外国人が住んでいます。そこで行われていた学習支援教室で出会った子どもたちが自分たちのグループを作ろうと、2001年に「すたんどばいみー」を結成しました。当時私は中学3年生でしたが、周りの外国籍のお兄さんやお姉さんは学校に行かなかったり、薬物に手を出したりしていて、高校や大学に進む人はいませんでした。私と数人の仲間は高校にも行きたかったので、自分たちでやれることをやっていこうと思い、作りました。
神奈川県大和市と横浜市にまたがる県営いちょう団地には、インドシナ難民や中国帰国、南米日系人など多くの外国人が住んでいます。そこで行われていた学習支援教室で出会った子どもたちが自分たちのグループを作ろうと、2001年に「すたんどばいみー」を結成しました。当時私は中学3年生でしたが、周りの外国籍のお兄さんやお姉さんは学校に行かなかったり、薬物に手を出したりしていて、高校や大学に進む人はいませんでした。私と数人の仲間は高校にも行きたかったので、自分たちでやれることをやっていこうと思い、作りました。
すたんどばいみーで大事にしていることは「自分たちの言葉を自分たちで残していくこと」です。日本人からではなく、自分たち自身で話し合い、共感でき、自分たちを解放していく場を作りたいと考え、運営してきました。今、すたんどばいみーには20代のカンボジア人、ベトナム人、中国人、アルゼンチン人など15-6人からなる運営スタッフがいて、高校生教室、中学生教室、小学生教室に通ってくる在日外国人の子どもたちに勉強を教えたり、色々な相談に乗ったり、イベントなどもやっています。
 すたんどばいみーには活動を支援する日本人の大人たちがいて、その関わり方はあくまでも、彼らが自主的に自分たちの課題を解決していくのを支えるというものでした。その中で子どもたちが成長し、自分たちで様々なことをやれるようになった時に、「どう手を引くのか」が課題になりました。そこでは、マジョリティである日本人とマイノリティである外国人が、お互い尊重し合い、対等になることを目指す形で、関係を築いていかなければなりません。そのために、私たちは彼らのような外国人との関係では力が強い立場に立っていることを認識した上で、自分たちのグループを作る必要があると考え、2007年にNPO法人教育支援グループ「Ed(エド).ベンチャー」を立ち上げました。ちょうど新自由主義的な政策の中で、子どもたちの間でも貧困や格差が問題になっていました。そこで、外国人だけでなく、弱い立場に立つ子どもたちを日本人の力を集めて支えていくことにしたのです。
すたんどばいみーには活動を支援する日本人の大人たちがいて、その関わり方はあくまでも、彼らが自主的に自分たちの課題を解決していくのを支えるというものでした。その中で子どもたちが成長し、自分たちで様々なことをやれるようになった時に、「どう手を引くのか」が課題になりました。そこでは、マジョリティである日本人とマイノリティである外国人が、お互い尊重し合い、対等になることを目指す形で、関係を築いていかなければなりません。そのために、私たちは彼らのような外国人との関係では力が強い立場に立っていることを認識した上で、自分たちのグループを作る必要があると考え、2007年にNPO法人教育支援グループ「Ed(エド).ベンチャー」を立ち上げました。ちょうど新自由主義的な政策の中で、子どもたちの間でも貧困や格差が問題になっていました。そこで、外国人だけでなく、弱い立場に立つ子どもたちを日本人の力を集めて支えていくことにしたのです。
 現地でニーズを探り、支援しようと4ヶ月間、毎週被災地へ
現地でニーズを探り、支援しようと4ヶ月間、毎週被災地へ
4月初めから被災地への支援活動を始めたと聞きましたが、
どのような経緯があったのでしょうか。
 東日本大震災の発生直後に、神奈川県では被災者を受け入れる家庭を募集しました。そこで私たちは地域単位で受け入れようという提案を県にしたのですが、何も返事がなく、埒があきませんでした。そこで行政を通してではなく、直接ピンポイントで受け入れようと、以前個人的によく行っていた岩手県陸前高田市の県営「モビリア」オートキャンプ場に支援物資を積んで行きました。
東日本大震災の発生直後に、神奈川県では被災者を受け入れる家庭を募集しました。そこで私たちは地域単位で受け入れようという提案を県にしたのですが、何も返事がなく、埒があきませんでした。そこで行政を通してではなく、直接ピンポイントで受け入れようと、以前個人的によく行っていた岩手県陸前高田市の県営「モビリア」オートキャンプ場に支援物資を積んで行きました。
そうすると、とんでもない思い違いをしていたことが分かりました。足りないと思っていた物資はすでにたくさん集まっていましたし、避難してもらおうと思った子どもや高齢者などは地域で支え合って、親戚や知り合いなどのつてで、被災地外に避難させていたのです。それを見て、今必要なのは直接現地に行って、ニーズを探りながら、被災者の求めることに応えていくことだという結論に達して、すたんどばいみーの若者たちを誘って、行くことにしたのです。
 4月16日に、初めてモビリアの避難所に行きました。そこで印象的だったのは、大人たちは会議などで結構忙しそうにしているのですが、子どもたちは会議が始まると、そこにはいられないという雰囲気になり、寒々とした屋外に出て行くことでした。彼らに「何しているの?」と聞くと、初対面なのに「家族は何人?」「国籍はどこ?」などと興味を持って、いろいろ聞かれました。そんな会話の中で、子どもたちは「実はおじいちゃんが津波で流された」「お兄ちゃんが流された」などと、ぽろっと話すのです。それを聞いて、どう返事してよいのか分からず、詰まった人もいたのですが、運営スタッフで話し合い、できる限り通い続けて、子どもたちを支えようということになりました。
4月16日に、初めてモビリアの避難所に行きました。そこで印象的だったのは、大人たちは会議などで結構忙しそうにしているのですが、子どもたちは会議が始まると、そこにはいられないという雰囲気になり、寒々とした屋外に出て行くことでした。彼らに「何しているの?」と聞くと、初対面なのに「家族は何人?」「国籍はどこ?」などと興味を持って、いろいろ聞かれました。そんな会話の中で、子どもたちは「実はおじいちゃんが津波で流された」「お兄ちゃんが流された」などと、ぽろっと話すのです。それを聞いて、どう返事してよいのか分からず、詰まった人もいたのですが、運営スタッフで話し合い、できる限り通い続けて、子どもたちを支えようということになりました。
それ以降、8月末まで丸々4ヶ月、交代で毎週末、モビリアに行きました。金曜日の夜出発すると、土曜日の朝8時半に現地に着くので、そこで4歳から中学2年生まで、12-3人の子どもたちに声をかけて、一緒に遊び、勉強し、午後は調理などのイベントをやり、日曜日の夜9時か10時に大和に帰ってくるという繰り返しでした。
 支援される側のことを想像し、ぎりぎりのところまで無理をする
支援される側のことを想像し、ぎりぎりのところまで無理をする
 エドベンチャーの大人たちが車を運転して、乗せて行きましたが、現地では役割をはっきり分けて、エドベンチャーは学校支援を行いました。津波で流された中学校が小学校に間借りする形で、学校を再開していった時に必要な物資や教材を届ける活動です。5月21日からは、陸前高田の学校回りは土曜日の昼頃に終わらせ、100km南下して、宮城県石巻市の万石浦中学校の避難所で活動しました。石巻市には神奈川県職員が交代で避難所運営のために入っていて、「子どもたちが荒れているので、見てくれるグループを探している」といわれ、行ってみることにしたのです。
エドベンチャーの大人たちが車を運転して、乗せて行きましたが、現地では役割をはっきり分けて、エドベンチャーは学校支援を行いました。津波で流された中学校が小学校に間借りする形で、学校を再開していった時に必要な物資や教材を届ける活動です。5月21日からは、陸前高田の学校回りは土曜日の昼頃に終わらせ、100km南下して、宮城県石巻市の万石浦中学校の避難所で活動しました。石巻市には神奈川県職員が交代で避難所運営のために入っていて、「子どもたちが荒れているので、見てくれるグループを探している」といわれ、行ってみることにしたのです。
そこで感じたのは、エドベンチャーの大和市での活動と同じ、当事者性の問題でした。支援する側は「できることをやろう」というわけですが、それはあくまで支援する側の論理であって、被災者(支援される側)のものではありません。支援する側が支援される側になることはできませんが、支援される側のことを想像することはできます。そういう形で、支援する側が当事者性を持たないと、ニーズといっても、支援される側の状況や気持ちを無視した言葉だけのものに終わってしまいます。そこで私たちには、被災者の状況を思い、ぎりぎりのところまで無理しようと考えて、毎週、陸前高田と石巻両方に行くのは実に大変だったのですが、万石浦での活動にも引きずり込まれるように入っていきました。
石巻・万石浦ではどのような活動をしたのでしょうか。
 陸前高田と石巻は全く状況が違っていました。陸前高田は避難所や仮設住宅に地域がまとまる形で入っていたので、コミュニティが維持されており、子どもたちもその中にいました。それに対して、石巻は合併で、仙台に次ぐ、宮城県で2番目の人口を持つようになった都市です。被災地域と被災していないところの違いも明確で、避難所や仮設住宅にもバラバラに入っています。そうした中で、避難所になっている体育館で、子どもたちは騒ぐと怒鳴られるし、居場所もなく、子ども同士でもうまく遊べないような状況でした。
陸前高田と石巻は全く状況が違っていました。陸前高田は避難所や仮設住宅に地域がまとまる形で入っていたので、コミュニティが維持されており、子どもたちもその中にいました。それに対して、石巻は合併で、仙台に次ぐ、宮城県で2番目の人口を持つようになった都市です。被災地域と被災していないところの違いも明確で、避難所や仮設住宅にもバラバラに入っています。そうした中で、避難所になっている体育館で、子どもたちは騒ぐと怒鳴られるし、居場所もなく、子ども同士でもうまく遊べないような状況でした。
そこに行ったわけですから、子どもたちは私たちに対して、殴る、蹴る、棒でたたく、石を投げつけるなどの行動を繰り返しました。何回行っても、同じなので、私たちも相当疲れてしまったのですが、7月末に修学旅行に行くことを企画した時から、様子が変わってきました。修学旅行という目標に向け、その準備や約束事を決めていく中で、子どもたちの集団性が出てくるようになり、私たちに対する暴力が少なくなっていったのです。
 気持ちを言葉にすることで、後から振り返ることができる材料を残す
気持ちを言葉にすることで、後から振り返ることができる材料を残す
-
すたんどばいみーは9月10日に陸前高田での活動に一区切り付けるイベントを開いたと聞きました。どんなことをやったのでしょうか。
 個人的には話していましたが、すたんどばいみーとして、子どもたちに、自分たちが何者で、どうして日本にいるのかなどの自己紹介をしてきませんでした。そこで子どもたちだけでなく、親にも呼びかけて、自己紹介も含めて、神奈川での活動や外国人として、日本で生きている中で直面している問題などを知ってもらうことにしました。メインプログラムは3月11日に起きたことについての子どもたちの発表でした。私たちは自分たちが感じているが上手に表現出来ずに、“むずむずしていること”を言葉に落として、発表する作業を10年間やり続けてきました。そこで得たものの大きさを考えると、陸前高田の子どもたちも、3月11日当日の行動や感じたことなどを地図に書いたり、文章にすることはいつか必ず役に立つと考えました。
個人的には話していましたが、すたんどばいみーとして、子どもたちに、自分たちが何者で、どうして日本にいるのかなどの自己紹介をしてきませんでした。そこで子どもたちだけでなく、親にも呼びかけて、自己紹介も含めて、神奈川での活動や外国人として、日本で生きている中で直面している問題などを知ってもらうことにしました。メインプログラムは3月11日に起きたことについての子どもたちの発表でした。私たちは自分たちが感じているが上手に表現出来ずに、“むずむずしていること”を言葉に落として、発表する作業を10年間やり続けてきました。そこで得たものの大きさを考えると、陸前高田の子どもたちも、3月11日当日の行動や感じたことなどを地図に書いたり、文章にすることはいつか必ず役に立つと考えました。
感じていることを言葉にするのは、どういう意味があるのでしょうか。
 自分自身を作っていくことです。今はこうした形で質問にも答えることができますが、中学生の頃は言葉で自分を表現することができませんでした。いつも「なんていっていいのだろう」で終わってしまい、自分の中にもやもや感が残りました。それをいちょう団地の学習教室で、日本人の大人たちに支援してもらいながら、一つひとつ言葉に置き換える作業を繰り返す内に、自分の考えていることを言葉にできるようになったのです。ですから、私にとって、もやもやしている感覚を言葉にするのは自分を作っていくことなのです。陸前高田の子どもたちにとって、3月11日の経験は彼らがこれから生きていくベースになるものです。ですから、それを言葉にして、形として残すことで、彼らが大人になった時に振り返る材料にすることができればよいと考えたのです。
自分自身を作っていくことです。今はこうした形で質問にも答えることができますが、中学生の頃は言葉で自分を表現することができませんでした。いつも「なんていっていいのだろう」で終わってしまい、自分の中にもやもや感が残りました。それをいちょう団地の学習教室で、日本人の大人たちに支援してもらいながら、一つひとつ言葉に置き換える作業を繰り返す内に、自分の考えていることを言葉にできるようになったのです。ですから、私にとって、もやもやしている感覚を言葉にするのは自分を作っていくことなのです。陸前高田の子どもたちにとって、3月11日の経験は彼らがこれから生きていくベースになるものです。ですから、それを言葉にして、形として残すことで、彼らが大人になった時に振り返る材料にすることができればよいと考えたのです。
すたんどばいみーの今後の活動についてお聞かせ下さい。
 当初は「子どもたちの発表を集めた冊子を作って終わりかな」と考えていました。ところが、子どもたちの話を聞く中で、「終わりにして、しまっていいのか」という気持ちになり、今はむしろ「冊子を作って、新しく始まってしまった」という感じがしています。何をやるかはまだ決まっていませんが、月に1回は陸前高田に行って、状況の変化をつかむところから始めようと考えています。今も週1回は電話をしてくる中学生もいますし、出会った子どもたちとの関係を大切にしながら、次の一歩を踏み出していくつもりです。
当初は「子どもたちの発表を集めた冊子を作って終わりかな」と考えていました。ところが、子どもたちの話を聞く中で、「終わりにして、しまっていいのか」という気持ちになり、今はむしろ「冊子を作って、新しく始まってしまった」という感じがしています。何をやるかはまだ決まっていませんが、月に1回は陸前高田に行って、状況の変化をつかむところから始めようと考えています。今も週1回は電話をしてくる中学生もいますし、出会った子どもたちとの関係を大切にしながら、次の一歩を踏み出していくつもりです。
 震災が突きつけた問題を解決できる力を持つ大人に子どもたちを育てる
震災が突きつけた問題を解決できる力を持つ大人に子どもたちを育てる
石巻・万石浦はどうでしょうか。
 言葉の問題でいえば、今までは、あえて言葉にしないというやり方でやってきました。子どもたちは皆、大人でさえ誰も経験したことのない大変な体験をしました。これは彼らがこれから生きていく上での根本にかかわる問題なので、それを簡単に言葉にして、マイナスのままで固定してしまうのが怖いと考えました。また、気持ちが荒れている中で、言葉にしてしまったら、乗り越えられない経験として、積み重なっていくことも恐れたのです。
言葉の問題でいえば、今までは、あえて言葉にしないというやり方でやってきました。子どもたちは皆、大人でさえ誰も経験したことのない大変な体験をしました。これは彼らがこれから生きていく上での根本にかかわる問題なので、それを簡単に言葉にして、マイナスのままで固定してしまうのが怖いと考えました。また、気持ちが荒れている中で、言葉にしてしまったら、乗り越えられない経験として、積み重なっていくことも恐れたのです。
11月上旬に、子どもたちと松島や仙台空港にバスで遠足に行きました。その時、被災地域を通ると、子どもたちが初めて「あそこでおばあちゃんが流されて、崩れている崖につかまって助かった」などと言い始めたのです。これは大変大きな変化で、言葉にする準備ができ始めているのかなという気がしています。それを外から来た大人に対してではなく、子どもたち自身で言い合い、聞き合うことができるようになることが、将来、石巻復興の原動力になる子どもたちにとって、絶対に必要なことだと思います。7月末の修学旅行以来、振り返りということで、エドベンチャーの大人が18人ぐらいの子どもと1対1で話をしていますが、これからは子どもと子ども、地域の大人と子どもが話しをできるようにしていきたいと考えています。
陸前高田やその他の地域への支援はどうでしょうか。
 陸前高田では元教員や現地スタッフの人たちと一緒にNPOを立ち上げます。その団体で補助金を申請して、学校予算がない中で、必要になっているチョークやクリップなど細かい消耗品や教材などを現地の業者に発注して、学校に納め、教育現場で役立ててもらいます。また、8月に福島県富岡町教育委員会から原発事故で避難した三春町で地域の象徴として学校を作りたいので、支援して欲しいという要請があり、顕微鏡などを提供しました。富岡町は陸前高田、石巻とも違って、ベースになる地域そのものがなくなっている状態なので、支援の仕方が難しく、備品提供など、できることをやっていく考えです。
陸前高田では元教員や現地スタッフの人たちと一緒にNPOを立ち上げます。その団体で補助金を申請して、学校予算がない中で、必要になっているチョークやクリップなど細かい消耗品や教材などを現地の業者に発注して、学校に納め、教育現場で役立ててもらいます。また、8月に福島県富岡町教育委員会から原発事故で避難した三春町で地域の象徴として学校を作りたいので、支援して欲しいという要請があり、顕微鏡などを提供しました。富岡町は陸前高田、石巻とも違って、ベースになる地域そのものがなくなっている状態なので、支援の仕方が難しく、備品提供など、できることをやっていく考えです。
教員という立場で考えると、今、全国で被災地のがれきの中から教育を見つめ直すことが求められていると思います。3・11の大震災は、地域コミュニティ、原発、地方と都市の問題など、今まで考えたこともなかった課題を私たちに突きつけました。それらを解決し、これからの社会を作っていくのは、被災した子どもたちと被災していない子どもたちです。彼らが大人になって出会った時に、マイノリティの在日外国人も含めて手を携えていけるように、3・11の記憶が鮮明な内に、学校も動き出していかなければならないと思います。