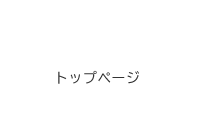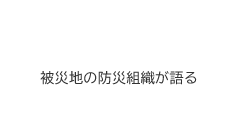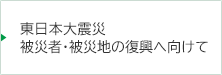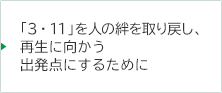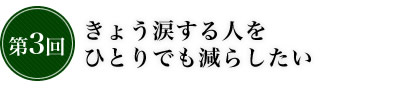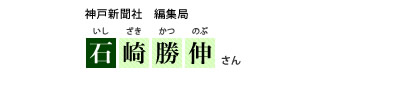1995年に起こった阪神・淡路大震災。
6,434名に及ぶ死者をはじめ、被災した多くの人たちは深い悲しみと大きな打撃を受けました。また、震災の爪痕は深く、15年経った今なお、その被害に苦しんでいる人々も多くいます。一方で、この数年を見ただけでも、全国各地で地震や集中豪雨、台風による災害が発生し、多くの犠牲者が出るなど、阪神・淡路大震災の教訓を生かすことは極めて重要になっています。
「阪神・淡路大震災から何を学ぶか」というテーマで、12回にわたって、その教訓を明らかにしていきたいと思います。

 「役立たず」を意識して話を聞き続けた現場での取材
「役立たず」を意識して話を聞き続けた現場での取材
石崎さんは入社直後に震災に遭ったと聞きました。
どんな状況だったのでしょうか。
 入社3年目で兵庫県加古川市の東播総局(現東播支社)勤務でしたが、応援に行くことになり、震災発生翌日の1月18日に六甲山の裏側から10時間ぐらいかけて、神戸市に入りました。それまでも悲惨な事件事故の現場を見てきましたが、驚きの連続でした。見渡す限り家がつぶれていて、遺体が次々に運び出される中で遺族が号泣する声があふれ、ビルは倒れて、高架の高速道路はひっくり返っていました。
入社3年目で兵庫県加古川市の東播総局(現東播支社)勤務でしたが、応援に行くことになり、震災発生翌日の1月18日に六甲山の裏側から10時間ぐらいかけて、神戸市に入りました。それまでも悲惨な事件事故の現場を見てきましたが、驚きの連続でした。見渡す限り家がつぶれていて、遺体が次々に運び出される中で遺族が号泣する声があふれ、ビルは倒れて、高架の高速道路はひっくり返っていました。
神戸の東隣の芦屋市を担当して取材したのですが、当時多くの学校が避難所になる中で、取材に行った、ある中学校では教室のドアを開けると、棺おけがぎっしり並んでいました。そして、次の教室もその次もと、どの教室も棺おけがぎっしりで、申し訳程度に白い花が置かれているのです。ぽつりぽつりと到着する遺族に何か聞こうと思っても、何を言ったらよいのか、言葉が出ません。「今のお気持ちは」と聞くテレビ局の取材クルーもいましたが、私は一緒に泣くことしかできませんでした。その時、この街は永遠に悲嘆に暮れる、この先10年、20年笑いがひとつもない街になってしまうのではないかと思いました。また、神戸・阪神間にはロープが張られて、「昔、街だったところ」と表示されているというSF映画さながらの想像をしました。被害の状況はそれほどひどかったのです。
その時、新聞記者として、どうお考えになりましたか。
 神戸新聞社自体も壊滅的な打撃を受けました。JR三ノ宮駅前の本社は大破、家族を亡くした社員がたくさんいて、販売店もつぶれ、新聞を出せるかどうかも分かりませんでした。そうした中でも、報道の使命として、話を聞かなくてはいけない、伝えなくてはいけないとは考えていました。しかし、号泣する疲れ切った遺族に何が聞けるというのでしょうか。その時、強烈に思ったのは「役立たず」ということでした。現場に入るレスキュー隊や医者は命を救い、人々を助けるわけですが、自分のような記者には何もできないのです。
神戸新聞社自体も壊滅的な打撃を受けました。JR三ノ宮駅前の本社は大破、家族を亡くした社員がたくさんいて、販売店もつぶれ、新聞を出せるかどうかも分かりませんでした。そうした中でも、報道の使命として、話を聞かなくてはいけない、伝えなくてはいけないとは考えていました。しかし、号泣する疲れ切った遺族に何が聞けるというのでしょうか。その時、強烈に思ったのは「役立たず」ということでした。現場に入るレスキュー隊や医者は命を救い、人々を助けるわけですが、自分のような記者には何もできないのです。
悲嘆に暮れている中で、話を聞かれるというのは、とてもしんどいことです。それを分かった上で、「何の役にも立たないが、これで飯を食っているんだから」と自分に言い聞かせながら、被災者の1人として歩き回って、泣きながら被災者のつぶやきを聞き、目に見えるものを書き留めていきました。
一方で、メディアが頼りにされるという状況も生まれました。行政をはじめ、被害の全体状況を誰もつかめない中で、被災者の様子を外に発信することで、海外からも救援チームが入ってきたり、義援金や救援物資が届きました。また後から聞いた話ですが、家が燃えている中、断水で消火活動ができない消防隊員がぼうぜんとするかたわらで、「水がないなんて、おかしいんとちゃう。お願い、はよ神戸新聞に連絡してよ」とテレビカメラに向かって叫んでいた女性がいました。行政機能がまひし、訴えるところがなくなった時に、社会に訴えるしかないとメディアへの期待が高まったのだと思います。
さらに、記者たちは新聞の束を抱えながら、避難所での取材を続けました。避難所では新聞の束を置いた途端、開いているスーパーや銭湯の場所など人々は生きていくために必要な情報を食い入るようにして、探していました。この時ほど、メディアが人の役に立っているのだと感じたことはありません。
 復旧、復興から漏れる人の声をすくい上げ、社会に発信
復旧、復興から漏れる人の声をすくい上げ、社会に発信
その後、現在まで神戸新聞は震災報道を続けてきていますが、
その中で伝えたいことは何なのでしょうか。
 永遠に悲しみに暮れる街になると思っていたのが、ハード面は急ピッチで復旧、復興していきました。その中で暮らしている人々が少しでも笑えるようになるためのバックアップができればと思って、取材を続けてきました。ただ地震による直接被害を生き延びた人たちでもたくさんの人たちが亡くなっていて、その人たちを救えなかったという無念さは今でも感じています。
永遠に悲しみに暮れる街になると思っていたのが、ハード面は急ピッチで復旧、復興していきました。その中で暮らしている人々が少しでも笑えるようになるためのバックアップができればと思って、取材を続けてきました。ただ地震による直接被害を生き延びた人たちでもたくさんの人たちが亡くなっていて、その人たちを救えなかったという無念さは今でも感じています。
地震から2ヵ月ほど経ったころ、寒い日が続き、長引く避難生活で体調を崩す人がたくさん出るようになりました。その状態について、医者に取材すると「このままでは命さえ危ない」と言われました。それで「今のままでは避難所で、ストレスや体調悪化で亡くなる人は500人に上る」という記事を大きく新聞に載せました。行政は「そんな推測記事はむちゃくちゃだ」と言いましたが、実際には震災発生後に体調を崩して亡くなった震災関連死は900人以上に上りました。震災関連死は阪神・淡路大震災以前にはなかった概念で、記者たちの現場取材の中で初めて明らかにされたわけですが、長引く避難生活やストレスによる病気、自殺などで、たくさんの人が亡くなっています。その後、2004年10月に起きた新潟県中越地震では68人の方が亡くなりましたが、その内関連死が52名と4分の3以上を占めました。私も取材に行きましたが、阪神・淡路大震災と同じことが繰り返されるのは本当に悔しくて、救える命を救えなかったという申し訳なさ、無念さは今も心の奥底に残り続けています。
一方、震災で障害を負った人もいます。震災発生直後の避難所で車いすに乗った人がいて、「大変だなあ」と思ったのですが、「いや、待てよ。震災でけがをして車いすになったということもあり得るな」と考えて、取材を始めました。その時点では、多くの人は障害者手帳を申請していないので、役所では分かりません。そこで、あちこちの病院を回り、もともと知的障害がある中で、母子家庭でお母さんを亡くして、自分は足を切断した人ら多くの人の話を細かくリポートしました。障害者全体については自治体が障害者手帳で把握していますが、「障害の原因によって支援に差を付けることはしない」という理由で、震災が原因で障害を負った人を抽出してはいません。しかし、震災で家がつぶれ、家族を失い、障害を負った人には特別な支援策が必要だと考えて、対策を訴え続けてきました。その結果、震災発生15年を前にした2009年12月になって、ようやく神戸市は障害者手帳から少なくとも183人の震災障害者がいることを把握し、調査を始めました。兵庫県も実態調査に乗り出し、県内全体でその数は約300人に上ることが分かりました。
地震は一瞬で、その発生から16年が経過しようとしていますが、震災障害者の人たちもそうですが、震災という社会的災害は今も続いています。そうした中で、復旧、復興から漏れている人の声を聞き、その実態を明らかにすることで、少しでも社会を変えていくための手助けをすることが私たちの役割だと考えています。
 人と人の助け合い、支え合いの大切さを訴え続ける
人と人の助け合い、支え合いの大切さを訴え続ける
一貫して、人にフォーカスした取材をされているわけですが、
それにはどんな意味があるのでしょうか。
 新聞社で記者を続けていると、発表取材に慣れてしまいます。入社前は「事件事故の取材も含めて、すべて自分の足で稼ごう」と考えていたわけですが、実際にはそれはあり得ません。警察の発表資料がファクスで流れてきて、そこからどこまで突っ込んで、取材するかが仕事になっていきます。しかし、阪神・淡路大震災のような大きな災害になると、行政機関や警察も全体の状況を把握できず、発表では何も分かりません。震災当時は携帯電話もまだ普及していませんでしたから、現場で人の話を聞いて取材し、明治時代の新聞記者のように、落ち合う時間と場所を決めて、そこで情報交換していました。そうした形で避難所で長く取材していたので、何が起きているか、どんなことが見過ごされているのか、人々がどんなことで困っているのかを掘り起こすことができたし、震災関連死や震災障害者の記事も書くことができたのだと思います。
新聞社で記者を続けていると、発表取材に慣れてしまいます。入社前は「事件事故の取材も含めて、すべて自分の足で稼ごう」と考えていたわけですが、実際にはそれはあり得ません。警察の発表資料がファクスで流れてきて、そこからどこまで突っ込んで、取材するかが仕事になっていきます。しかし、阪神・淡路大震災のような大きな災害になると、行政機関や警察も全体の状況を把握できず、発表では何も分かりません。震災当時は携帯電話もまだ普及していませんでしたから、現場で人の話を聞いて取材し、明治時代の新聞記者のように、落ち合う時間と場所を決めて、そこで情報交換していました。そうした形で避難所で長く取材していたので、何が起きているか、どんなことが見過ごされているのか、人々がどんなことで困っているのかを掘り起こすことができたし、震災関連死や震災障害者の記事も書くことができたのだと思います。
当時の神戸新聞の記者たちは追い込まれて、そうした取材をせざるをえない面があったわけですが、その経験はその後の取材活動に生きています。兵庫県は明石市の歩道橋事故や2009年の佐用町の水害など事件事故が多いところですが、現場で話を聞いてメモを取り、記事にするという現場からの発想が何よりも大切だと思います。
震災の記憶を残し、後の世に伝えることはどんな意味があるのでしょうか。
 大きくいって、3つあると思います。
大きくいって、3つあると思います。
1つ目は震災によって傷を受けたり、後遺症を負ったりしたたくさんの人が忘れ去られないようにするためです。
2つ目はこの16年近くの間、あちこちで地震が起き、弱い家がつぶされ、弱い人が取り残されるという阪神・淡路大震災と同じことが繰り返されています。こうした状況を変えるための防災・減災への取り組みを進める目的です。
そして、3つ目が今、一番重要だと考えていることで、一人一人が周囲の痛みや弱さに関心を持って、お互いが支え合っていくためです。震災発生直後は大変悲惨な状況でしたが、金持ちも貧乏人もない、助け合いと支え合いがあり、「人間捨てたものではない」と思える経験をたくさんしました。ところが、その後、回復スピードの人による違いの中で、皆ばらばらになっていきました。そして、震災発生直後の助け合いが負担になり、人間関係が密接なのが逆にしんどいと思ったり、その経験がトラウマになって人間関係が希薄な方が楽だったりという意識がまん延している状況さえあります。
県外に行くと、神戸の人は震災の時に助け合ったから、まちづくりが盛んだったり、助け合いが多かったりするのではないか、と期待も込めて言われます。とんでもありません。逆に震災の時にしんどい思いをしたので、あまり人に頼られたくないという人が多いのが実情です。特に行政主導で行われた区画整理や再開発では住民と行政が対立して非常に紛糾したため、リーダーになった人たちは非常に疲れてしまっていて、その後遺症はとても大きなものがあります。そうした中で、「一人で生きるのだから、放っておいてくれ」と言われれば、それまでですが、人間一人では生きていけないという経験を皆、震災発生直後にはしたわけです。そこで学んだ「人と人とのきずなの大切さ」を伝えていくことが何よりも大切だと思います。
今年の1月18日、阪神・淡路大震災15年翌日の朝刊に、「あの日胸に刻んだ支え合いの大切さを思い起こしたい。将来の災害に備えるためだけではない。きょう涙する人を一人でも減らすために」と書きました(図)。「きょう涙する人を一人でも減らしたい」。私の思いはそこに尽きます。ご近所に救われた、人と人のつながりで助けられた、それを書いていくことで、神戸が自殺防止や孤独死をなくす取り組みの先進地だといわれるようになってほしいと考えています。


-
神戸・三ノ宮で出版社を経営していた高森一徳氏は震災発生から約1ヶ月後の1995年2月中旬、「阪神大震災を記録しつづける会」を立ち上げ、震災に遭った人たちの手記の公募を始めた。「新聞などのマスメディアに載る記事は家族が亡くなったなど人生や生活が激変した人を追ったものが中心です。それに対して、叔父の高森一徳は家族や家は無事でも、親しんできた神戸の街が焼失したことへの思いなど、新聞に載らないような小さな事実こそ記録に残す意味があると考え、その経験を語る場を作ろうと、会を始めました」と阪神大震災を記録し続ける会 事務局長 高森 順子氏は語る。
10年間で1,100編余の投稿が寄せられ、
10巻を出版そして、記録に残りそうもない神戸在住の外国の人たちの手記も集めようと、日本語、英語、中国語、朝鮮語でポスターを作り、学校など避難所や目立つ場所に張り出した。その結果、1ヶ月半で100編以上の投稿があり、95年5月には第1巻の出版にこぎ着けた。出版は当初から、10年間10巻で終了すると決めていたが、10巻までの投稿総数は外国人107編を含む1,134編、採用手記は434編に上る。「手記の内容を見ると、3、4年目が大きな節目です。震災で大変な目に遭ったという体験で共通していたのが、生活の話が全面に出てきます。個々人が置かれている状況が違う中で、経済的な困窮や家の二重ローン、マンション改修問題での対立など人には話しづらいテーマが増えました」(高森順子氏)。
高森一徳氏は2004年12月に急逝したが、計画通り、2005年1月に10巻目の「阪神大震災から10年 未来の被災者へのメッセージ」を刊行して、出版活動は終了した。以降は当初の計画通り、集まった記録の告知を活動の中心に据え、ホームページでの資料の公開や翻訳作業を行っている。2010年2月には震災15周年の集会を開催、今まで手記執筆者同士の横の関係がなかったことから、「何でも話せる場」として、毎年1回集まりを持つことを中心に会としての活動を続けている。
![]()