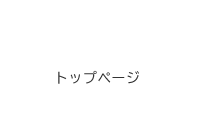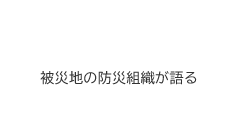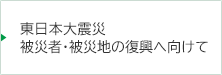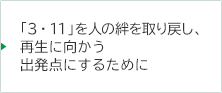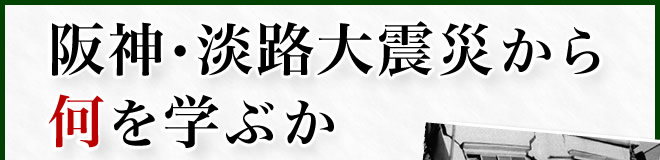
1995年に起こった阪神・淡路大震災。
6,434名に及ぶ死者をはじめ、被災した多くの人たちは深い悲しみと大きな打撃を受けました。また、震災の爪痕は深く、15年経った今なお、その被害に苦しんでいる人々も多くいます。一方で、この数年を見ただけでも、全国各地で地震や集中豪雨、台風による災害が発生し、多くの犠牲者が出るなど、阪神・淡路大震災の教訓を生かすことは極めて重要になっています。
「阪神・淡路大震災から何を学ぶか」というテーマで、12回にわたって、その教訓を明らかにしていきたいと思います。


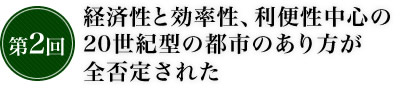
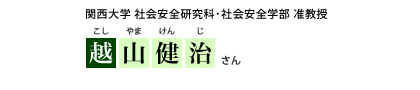
連載第2回は「阪神・淡路大震災とは何だったのか」というテーマで、その被害の特徴について、都市災害対策論が専門の関西大学社会安全研究科・社会安全学部、准教授、越山健治氏に、人的被害やインフラ、都市開発などのそれぞれの側面から、話を聞きました。
 大規模性・都市性・階層性という3つの特徴
大規模性・都市性・階層性という3つの特徴
阪神・淡路大震災の被害の特徴についてお聞かせ下さい。

 大規模性、都市性、階層性の3つがあげられます。1つ目の大規模性とは人が集中的に住んでいる場所が10数秒激しく揺れたことで、10市10町の250-300万人が一瞬にして、日常から非日常の世界に移行して、被災者になったことです。2つ目の都市性とは被害の中心が、1平方キロあたり1万人以上が住んでいる日本有数の人口密集地域であり、かつモダンで先進的な都市として評価の高かった地域であったことす。つまりこれは20世紀に高度に発展してきた都市が持つぜい弱性が明らかになった事例であるといえます。3つ目の階層性とは、住宅の被害と人的被害がリンクしたことにより社会的に弱い立場の人たちが大きな被害にあったということです。都市の中心部に残っていた築40-50年の古い文化住宅や長屋に住む中高年や高齢者、単身者の人たちが大きな被害を受けた災害でした。一般に住宅には収入や財産などの差による階層性が出ますが、地震が早朝に起きたことから住宅被害がそのまま被災者層を形成するという結果となった災害です。
大規模性、都市性、階層性の3つがあげられます。1つ目の大規模性とは人が集中的に住んでいる場所が10数秒激しく揺れたことで、10市10町の250-300万人が一瞬にして、日常から非日常の世界に移行して、被災者になったことです。2つ目の都市性とは被害の中心が、1平方キロあたり1万人以上が住んでいる日本有数の人口密集地域であり、かつモダンで先進的な都市として評価の高かった地域であったことす。つまりこれは20世紀に高度に発展してきた都市が持つぜい弱性が明らかになった事例であるといえます。3つ目の階層性とは、住宅の被害と人的被害がリンクしたことにより社会的に弱い立場の人たちが大きな被害にあったということです。都市の中心部に残っていた築40-50年の古い文化住宅や長屋に住む中高年や高齢者、単身者の人たちが大きな被害を受けた災害でした。一般に住宅には収入や財産などの差による階層性が出ますが、地震が早朝に起きたことから住宅被害がそのまま被災者層を形成するという結果となった災害です。
-
亡くなった人の多くが圧死とは今まで誰も想定していなかったと聞きました。
 日本の都市は限られたエリアに、たくさんの人が集中して住んでいます。そこに強い揺れが起きた例は戦後以降は経験していません。神戸に限りませんが、日本の都市では新しい建物が建っていく一方で、古い密集市街地が残り続けています。そこに住んでいる人たちの多くは長い間住み続けて、地域のコミュニティにつながっているので、できるならばその地域からは立ち退きたくないと考えています。その結果、ふるくからあるコミュニティは維持され、密集市街地が残り続けるのです。人々がそうした関係の中で暮らすのは、とてもまっとうなことなのですが、問題は長年、家屋が建て替えられずに来たため、住宅の性能が落ちていることです。そして不幸なことに、その人々が集中して住んでいる場所に、地震が早朝に起きたことで、多数の圧死者が出たのです。
日本の都市は限られたエリアに、たくさんの人が集中して住んでいます。そこに強い揺れが起きた例は戦後以降は経験していません。神戸に限りませんが、日本の都市では新しい建物が建っていく一方で、古い密集市街地が残り続けています。そこに住んでいる人たちの多くは長い間住み続けて、地域のコミュニティにつながっているので、できるならばその地域からは立ち退きたくないと考えています。その結果、ふるくからあるコミュニティは維持され、密集市街地が残り続けるのです。人々がそうした関係の中で暮らすのは、とてもまっとうなことなのですが、問題は長年、家屋が建て替えられずに来たため、住宅の性能が落ちていることです。そして不幸なことに、その人々が集中して住んでいる場所に、地震が早朝に起きたことで、多数の圧死者が出たのです。
-
高速道路や新幹線をはじめとするインフラという面ではどうでしょうか。
 高速道路の高架部分の倒壊や新幹線の橋脚被害など、建造物の強度は問題になりました。しかし、日本全体の高速道路網や新幹線網に壊滅的な影響を与えるような機能面での問題は出ませんでした。一方で、被災地の水道やガスはずたずたになり、大きな問題になりました。しかし、これも大きな揺れが来ても、切断されないような高い耐震性を持つ水道管、ガス管を敷設することで、解決できる問題です。つまり構造上の技術的解決策はおおよそ出ているわけですが、一方で地域におけるこれらインフラ機能の冗長性や継続性、代替性といった新たな課題を示した災害であったといえます。
高速道路の高架部分の倒壊や新幹線の橋脚被害など、建造物の強度は問題になりました。しかし、日本全体の高速道路網や新幹線網に壊滅的な影響を与えるような機能面での問題は出ませんでした。一方で、被災地の水道やガスはずたずたになり、大きな問題になりました。しかし、これも大きな揺れが来ても、切断されないような高い耐震性を持つ水道管、ガス管を敷設することで、解決できる問題です。つまり構造上の技術的解決策はおおよそ出ているわけですが、一方で地域におけるこれらインフラ機能の冗長性や継続性、代替性といった新たな課題を示した災害であったといえます。
 根底に存在する日本の社会構造の問題
根底に存在する日本の社会構造の問題
都市開発や住宅政策という面ではいかがでしょうか。
 神戸市は1970年代から、六甲山系を切り開き、そこから出た土砂で海を埋め立て、人工島とニュータウンを作る都市開発手法を採用してきました。具体的には、便利で広大な近代的な住宅地を新しく作り出しそこに人を住まわせるというもので、それは経済性、効率性、利便性を重視した20世紀型開発の典型例といえます。しかし、そうした形で都市開発の一方で、都市部の老朽木造密集市街地は課題として積み残されたままだったわけです。結果的にこれらの地域のコミュニティに頼りながら生活してきた社会的に弱い立場の人々が大きな被害を受けたのが震災でした。そう考えると、阪神・淡路大震災は20世紀的な都市の作り方、地域での人の住まい方、住宅のあり方をもう一度考え直した方がよいという自然からの激烈なメッセージだったということができます。
神戸市は1970年代から、六甲山系を切り開き、そこから出た土砂で海を埋め立て、人工島とニュータウンを作る都市開発手法を採用してきました。具体的には、便利で広大な近代的な住宅地を新しく作り出しそこに人を住まわせるというもので、それは経済性、効率性、利便性を重視した20世紀型開発の典型例といえます。しかし、そうした形で都市開発の一方で、都市部の老朽木造密集市街地は課題として積み残されたままだったわけです。結果的にこれらの地域のコミュニティに頼りながら生活してきた社会的に弱い立場の人々が大きな被害を受けたのが震災でした。そう考えると、阪神・淡路大震災は20世紀的な都市の作り方、地域での人の住まい方、住宅のあり方をもう一度考え直した方がよいという自然からの激烈なメッセージだったということができます。
もう少し具体的にお話しください。
 確かに強度の弱い住宅が倒壊し、多くの方々が亡くなったのですが、ではなぜそうした住宅に社会的弱者が多く住んでいたのでしょうか。高齢者の死者が多いという事実を取ってみても、外国の専門家と議論すると、「家族はどうしていたのだ。一緒にいなかったのか」と不思議がられます。つまりそこには、低所得の高齢者が、単身または夫婦のみで文化住宅に住んでいるという日本の社会構造の問題が横たわっているのです。その結果が被害として表れたわけで、それは建物の耐震基準を高めるだけでは解決しません。根本にある、20世紀型開発のあり方や家族・地域コミュニティのあり方を見直していくことが必要です。
確かに強度の弱い住宅が倒壊し、多くの方々が亡くなったのですが、ではなぜそうした住宅に社会的弱者が多く住んでいたのでしょうか。高齢者の死者が多いという事実を取ってみても、外国の専門家と議論すると、「家族はどうしていたのだ。一緒にいなかったのか」と不思議がられます。つまりそこには、低所得の高齢者が、単身または夫婦のみで文化住宅に住んでいるという日本の社会構造の問題が横たわっているのです。その結果が被害として表れたわけで、それは建物の耐震基準を高めるだけでは解決しません。根本にある、20世紀型開発のあり方や家族・地域コミュニティのあり方を見直していくことが必要です。
しかしこうした問題は、社会根源的な課題であるがために、一朝一夕に解決するものではありません。そこで防災対策を行う際、こうした根本的な問題は横に置いて、耐震化を進めるという形がどうしても主流になってしまいます。
震災から15年が経ち、経験や教訓の風化がいわれますが、非常に危惧を感じるのは、先に述べたような根本的な問題提起が忘れ去られようとしていることです。その点がきちんと意識化され、そうした問題意識にもとづいた国や自治体の施策が行われないかぎり、仮に都市部で大地震が起きれば、また同じような被害が出るのではないか、という危機感を持っています。
 震災前の計画の見直しなしに行われた復興
震災前の計画の見直しなしに行われた復興
様々な経緯と歴史の中で作られてきた社会や人々のあり方が
震災で露わになったということでしょうか。
 その通りです。確か兵庫県の震災復興計画の基本理念においても「20世紀型の都市のあり方が根本的に否定された災害だ。より人間らしい空間や生活のスタイルを目指していかなければならない」といったニュアンスが述べられていたと記憶しています。防災上の個々の課題は解決していかなければなりませんが、そればかりにとらわれるのではなく、人間が人間らしく生きていくために、どのような都市を作っていくのかという視点を根本にすえる必要があると思います。
その通りです。確か兵庫県の震災復興計画の基本理念においても「20世紀型の都市のあり方が根本的に否定された災害だ。より人間らしい空間や生活のスタイルを目指していかなければならない」といったニュアンスが述べられていたと記憶しています。防災上の個々の課題は解決していかなければなりませんが、そればかりにとらわれるのではなく、人間が人間らしく生きていくために、どのような都市を作っていくのかという視点を根本にすえる必要があると思います。
実際には震災後の具体的な復興策は必ずしも、そうした方向に向かって行われてきたわけではありません。震災から5年後の2000年、復興を検証する国際会議が開かれたのですが、そこでいわれたのが「震災前に描かれていた都市の姿がそのままできあがっている」ということでした。震災前に計画されていた都市計画や再開発のプランに従い復興都市の形ができあがっていったのです。そこでは震災を経験した神戸のアイデンティティはどこにあるのか、本当に復興したのか、ということが問われました。
阪神・淡路大震災によって、神戸が行ってきた20世紀型の都市づくりが否定されたとすれば、震災前に立てられた計画は根本から見直さなければいけないはずです。そのためには、具体的な施策ではなく、都市づくりの上位概念を変えるような取り組みが必要です。それを自治体がやろうとしたら、関係する数百の法律をはじめ、あらゆるものを変えなくてはなりません。実際、被災者を目の前にしている状況では、そのような余裕もあるはずがなく、まずはスピードを持って復旧施策を行わねばなりません。残念ながら都市政策や都市計画において教訓を生かすには時間が必要です。
しかし、そうした問題意識を持っているのは、阪神・淡路大震災を経験した人以外にはほとんどいません。多くの人々は、自分たちが直接震災を経験していないので、「今までの都市づくりではダメだ」と指摘されても、実感が持てないのです。そのため、この15年の間でも、災害後の都市復興やまちづくりを支援するような抜本的な法制度の整備はほとんど進んでいないのが実情です。
 まちづくりの動きを合流させて、都市づくりにつなげる
まちづくりの動きを合流させて、都市づくりにつなげる
上から一挙に変えることができないとすれば、どうすればよいのでしょうか。
 今までのやり方を全国レベルで一挙に転換するのはなかなか難しいと思います。そうした中では、都市の作り方はゆっくりとしか変わっていかないわけですから、まちに住む市民が人間らしく暮らせる都市づくり、まちづくりとは何かという問題意識を持って動いていく以外にありません。そこで具体的な課題が出てきて、それを解決したいという動きを市民の側が作り出し、そのためには法律も変える必要があるという声が出てきて、それが全国に広がっていく。そうした地域からの動きを10年単位という長期的な視野に立ちながら、作り出していくのです。
今までのやり方を全国レベルで一挙に転換するのはなかなか難しいと思います。そうした中では、都市の作り方はゆっくりとしか変わっていかないわけですから、まちに住む市民が人間らしく暮らせる都市づくり、まちづくりとは何かという問題意識を持って動いていく以外にありません。そこで具体的な課題が出てきて、それを解決したいという動きを市民の側が作り出し、そのためには法律も変える必要があるという声が出てきて、それが全国に広がっていく。そうした地域からの動きを10年単位という長期的な視野に立ちながら、作り出していくのです。
阪神・淡路大震災は、残念ながら都市づくりという大きなスケールでは新しい動きを作り出せていませんが、しかし小さなスケールのまちづくりというレベルで見ると、「復興まちづくり」というキーワードは確かに全国に知れ渡り、それが日常の「防災まちづくり」の活動として徐々に拡がってきています。そうした動きや関連して生まれた制度などをひとつに合流させて、これからの都市づくりにつなげていくようにする必要があると思います。
また、災害を防ぐための予防的な対策だけでなく、復旧・復興という手段も使いながら、社会全体をより安全な側に近づけていく社会的な仕組みや制度を作り出していくことも求められています。そのためには、まず私たち自身が自分の生活の仕方を問い直して、住まいと地域の関係性を考え直すことです。自分が抱えている災害に対するリスクはどの程度なのかを明らかにした上で、それをどう地域全体で解決していくのかを皆が考える社会にしていくことが求められています。
住民や市民の自主的な取り組みが突破口になるというお話だと思うのですが、
具体的にどこから始めていけばよいのでしょうか。
 全く正反対のことがふたつあります。ひとつは強い地震が起こると、阪神・淡路大震災のような大きな被害が出るということはほぼすべての人が意識しています。ですから、それをベースに、すべてのことを「安全か安全でないか」という基準で、考えるようにしていくことです。今ほとんどの人は、食品を買う時には食品リスクをチェックしながら、一つひとつ丁寧に選んでいます。これと同じように、人々が住まいや職場を選ぶ際に、「安全の基準を軸に判断する」という視点を持つように、社会や人の意識を変えていくことです。地域活動のレベルではそうした動きがかなり出てきていますので、こうした動きを個人個人のレベルにまで落とし込んでいくことができれば、大地震の被害を減らすことができるはずです。
全く正反対のことがふたつあります。ひとつは強い地震が起こると、阪神・淡路大震災のような大きな被害が出るということはほぼすべての人が意識しています。ですから、それをベースに、すべてのことを「安全か安全でないか」という基準で、考えるようにしていくことです。今ほとんどの人は、食品を買う時には食品リスクをチェックしながら、一つひとつ丁寧に選んでいます。これと同じように、人々が住まいや職場を選ぶ際に、「安全の基準を軸に判断する」という視点を持つように、社会や人の意識を変えていくことです。地域活動のレベルではそうした動きがかなり出てきていますので、こうした動きを個人個人のレベルにまで落とし込んでいくことができれば、大地震の被害を減らすことができるはずです。
一方で、人間は誰でも危険事象について考えたくないため、思考の中で最初に外してしまいます。危険であるということばかりを考えていては、うかつに外も歩けなくなってしまいます。ある程度のリスクを受け入れた中で人々は行動せざるを得ませんが、通常は考えないようにしているわけです。そのため、危機意識を最優先とした取り組みを行っても、人々の納得はなかなか得られませんし、得られても長続きはしないものです。ですから、人々が意識しない中でも、防災力を高めていくような施策を、国や自治体は継続的に推進していくことが必要です。人々の認識を得なくとも防災力は維持され、向上される必要があるわけです。
 防災力を高め、人間らしく暮らせる都市を目指す
防災力を高め、人間らしく暮らせる都市を目指す
都市の安全力を高めるためには、
継続的な取り組みが欠かせないということですね。
 「安心できること」はゴールではありません。なぜなら、安心した途端に、安全ではなくなるからです。「ここでは地震は起きない」と安心した瞬間に、地震に対する対策がおろそかになります。地震で被害を受けた場所に調査に行くと、「自分のところでは起きないと安心しきっていた」という声が必ず、出てきます。「どうして安全だと思っていたのか」と聞いても、「そう思っていた」という答えしか返ってこないわけです。仮に人々の意識がそうだとしても、被害が出ないように安全力を高めていかなければなりません。
「安心できること」はゴールではありません。なぜなら、安心した途端に、安全ではなくなるからです。「ここでは地震は起きない」と安心した瞬間に、地震に対する対策がおろそかになります。地震で被害を受けた場所に調査に行くと、「自分のところでは起きないと安心しきっていた」という声が必ず、出てきます。「どうして安全だと思っていたのか」と聞いても、「そう思っていた」という答えしか返ってこないわけです。仮に人々の意識がそうだとしても、被害が出ないように安全力を高めていかなければなりません。
そうした中で、安全性を担保するひとつの手段が規制や法律です。国や自治体の一番大きな役割は、規制や法律にもとづく形で施策を進め、都市の安全力を高めることです。それに対して、経済合理性のみを重視するような規制緩和は安全力を下げてしまう典型的な例です。日本が低成長時代に入る中で、今までと同じ価値観で都市の管理を行えば、都市の防災性能は確実に下がってしまいます。そうした認識を踏まえて、50年先、100年先を見据え、20世紀型の都市づくりから転換し、人間が人間らしく生きていける21世紀型の都市を作り出していくために、私たち一人ひとりが努力し、防災力を高める取り組みを持続的に行っていくことが重要です。