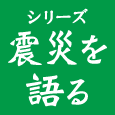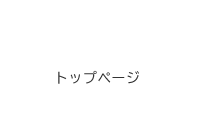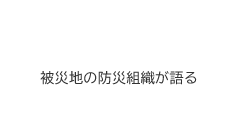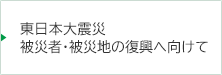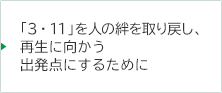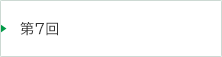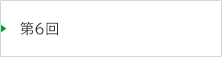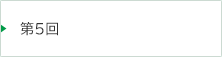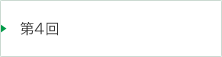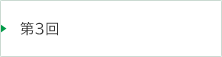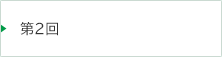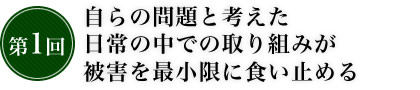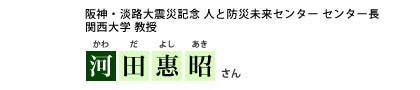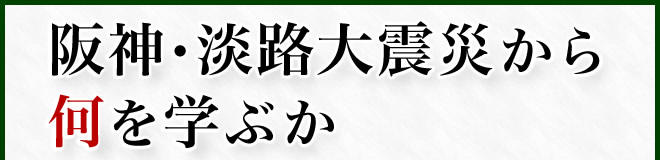
1995年に起こった阪神・淡路大震災。
6,434名に及ぶ死者をはじめ、被災した多くの人たちは深い悲しみと大きな打撃を受けました。また、震災の爪痕は深く、15年経った今なお、その被害に苦しんでいる人々も多くいます。一方で、この数年を見ただけでも、全国各地で地震や集中豪雨、台風による災害が発生し、多くの犠牲者が出るなど、阪神・淡路大震災の教訓を生かすことは極めて重要になっています。
こうした中で、「阪神・淡路大震災から何を学ぶか」というテーマで、今回から12回にわたって、阪神・淡路大震災を振り返り、復興に向けて取り組んできた人々の姿を浮き彫りにすると共に、その教訓を明らかにしていきたいと思います。

 予想もしなかった住宅の下敷きによる圧死者の多さ
予想もしなかった住宅の下敷きによる圧死者の多さ
阪神・淡路大震災の被害で、研究者として想定していなかったことには
どんなことがあるのでしょうか。
 倒壊した住宅の下敷きで亡くなった人が全死者の9割を占めるとは考えもしませんでした。1923年の関東大震災では死者の9割が火災で亡くなったため、それまで地震対策イコール火災対策であり、「地震だ。火を消せ」と標語になっていたほどです。学者も国も自治体も、火災を出さないこと、広域の延焼を食い止めることをポイントにして地震対策を進めてきました。ところが、阪神・淡路大震災では住宅の下敷きになって、ほんとうにたくさんの人が亡くなりました。まさかそんな事態になるとは思ってもみませんでした。
倒壊した住宅の下敷きで亡くなった人が全死者の9割を占めるとは考えもしませんでした。1923年の関東大震災では死者の9割が火災で亡くなったため、それまで地震対策イコール火災対策であり、「地震だ。火を消せ」と標語になっていたほどです。学者も国も自治体も、火災を出さないこと、広域の延焼を食い止めることをポイントにして地震対策を進めてきました。ところが、阪神・淡路大震災では住宅の下敷きになって、ほんとうにたくさんの人が亡くなりました。まさかそんな事態になるとは思ってもみませんでした。
阪神・淡路大震災の2週間ほど前に起きた三陸はるか沖地震は震度6強で、死者は1人です。同じ震度ですから、震度情報を聞いた段階では、それほど死者は出ないだろうと考えていました。ところがラジオで放送される死者の名前がどんどん増えていくのです。一体どこまでいくのだと愕然としました。
古い木造住宅がいとも簡単につぶれ、早朝5時46分だから寝ている人が多くて、それで押しつぶされたわけです。当時の兵庫県の高齢化率は15%なのに、亡くなった人の45%が高齢者です。多くの高齢者が古い木造住宅の1階で寝起きしていたという実態が死者の多さとその構成からうかがい知ることができます。
現在も木造住宅の耐震化は大きな問題ですか。
 最大の問題です。木造住宅の耐震補強は進んでおらず、日本全体で1,200万戸もが耐震不適格です。地震による人的被害を最小限に食い止める切り札は古い木造住宅の耐震状況を診断し、耐震補強を行うことです。住宅が倒壊したとしても、阪神・淡路大震災のように、たくさんの人が亡くなるようなことにはしたくありません。
最大の問題です。木造住宅の耐震補強は進んでおらず、日本全体で1,200万戸もが耐震不適格です。地震による人的被害を最小限に食い止める切り札は古い木造住宅の耐震状況を診断し、耐震補強を行うことです。住宅が倒壊したとしても、阪神・淡路大震災のように、たくさんの人が亡くなるようなことにはしたくありません。
西日本の太平洋岸に沿って、南海トラフと呼ばれる4,000メートル級の深くて広い溝が走っています。これに沿って、100-150年間隔でマグニチュード8クラスの地震が起こっています。これが東海、東南海、南海地震です。関西地方に大きな被害をもたらすと想定される南海地震が起こる可能性が最も高いのが2030-35年で、まだ20年ほどの余裕があります。そこで、これから5-6年かけて、耐震パネルを普段寝起きしている居間や寝室に張っていこうと各自治体に提案しています。パネルは工賃含めて壁1枚8万円ほどかかりますが、高齢者だけで暮らしていても、子どもたちがお金を出したり、アパートであれば入居者がお金を出し合えば、老朽化したアパートや木造住宅でも比較的容易に耐震化することができます。住宅一棟丸ごとの耐震化は、自治体が補助金を出しても300万円ほどもかかるためなかなか進みません。ですから、住宅一棟丸ごとの耐震化よりも、はるかに簡単で実効性があります。
 道路は最も大切なライフライン。がれき除去が最大の課題
道路は最も大切なライフライン。がれき除去が最大の課題
他にも想定していなかったことがあるのでしょうか。
 がれきの量の多さです。神戸市で毎日出るゴミのほぼ25ヶ月分に匹敵する1,850万トンのがれきが出て、その処理に3ヶ月もかかりました。その後の研究で、今後30年以内に70%の確率で発生すると推定されるマグニチュード7クラスの首都直下地震では9,600万トン、大阪市の中心部で震度7になると見られる、大阪府を南北に走る上町断層帯地震では1億2,000万トンのがれきが出ることが分かりました。首都直下地震で、阪神・淡路の5.4倍、上町断層帯に至っては実に6倍強です。大阪府のがれきの量がこれほど多いのは戦前からの古い木造住宅が大量に残っているからです。東京は1945年の東京大空襲で大量の焼夷弾が投下され、木造住宅がほとんど燃えてしまいました。ところが大阪ではアメリカ軍が狙ったのが大阪城に隣接する軍の工場だった砲兵工廠で、焼夷弾ではなく、大量の爆弾を投下したため、住宅が東京に比べると焼けませんでした。それが東京と大阪のがれきの量の差として、出てきています。
がれきの量の多さです。神戸市で毎日出るゴミのほぼ25ヶ月分に匹敵する1,850万トンのがれきが出て、その処理に3ヶ月もかかりました。その後の研究で、今後30年以内に70%の確率で発生すると推定されるマグニチュード7クラスの首都直下地震では9,600万トン、大阪市の中心部で震度7になると見られる、大阪府を南北に走る上町断層帯地震では1億2,000万トンのがれきが出ることが分かりました。首都直下地震で、阪神・淡路の5.4倍、上町断層帯に至っては実に6倍強です。大阪府のがれきの量がこれほど多いのは戦前からの古い木造住宅が大量に残っているからです。東京は1945年の東京大空襲で大量の焼夷弾が投下され、木造住宅がほとんど燃えてしまいました。ところが大阪ではアメリカ軍が狙ったのが大阪城に隣接する軍の工場だった砲兵工廠で、焼夷弾ではなく、大量の爆弾を投下したため、住宅が東京に比べると焼けませんでした。それが東京と大阪のがれきの量の差として、出てきています。
がれきはどうして問題になるのでしょうか。
 阪神・淡路大震災後の15年間の研究によって、最も大切なライフラインは電気や水道、電話ではなく、道路だということが分かってきました。警察や消防、自衛隊がいくら装備を整え、フットワークをよくして、災害時の緊急対応ができるようにしても、道路ががれきに埋もれていたのでは、身動きがとれません。そして、復旧、復興も進みません。道路のネットワークを維持する上で、最大の阻害要因ががれきなのです。ですから、がれきをできるだけ出さないようにし、住宅の倒壊等で発生してしまったがれきを速やかに取り除くことが極めて重要なのです。
阪神・淡路大震災後の15年間の研究によって、最も大切なライフラインは電気や水道、電話ではなく、道路だということが分かってきました。警察や消防、自衛隊がいくら装備を整え、フットワークをよくして、災害時の緊急対応ができるようにしても、道路ががれきに埋もれていたのでは、身動きがとれません。そして、復旧、復興も進みません。道路のネットワークを維持する上で、最大の阻害要因ががれきなのです。ですから、がれきをできるだけ出さないようにし、住宅の倒壊等で発生してしまったがれきを速やかに取り除くことが極めて重要なのです。
阪神地区は海に面して、都市が串ダンゴ状に連なっているので、道路ががれきに埋もれて通行できなくても、海から救援のために街に入っていくことができました。しかし、首都直下地震の場合、被害は震源からタマネギ状に広がり、臨海部は限られていますから、海から近づくことはできません。その意味で道路の果たす役割が全く異なり、極めてウェイトが高いのです。ですから、がれきの処理を速やかに行うことが大変重要なのです。
 災害対応は「日常、やっていることしかできない」
災害対応は「日常、やっていることしかできない」
阪神・淡路大震災から15年が経ちましたが、
その教訓は生かされているのでしょうか。

 阪神・淡路大震災の最大の教訓は自治体から、地域コミュニティ、住民に至るまで、災害対応は日頃、やっていることしかできないという点にあります。いざという時に、インターネットを使おうとパソコンを配っても、パソコンに触れたことのない人にインターネットは使えません。ですから、日頃やっていることの延長上で、災害対応はやらなくてはいけないのです。そうした観点から、近畿圏の各府県では通常の事業や活動の中に、防災対策をはめ込むようにしています。例えば、奈良県では、年間約1,000件の事業を実施しています。震災対応の業務は301件あるので、そのままでは施策は合計で約1,300件になってしまいます。それを再調整して、1,000件の中に入れ込みました。具体的には、集中豪雨で、道路が不通になった場合、今までは土木部しか対応していませんでした。けれども、通行止めは長期化するかもしれないので、医療や食料、学校など地域住民の生活に大きな影響を与える様々な問題が出てきます。そこで、そうした関連業務も一緒に動くようにしました。そして、それを定めた県の地震防災アクションプランは当時82人いた課長全員の出席の下で、議論を行い、策定しました。全員が参加することで、防災対応はどの課でも人ごとではなくなり、自分たちの仕事の一部になりました。
阪神・淡路大震災の最大の教訓は自治体から、地域コミュニティ、住民に至るまで、災害対応は日頃、やっていることしかできないという点にあります。いざという時に、インターネットを使おうとパソコンを配っても、パソコンに触れたことのない人にインターネットは使えません。ですから、日頃やっていることの延長上で、災害対応はやらなくてはいけないのです。そうした観点から、近畿圏の各府県では通常の事業や活動の中に、防災対策をはめ込むようにしています。例えば、奈良県では、年間約1,000件の事業を実施しています。震災対応の業務は301件あるので、そのままでは施策は合計で約1,300件になってしまいます。それを再調整して、1,000件の中に入れ込みました。具体的には、集中豪雨で、道路が不通になった場合、今までは土木部しか対応していませんでした。けれども、通行止めは長期化するかもしれないので、医療や食料、学校など地域住民の生活に大きな影響を与える様々な問題が出てきます。そこで、そうした関連業務も一緒に動くようにしました。そして、それを定めた県の地震防災アクションプランは当時82人いた課長全員の出席の下で、議論を行い、策定しました。全員が参加することで、防災対応はどの課でも人ごとではなくなり、自分たちの仕事の一部になりました。
市町村や住民レベルの対応はどうなのでしょうか。
 県のアクションプラン策定の翌年、天理市と橿原市が先行事例として、アクションプラン策定に取りかかりました。それが2年でできあがり、その後全市町村でアクションプランが作られました。その結果、今まで県では自主防災組織の組織率程度位しか分からなかったのが、市町村が災害時にどんな活動をするのかが分かるようになりました。そうすると、県として、やらなければならないことがはっきりします。例えば、何も分からない状態では、まず食料と水を入れなくてはいけないということになります。しかし、今では、それは市町村に備蓄されているので、真夏であれば、ウェットティッシュを入れるなど、きめ細かな対応をするというようになっています。
県のアクションプラン策定の翌年、天理市と橿原市が先行事例として、アクションプラン策定に取りかかりました。それが2年でできあがり、その後全市町村でアクションプランが作られました。その結果、今まで県では自主防災組織の組織率程度位しか分からなかったのが、市町村が災害時にどんな活動をするのかが分かるようになりました。そうすると、県として、やらなければならないことがはっきりします。例えば、何も分からない状態では、まず食料と水を入れなくてはいけないということになります。しかし、今では、それは市町村に備蓄されているので、真夏であれば、ウェットティッシュを入れるなど、きめ細かな対応をするというようになっています。
一方、住民は行政が何をやるかが見えるようになりました。行政はこうした活動をやるということをはっきりさせたことで、住民に対する啓発事業を積極的に行うことができるようになりましたし、対策の抜けや漏れもなくなりました。
 地震は起こらないと思い込んでいた地域で大きな被害
地震は起こらないと思い込んでいた地域で大きな被害
全国レベルで見た時にはどうなのでしょうか。
 この15年、様々な地域で大規模な地震や災害が起こりましたが、大きな被害を出したのはすべて、自分の所では地震は起こらない、人ごとだと思っていたところです。輪島にしても、柏崎、宮城栗原にしても、全く準備がありませんでした。災害が発生する可能性が高まっているにもかかわらず、被災地以外は防災に対する意識が高まっていないのが実情です。
この15年、様々な地域で大規模な地震や災害が起こりましたが、大きな被害を出したのはすべて、自分の所では地震は起こらない、人ごとだと思っていたところです。輪島にしても、柏崎、宮城栗原にしても、全く準備がありませんでした。災害が発生する可能性が高まっているにもかかわらず、被災地以外は防災に対する意識が高まっていないのが実情です。
全国的に見ると、西高東低で、阪神地区から遠くなるほど、対策が遅れています。例えば、2008年の岩手県奥州市と宮城県栗原市で震度6強を記録した岩手・宮城内陸地震はけが人がとても多い結果となりました。全半壊・一部損壊家屋を分母に、けが人を分子にして計算すると、けが人の比率は2004年の新潟中越地震の10倍にもなります。
前にも述べたように、地震で人が亡くなるかどうかは家がどれだけつぶれるかにかかっているため、耐震診断・耐震補強が対策の切り札です。しかし、けがは常日頃、地震が起こる可能性が高いと考えていれば、かなりの程度防ぐことができます。特に高齢者は頭で考えていることと、身体の動きが一致しないので、起きるはずはないと思い込んでいた地震が起きると、あわてて廊下を曲がらなければいけないのに、まっすぐ突っ込んでいったり、玄関でつまずいたりして、けがをしてしまいます。
一方、静岡県では、東海地震がマグニチュード8クラスで確実に起こるとして様々な対策がとられており、住宅の家具固定率は64%と全国の2.5倍にもなっています。そのため、2009年8月に発生した駿河湾沖地震でけがをした人は非常に少なく、死者もひとりだけでした。
 様々な対策を組み合わせ、巨大な複合型災害に備える
様々な対策を組み合わせ、巨大な複合型災害に備える
お話をお聞きしていると、日常的な心構えや対策が大きな効果を
発揮するように思えます。
 その通りです。特効薬的なものはなくても、今まで述べたような様々な対策を集めれば、効果は非常に大きくなります。例えば、玄関の靴が整理整頓してある家は屋内も整理整頓してあり、地震によるけが人は少ないのです。けが人がたくさん出るのは階段の踊り場に物が積んであったり、タンスの上に雑誌が縛って置いてあるような家です。
その通りです。特効薬的なものはなくても、今まで述べたような様々な対策を集めれば、効果は非常に大きくなります。例えば、玄関の靴が整理整頓してある家は屋内も整理整頓してあり、地震によるけが人は少ないのです。けが人がたくさん出るのは階段の踊り場に物が積んであったり、タンスの上に雑誌が縛って置いてあるような家です。
また、災害が起こった時に、真っ先に必要なのは家族の安否確認です。そのためにNTTは伝言ダイヤルや伝言メッセージを提供していますが、災害発生時にはすぐに回線がいっぱいになってしまいます。その負担を減らすには、家族が毎日どのような行動をしているかを皆が把握していることが大切です。そして、たまたまその日だけ違った行動をしているとすれば、そこだけ確認するのです。例えば、子どもが塾に通っている時に地震が起きたとしても、電車に乗っている時間であれば安否確認が必要ですが、塾にいるのであれば、まず大丈夫です。
もちろん国や地方自治体の防災対策は重要ですが、私たち一人ひとりが地震や災害を人ごとと思わずに、みずからの問題と考えて、住宅の耐震診断・耐震補強から日常生活の中での行動まで、意識的に対策を行うことが重要です。特に直下型地震による液状化で堤防が低くなる中での地球温暖化の影響による巨大な台風の襲来や集中豪雨など都市部を中心に今まで予想したこともないような巨大な複合型災害が起きる可能性が高まっています。そうしたことも含めて、阪神・淡路大震災の教訓に学び、一人ひとりが防災・減災に取り組んでいく必要があります。