類焼損害保障特約 ※1
自宅が火元となり、近隣の住宅や家財に損害が生じた場合の保障
支払限度額1億円
自然災害である以上、地震はいつどこで起こるかわかりません。もし、通勤・通学中や買い物の途中、大きな街にいる時に地震が起きたら、どんな状況になるか考えてみたことはありますか?渋谷の街を例にご紹介します。

まず、比較的想像しやすいのが、大きなビルの窓が割れたり看板が外れたりして、歩行者の頭上にガラスの破片やコンクリート片が落下することです。揺れを感じたら慌てて外に出る人が多いですが、建物の中に留まることで被害を防げることもあります。また、停電により信号機の故障が発生し、交通が麻痺し事故が発生する可能性もあります。
外出先で地震が起きると、早く帰宅したい、家族の安否を確認したいという気持ちになると思います。気持ちが焦った人たちが発生直後、駅に殺到し将棋倒しになり新たな被害を生むことも考えられます。渋谷は土地が低く谷になっており、液状化により歩道が波打ったり泥水が溢れ出したり、転倒など予期せぬ被害も多く潜んでいます。
駅に向かうにつれてすり鉢状になっている渋谷では、多くの人が一気に下へ向かってなだれこむことが予想されます。冷静に考えれば、大地震の直後に駅に向かっても電車は動いていないはずです。「群衆なだれ」に巻き込まれないためにも、できるだけ高い方へ避難することが望ましいです。居合わせた場所によって避難すべき方向は異なります。普段よく訪れる街の特徴や避難経路・避難場所は事前に確認しておくとよいでしょう。
こちらは、危機管理の専門家が、出かける際に必ず持ち歩いているものの写真です。

①止血パッド ②ワセリン ③ヘッドライト ④ゴミ袋(黒) ⑤モバイルバッテリー ⑥シート状のソーラーパネル ⑦ゼリー飲料 ⑧おやつ
これらすべてを毎日持ち歩くのは難しいかもしれません。ただ、なぜこれらが必要と考えているかを知るだけでも防災意識が変わってくるはずです。
例えば「不透明のゴミ袋」。首を通す穴を開けて雨具や防寒具として、街中で身動きが取れなくなった時地面に座って休憩する際の敷物として、水筒などを持っていない時の給水袋として、究極はトイレがない場所で用を足す際に身体を覆う目隠しとして使うこともできます。畳むとコンパクトになるので、バッグに1枚入れておくのは負担も少なくすぐに始められるかもしれません。防災グッズを揃えることも大切ですが、どんな時にどう使うのかを想像することも同じくらい大切なことです。
外出中に被災すると、家族となかなか連絡が取れず安否確認ができなくて不安になることも想定されます。地震が起きた時に有効な連絡手段や待ち合わせの方法について、家族構成や住んでいる地域の特性に合わせて考えてみましょう。
まずは連絡手段。比較的つながりやすいのは公衆電話ですが、最近は携帯電話も災害時にもつながるように改善を進めているようです。携帯電話で使えるアプリの中では、東日本大震災を機に開発されたLINEがつながりやすいそうです。X(旧Twitter)も情報収集に役立ちますが、誤報やデマなども散見されるので冷静な判断が必要です。
家族が離れた場所で被災したことを想定して、待ち合わせ場所を「具体的」にすり合わせておくことが重要です。そして、地震直後の避難所は人で溢れかえっているため、「10時・15時・20時の 1日3回」「(避難所となっている)学校の鉄棒の横で」「20分だけ待つ」というように、細かく待ち合わせの条件を決めておくのが良いです。これも、地震が起きた時の状況をシミュレーションしておくことで初めて十分な準備ができます。
発災時、小学生は保護者への引き渡しが基本ですが、地域によっては、中学生は各自で帰宅させる場合もあるので、お子さんの学校の災害時の対応についても日頃から調べておく必要があります。
これまでお伝えした通り、大地震が起きた際、被害を最小限に抑えるには、自分がいつどこにいてどんな災害が起きるかを、平常時にどれだけ考えられるかにかかっています。「もしもの100」は、震災時に役に立つ防災グッズや、知っておくと便利な防災知識を100個、親しみやすいイラストと共に紹介しています。
100個の中で特に注意を引くのが、75番目の「冷静な判断ができるのは10%」という数字かもしれません。私は大丈夫と思っていても、いざという時にパニックになって思考停止になる方が多いようです。例えば「1秒でキッチンを出る、3秒で家を出る」など、具体的な行動を数字で覚えておくだけで素早く行動できるようになります。
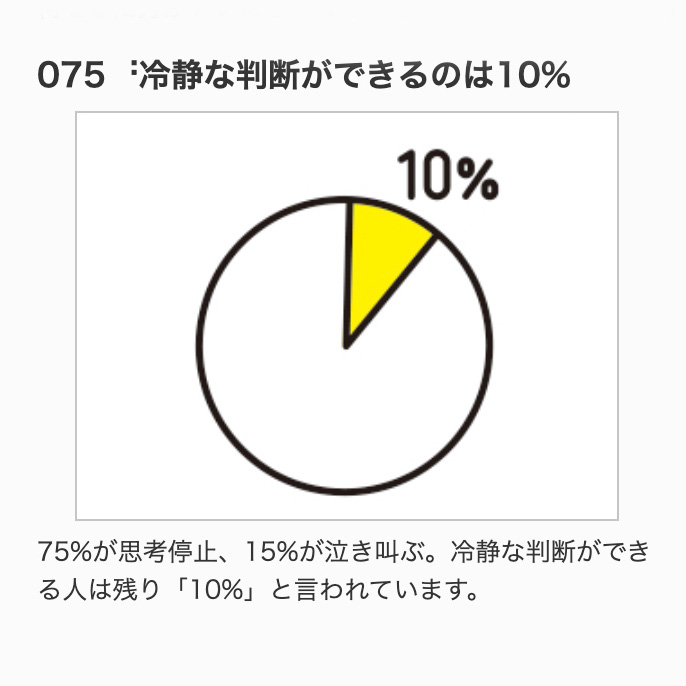
23番の「連絡先メモ」は、スマホに慣れてしまった私たちには盲点かもしれません。電子機器はいざというとき、故障したり充電が切れたり通信できない可能性もあります。重要な電話番号はメモを持ち歩くだけでも役立ちます。
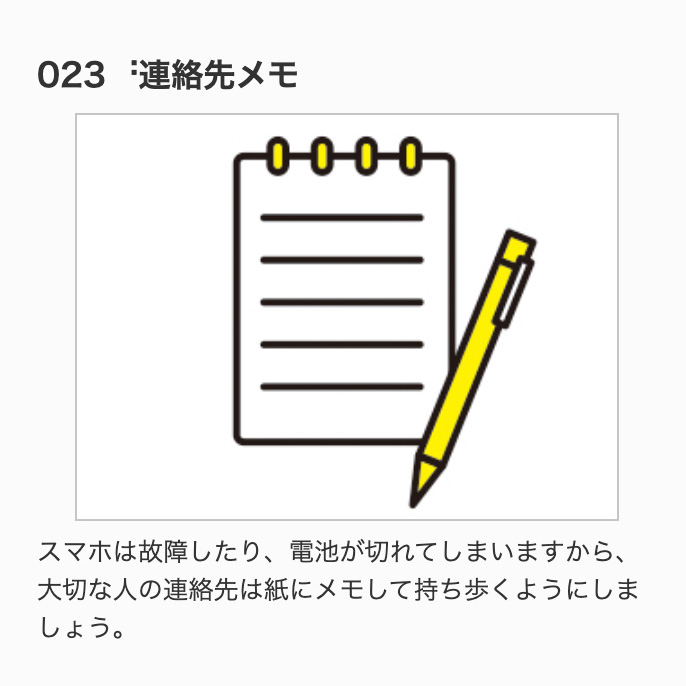
98番の「地下はむしろ安全」も目からうろこの情報です。窓や扉の少ない地下はどうしても不安な気持ちになり地上に出たくなりますが、とどまる勇気が必要な場合もあります。地震発生後のパニックで階段や出入り口に殺到するだけで事故につながるので、耐震性が強い場所で様子を見ることも必要です。万が一の浸水に備えて入口付近で様子を見ましょう。

首都直下型地震や南海トラフ地震の可能性はここ数年頻繁に耳にしますね。それでも私たちはその「いつか」を「いつか考える」と先延ばしにしがちです。地震はいつ何時起きるかわからないということを前提に、今いる場所で何ができるかを想像して備えることが、私たちの未来を守るために大切な行動だと考えて、一歩を踏み出してみませんか。
(前編として、家の中で地震が起きたらをテーマに、防災・減災のヒントをお伝えしています。)
>記事を読む



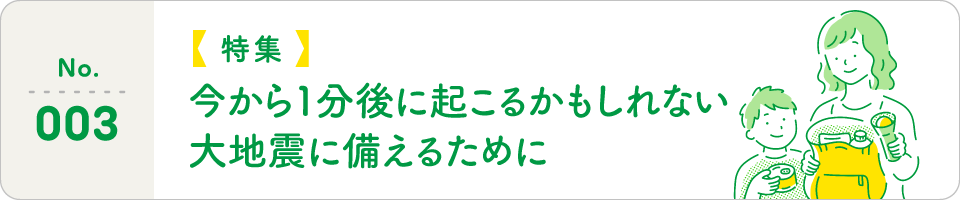

特約をプラスして、
よりワイドに保障。
基本の保障にプラスできる充実の特約。さまざまなリスクに備えて、幅広い保障を用意しています。
自宅が火元となり、近隣の住宅や家財に損害が生じた場合の保障
支払限度額1億円
家財の盗難による損害の保障
支払限度額300万円
貸主に対して賠償責任を負った場合の保障
支払限度額4,000万円
ご自身やご家族(同一生計の親族)が賠償責任を負った場合の保障
支払限度額3億円
※1 火災共済に30口以上加入している場合にセットできます。
※2 火災共済のみの加入で家財契約に30口以上加入している場合にセットできます。
※3 火災共済の家財契約に30口以上加入している場合にセットできます。
防災・減災活動、
もっと知りたい方はこちら